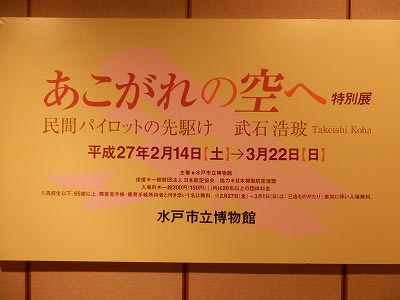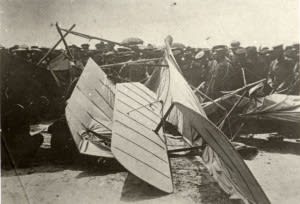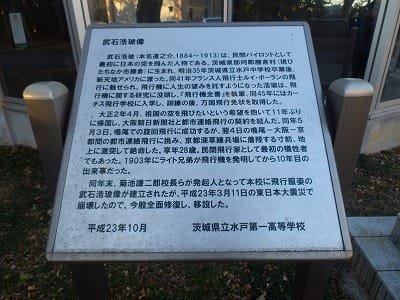昭和34(1959)年、氷川丸に乗船しアメリカに留学するT君を見送りにご家族と一緒に横浜に来たのは、今から56年前のことだ。
氷川丸は翌年の1960(昭和35)年には引退しているから、ほぼ最後の航海に近い。
船の寿命は約20年といわれ、1930(昭和5)年に竣工し、すでに船齢30年を経て、スクラップにされても不思議ではなかった氷川丸だったが、横浜港開港100年という節目に合わせ、新たに建設されるマリンタワーと共に港町横浜のシンボルとして生き続けることになった。
氷川丸は山下公園のシンボルのようで、目にはするが、乗船して内部を見てみようとは思わなかった。



2008年「日本郵船氷川丸」博物館としてリニュアールオープンした。

受付の脇には、日比野克彦さん制作の「段ボールの氷川丸」がお迎え。
パネル等で歴史を紹介。
1930年、三菱重工業横浜製作所で生まれた氷川丸は、総トン数1万1622トン、全長163.3メートル、船幅20.12メートル、船速18.21ノットという、当時の造船技術の粋を集めた、最新鋭の貨客船だった。
*大洗~苫小牧の大型フェリーが大洗港に停泊しているのを見慣れた目では、随分小さな船、これで太平洋を航行するのはさぞ揺れたことだろう、等と思っていたが、乗船してみると大きく感じられた。
氷川丸は日本郵船の太平洋横断シアトル航路の貨客船として就航した。
太平洋戦争中は、日本海軍に徴用されて主に南方での病院船として用いられ、終戦後は復員輸送のための引き揚げ船の役目を担った。
1953(昭和28)年には11年ぶりにシアトル航路に復帰。
引退までに太平洋横断254回、船客数2万5千余名を越えた。



2008年のリニュアールにより一等食堂・一等社交室・一等客室などが当初の姿に復元された。

エンジンの音が聞こえてきそうな機関室。
現在の大型豪華客船とは比べようはないだろうが、材料の鉄はイギリスから、エンジンはデンマーク製、内装デザインはフランス製と贅を尽くした。
デザインやインテリアはアール・デコを基調とした。
海外留学が珍しい時代に高校生で留学し、東大を卒業後商社に勤務、ニューヨーク・モスクワに勤務したのち子会社に出向、出張先のロンドンで客死したT
君。「何れ一緒に旅しよう」と話したこともある。
波乱万丈の昭和を生き抜いた「氷川丸」に乗船し、亡きT君の思い出がよみがえった。