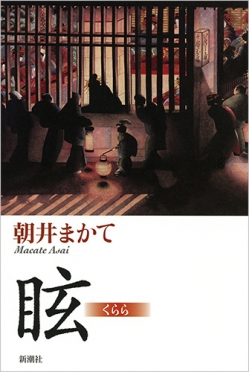①アリとニノ 面白さ:☆☆☆☆
著者:クルバン・サイード(エーレンフェルス ヌッシムバウム)
生年・出身地:エルフリーデ・フォン・エーレンフェルス 1894年 オーストリア
レフ・ヌッシムバウム 1905年 アゼルバイジャンのバクー
出版年:1937年 邦訳出版年:2001年 邦訳出版社:(株)河出書房新社
コメント:本書はウィーンで出版されベストセラーとなった。1971年にイギリス人がベルリンの古本屋で見つけてアメリカで出版、2000
年に再度アメリカとドイツで復刻された。舞台は第一次世界大戦前後のカスピ海沿岸のアゼルバイジャンのバクー。そこには
イスラム教徒やギリシャ正教徒のグルジア人やアルメニア人が暮らしている。グルジア人の豪商の娘ニノとイランの貴族でも
あるアリとの純愛物語である。二人はロシアの支配下でロシアの学校に通い、近代的な教養を持っていた。戦争とロシア革命
にザカフカス地方の民族は翻弄されていく。ロシアからトルコ、そして独立、またソビエトの下に。グルジアの踊りとか、イ
ランのハーレムの暮らしとか、興味深い場面が多い。著者の一人のヌッシムバウムはイスラム教に改宗したユダヤ人でベルリ
ンで学業を終えたジャーナリストだ。もう一人のエーレンフェルスはイスラム教に改宗した夫がいる、オリエント趣味の男爵
夫人である。
②世界地図の下書き 面白さ:☆☆☆
著者:朝井リョウ
生年・出身地:1989年 岐阜県
出版年:2013年 出版社:(株)集英社
コメント:児童養護施設「青葉おひさまの家」に預けらている小学校低学年4人と中学3年1人の物語。卒業生のためにランタンをつくって
飛ばす。自分たちで成し遂げたことは生きる力となる。
③ユダの季節 面白さ:☆☆☆
著者:佐伯泰英
生年・出身地:1942年 北九州市
出版年:2005年 出版社:KKベストセラーズ
コメント:スペインを舞台にした冒険小説。主人公はスペイン在住の日本人カメラマン。闘牛を取材している。時はフランコ独裁政権末
期。妻子を殺された主人公はある日本人がその事件にからんでいることを知る。日本赤軍やETA(バスクの祖国と自由)や政権
内部の権力闘争が絡んでくる。闘牛やスペインの風土の描写はいいが、スペインの政治がよくわからないこともあり、面白さ
はいまいち。
④堤未果のショック・ドクトリン 面白さ:☆☆☆
著者:堤未果
生年・出身地:東京都
出版年:2023年 出版社:(株)幻冬舎
コメント:ナオミ・クラインというカナダ人ジャーナリストの「ショック・ドクトリン」で著者は目覚めたという。
ーショック・ドクトリンとは、テロや戦争、クーデターに自然災害、パンデミックや金融危機、食糧不足に気候変動など、シ
ョッキングな事件が起きたとき、国民がパニックで思考停止している隙に、通常なら炎上するような新自由主義政策(規制緩
和、民営化、社会保障切り捨ての三本柱)を猛スピードでねじ込んで、国や国民の大事な資産を合法的に略奪し、政府とお友
達企業群が大儲けする手法です-
日本の例としては、東日本大震災、コロナパンデミックが危機であり、マイナンバーカードやファイザー・ワクチンの問題点
が列挙されている。プライバシーが危機にさらされているとか、なりすましが横行しているとか問題は多い。ファイザーのワ
クチンは有効だったのか心配になってくる。政府と当該企業との癒着がはなはだしいようだ。きちんとワクチンについての総
括を出すべきだ。