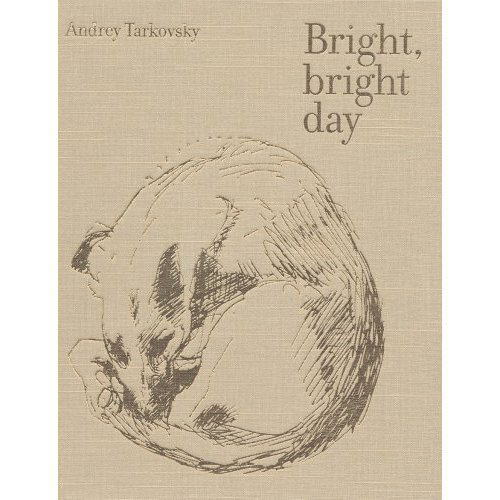★ それぞれ謎めいた顔をもつ遠くの葉。沢山の顔がある!大きな花びらをもった花々。花びらは毒のある性器の上に開いている。まったく沢山の性器があるものだ。さまざまに異なった、知ることのできない何千もの道。庭で、切手ほどの大きさしかない所に、何千もの生物が姿を隠している。大地は絶え間なく腐る。このこと、つまり腐ることしかしていない。水は、小さな丘からにじみ出る。ぽたぽたと空から落ちる。目は見ているようで、じつは見ていない。目は、暗闇を映している潜水艇の二つの窓のようなものだ。
★ 秘密がないということ、これが秘密だ。外側から見られた世界が、どうしようもなくそこにある。というのも、内面と呼ばれたもの、思想と呼ばれたものは、世界の外面にすぎなかったからだ。色のついた表面、一種の表皮のようなもの。本当の肉、部屋の内部、言葉と魂とはなにかといえば、それはあらゆる花と葉と果実と、皮膚と、小石と、足跡からなるもの、不可解なしるしに満ちたあの現実なのである。
★ 根と蔓と茎と枝と葉脈のほぐしようのない絡みあい。鏡はない。(自分の姿は見えない)。まなざしは、例外的な地点、支点とすべき唯一の場所を空しく求める。まなざしはそれを見つけられない。目は果実なのだ。
★ 女の美しさ。はじめは理解できず、困惑させられ、不安にさせられてしまう美しさ。その美しさはあまりにも奇蹟的だし、だれもみなひとしく美しいので、まるで、まやかしのように思えてしまう。どうしてこんなことがあり得るのか。腹いっぱいに食べることなんかほとんどなく、現代栄養学の基本的な成分には、おおむね事欠いている民族がここにいる。
★ わたしたち、肉をくらい、牛乳を飲み、ビタミン剤をとるものたち。あまりにも豊な富にあふれているので、その富を世界中に、飢えた民族や栄養不良の子供たちに分け与えることのできるわたしたち。しかもこれらの民族は、美しいということだけで復讐しているのだ。
★ インディオの女の美しさは光り輝いている。美しさは、内面から来るのではなく、肉体のあらゆる深みからやって来る。それは、果実の肌の美しさが、果肉全体で照らされ、樹木全体のあらゆる肉で照らしだされているのと同様である。
★ インディオの女の美しさは、自由の結果である。道徳や宗教の禁制を恐れることなく、あるがままであるという自由。自分の肉体と精神のために、労働と交合と分娩を選ぶ自由。愛さなくなった男から逃れ、気に入った男を求める自由。堕胎用の煎じ薬を飲む自由。子供が欲しくなければ、分娩の際に毒殺してしまう自由。気に入った家に住み、欲するものを所有し、憎むものを拒む自由。肉体の自由と裸身の自由。自分の顔を手入れする自由。競争相手もなく、自分自身の姿態以外には、他の何物とも競うことがないという自由。不品行の自由と分別の自由。
★ 躍動し、敏捷で、生々とした人間的な美の姿。水と太陽と蔓と樹木の美。肉体は逃れもしないし、隠れもしない。それは生命の恐るべき力のすべてを発散する。手は活動する。扇や、笊(ざる)や、籠を編むために、ナワラ織りの繊維が織りなす模様を、手は心得ている。肉体の内部にあり、樹々の葉や、鹿の皮や、蛇や魚のうろこの上にも記されている模様を手は知っている。
★ なにものももはや目をだますことはない。インディオの女たちの目は、黒い入り江のようだ。青銅色の顔のなかで静かにきらめきつつ、見つめている。目は《魂》にいたる扉として見開かれることなど決してない。
★ わたしたちの目の残忍さと貪欲。
しかしここには、河のほとりに立って動かない若い女の、見つめている目だけがある。(見つめている目)。
★ 言葉を沈黙に満ちたものにすることは容易ではない。わたしの喉の中につながれたスピーカーをにわかに止め、わたしの目の中に隠されたレンズに覆いをかけ、耳の底で振動している膜に穴を開けるのは容易ではない。わたしがやってみたいと思うのはそういうことだ。言葉はわたしの中で跳ねまわり、わたしの体のあらゆる穴からほとばしり出て、空間をおおいつくそうとしている。言葉による征服、言葉や、形容詞という蟻のあらゆる小さな咬み傷。話すことを学びつくしたとき、残るものはなにか。沈黙する術(すべ)を学ぶことだ。
★ インディオたちは沈黙につきまとわれている。いつの日か、たぶん沈黙は、わたしたちのところまでやって来るだろう。たぶん沈黙は、わたしたちをおおい、わたしたちの肉体の内部に入り込むだろう。沈黙がやって来て、無数の電球や、ヘッドライトやウィンカーや、照明に輝く陳列窓を壊すだろう。もし沈黙がやって来れば、それはわたしたちの言葉の多くを殺し、それらの言葉を支えているコンクリートやガラスから言葉をひき離して、絶滅させてしまうだろう。沈黙は、わたしたちの書物の多くを、意識が発信するものを混乱させるのに役立つだけの書物を破壊するだろう。沈黙は、囚われの身となっていた多数の言葉と影像を解放するだろう。たぶん沈黙は、これらすべてのことをわたしたちと一緒に行なうだろう。
<ル・クレジオ『悪魔祓い』>