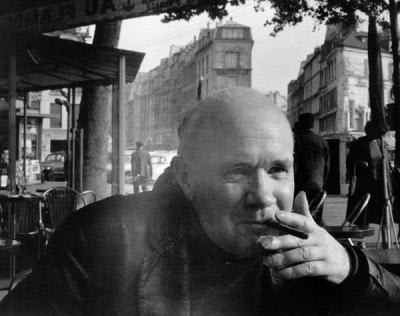★ アルジェリア戦争の前は、フランスにいるアラブ人は美しくなかった。物腰は鈍重でもたもたしていた。面構えは歪んでいた。それがほとんど突然、勝利が彼らを美しくした。だがすでに、勝利が明らかになりそのまばゆさに何も見えなくなる少し前、アウレス及びアルジェリア全土で50万を超えるフランス兵がくたばってめろめろになっていた頃、ある奇妙な現象が、アラブ人労働者の顔に体に、目につくように、作用するようになっていた。いまだ脆弱だが、彼らの皮膚から私たちの眼から、ついに鱗が落ちる時には目も眩むばかりになるであろう美の、接近のような、予感のようなものが。この明白な事実を受け入れないわけにはいかなかった。彼らが政治的解放をかちとったのは、本来そのように見られるべきだったそのままの姿で、とても美しく現われ出んがためだったのだ。同様に、難民キャンプを逃れ、キャンプのモラルと秩序、つまり生き抜く必要が課すモラルを逃れ、と同時に恥辱をも逃れてきたフェダイーンはとても美しかった。この美は新しい、生まれ変わった、生まれたままのあどけない美だったので、みずみずしく、生気にあふれるあまり、恥辱から身をもぎ離しつつある世界中のあらゆる美と響き合うことになった事情までも、たちどころに露わにしてしまった。
★ 夜のピガールを徘徊していた大勢のアルジェリア人の女衒も、アルジェリア革命のために自分の切り札を使っていた。そこにも美徳があった。自由を重視したか美徳――つまりは労働――を重視したかで革命を色分けしたのはハンナ・アレントだったと思う。おそらく認めなければならないのは、革命あるいは解放というものの――漠たる――目的は、美の発見、もしくは再発見にあるということだ。美、即ち、この語によるほか触れることも名づけることもできないもの。いや、それよりも、盛んに笑う傲岸不遜という意味を、美という語に与えよう。過去のものとなった悲惨に、この悲惨、この恥辱を招いた体制及び人間たちにまだ舐められてはいても、こんなに生意気そうに、しかもよく笑うのは、恥辱からはじけ出ることなどちょろいものだったと気づいているからに違いない。
★ だがこの頁ではとりわけ次のこと、顔から体から、それを無気力にしていた死んだ皮膚を落とさないような革命は、本当に革命なのかということが問題だったはずだ。私が言いたいのはアカデミックな美のことではなく、陰鬱さと手を切った体、顔、叫び、言葉の、触れることの――名づけることの――不可能な喜び、要するに、官能的で強烈なあまり、どんなエロチスムも追放しようとするような喜びのことだ。
<ジャン・ジュネ『シャティーラの四時間』(インスクリプト2010)>