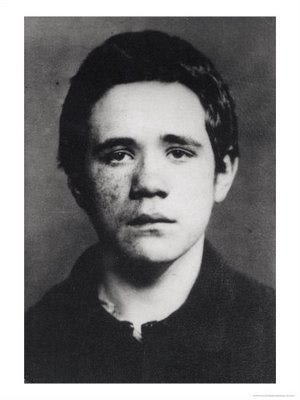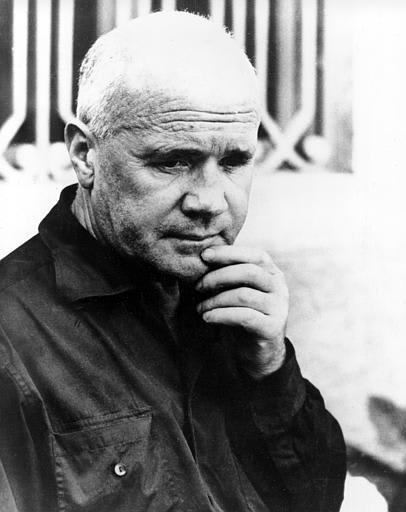★ godard_bot Jean-Luc Godard
ありきたりの言い方だが、《映画とは人生だ》と言うこともできる。でも一緒に暮らしている女たちは、この点でぼくを非難している。彼女たちはこう言うんだ。《あなたは人生を生きていない。映画なんかやめてしまいなさいよ》と。―ゴダール
8時間前
★ godard_bot Jean-Luc Godard
だから私がこの映画でしようとしたのは、映画のなかで《アルジェリア》という言葉を発するということ、しかもそれを、自分が今いる場所で、自分自身のやり方で発するということです。―ゴダール
12時間前
★ godard_bot Jean-Luc Godard
そして映画は、同時に人生でもあるんだ。だからわれわれが人生を映画に撮ると、人々はわれわれに、これはもはや映画ではない、金を払ってまでしてつづけて二度も人生を見たくないはないなどと言ってくるわけだ。―ゴダール
14時間前
★ godard_bot Jean-Luc Godard
ぼくは最近、自分の映像史についてこう考えるようになった。それは、ひとは決してまず最初に映像を見ようとはしないということ、ひとがまずはじめに見るのは二番目に来るもの、テキストの方だということだ。―ゴダール
16時間前
★ godard_bot Jean-Luc Godard
ぼくが思うのに、バルトはモードに本当に興味をもっているわけじゃない。モードそれ自体を好きなわけじゃなく、すでに死んだ言語としての、したがって解読可能な言語としてのモードが好きなだけなんだ。―ゴダール
20時間前
★ godard_bot Jean-Luc Godard
われわれは世界を、現実を、われわれ自身を分析するという刑を宣告されているわけだが、でも画家や音楽家はこうした刑を宣告されていない。―ゴダール
6月28日
★ godard_bot Jean-Luc Godard
私の敵は、映像を役立てようとしない人たちです。あるいはまた、映像を、提示するためよりはむしろ隠すために役立てようとする人たちです。―ゴダール
6月20日
★ godard_bot Jean-Luc Godard
映画をつくるというのは難しいことじゃありません。だいいち、金がかかりません。いや、金のかかる映画は金がかかり、金のかからない映画は金がかかりません。―ゴダール
6月20日
★ godard_bot Jean-Luc Godard
私が映画を好都合だと思うのは、こう言ってよければ、自分のそうした恥部を平気でさらけ出すことができるからです。しかも、それを見事にやってのけることができるからです。だから映画はおもしろいのです。―ゴダール
6月19日
★ godard_bot Jean-Luc Godard
労働者がフォードの車体のボルトを締めようとするときであれ、自分が愛している女の肩を愛撫しようとするときであれ、あるいはまた、小切手を手にとろうとするときであれ、それらのアイディアはどれもみな、運動に属しているのです。―ゴダール
6月19日
★ godard_bot Jean-Luc Godard
事実、人々がそうしたものを必要とするときもあります。私もまた、すべての人と同様、アラン・レネの映画ではなく、アラン・ドロンの映画を見にゆくことを必要としています。そしてそこには、真実のなにかがあります。―ゴダール
6月19日
★ godard_bot Jean-Luc Godard
私はいつも、人々がそれぞれドキュメンタリーとフィクションと呼んでいるものを、同じひとつの運動の二つの側面と考えようとしてきました。それにまた、真の運動というのは、この二つのものが結びつけられることによってつくり出されると考えてきました。―ゴダール
6月19日
★ godard_bot Jean-Luc Godard
ヒッチコックは女優を、植物を撮影するように撮影した。もっとも、薔薇とチューリップの間に探偵もののシナリオを配置してはいた。―ゴダール
6月19日
★ godard_bot Jean-Luc Godard
ヴァディムが美人をつかって映画を撮るときは、観客はしばしば欲求不満になる。というのも、ヴァディムがその女と寝ていることがわかるからだ。でもヒッチコックに関しては、彼はグレース・ケリーをものにしたりはしていないと確信することができるわけだ。―ゴダール
6月18日
★ godard_bot Jean-Luc Godard
エイゼンシュテインは、編集というものを発見したつもりでいたのですが、実際はアングルというものを発見したのです…カメラをどこに置くべきかを知ったのです。―ゴダール
6月18日
★ godard_bot Jean-Luc Godard
今つくられるべき真におもしろい映画は、『極北の怪異』と『恋人のいる時間』をまぜあわせたような映画でしょう。つまり、ある恋する女の仕種とあるエスキモーの仕種はどの点で互いに似ているのかということを示そうとするような映画でしょう。―ゴダール
6月18日
★ godard_bot Jean-Luc Godard
ヌーヴェル・ヴァーグがある時期のフランス映画を突き破ることができたのは、ただ単に、われわれ三、四人の者が互いに映画について語りあっていたからです。―ゴダール
6月17日
★ godard_bot Jean-Luc Godard
そして、映画づくりの外でではなく、映画をつくりながら考えようとしました。なぜなら、そうしようとはしないで紙に書いたりすると、それはむしろ小説になってしまうからです。そしてその小説が、あとで映画としてコピーされるわけです。―ゴダール
6月17日
★ godard_bot Jean-Luc Godard
スターというのがしばしばきわめて興味深いものであるのは、スターが、癌と同様、一種の奇形だからです。スターが誕生するということは、ある人間のきわめて単純な人格が急に増殖しはじめ、ばかでかいものになるということなのです。―ゴダール
6月17日
★ godard_bot Jean-Luc Godard
それに私は、自分の生まれを通して知っていることだけをとりあげようと心がけました。つまり、良家の息子や娘たちに、バカンスの期間中にマルクス・レーニン主義ごっこをさせようとしたわけです。―ゴダール
6月17日
★ godard_bot Jean-Luc Godard
私は映画をつくっていたときは、はじめのうちは、だれかがこの映画を見るということは考えていませんでした。それに私が思うに、映画をつくっている人たちの四分の三も、このことを考えていないはずです。―ゴダール
6月16日
★ godard_bot Jean-Luc Godard
私が思うに、映画は以前は、今よりもいくらか現実主義的なやり方でつくられていました。人物たちはコーヒーを飲んだりしながら、平気で、いきなり《神は存在する》などといったことを口ばしったものです。―ゴダール
6月16日
★ godard_bot Jean-Luc Godard
私はむしろ、ゆで卵をつくることも含め、すべてが政治だと考えています。なぜなら、ゆで卵をつくるためには、ある一定の金を用意しなければならないし、ある一定のやり方を学ばなければならないからです。―ゴダール
6月16日
★ godard_bot Jean-Luc Godard
ところが映画批評というのは、言葉について語る言葉なのです。しかも厄介なことに、その言葉は映像について語ろうとします。映像は言葉で語られるようにはできていないのです。―ゴダール
6月16日