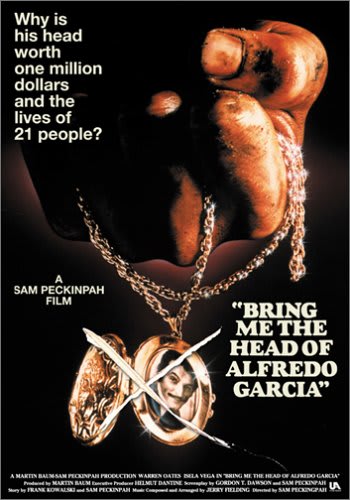★ この日、日掛けの集金をやすませてもらった田中屋の正太は、表町組の店を見まわるうちに、団子屋の背高から美登利にその日が訪れたことを耳にする。団子屋の背高にはどうやら隠しおおせたものの、正太が受けた衝撃の深さは、ほとんど無意識のうちに口をついて出るそそり節の一節にまぎれようもなく露にされる。
★ 正太が口ずさむそそり節の類型化された哀調は、この「結約証書」(注;明治時代の妓楼と遊女のあいだにかわされた契約書)に凝縮されている契約の非情さとうらはらの関係にある。もちろん、正太はこの一枚の証書によって決定される美登利の過酷な運命を見とおすことができないし、それは一葉自身によっても書かれなかった余白の部分である。しかし、正太にとって大人になることは、結局は金銭がつくりだすこうした非情な関係に入りこむ以外のなにものでもなかったのだ。
★ 団子屋の背高に別れた正太は廓の角で大黒屋の番頭新造につきそわれた美登利と行きあわせる。「初々しき大嶋田」に姿をかえた美登利は、正太の眼には、「極彩色のただ京人形を見るやう」に映る。しかし、何時になく家路をいそぐ美登利の態度を、「何故今日は遊ばないのだろう」といぶかしむ正太は、美登利の変身が意味するものからとおくへだてられている。大人の世界に迎えとられてしまった美登利と、子どもの世界にとりのこされている正太との残酷な対照が一瞬のうちに照らしだされる卓抜な場面である。
★ 美登利にゆるされていた子どもの時間が閉ざされてしまったとき、大音寺前の子どもたちの時間も終わりを告げる。(略)大音寺前を賑わわせていた子どもの世界を跡かたもなく崩してしまった見えない力の正体が、「近代」そのものであったとすれば、それは『たけくらべ』に導かれて子どもの時間へと遡行する旅を終えたばかりの私たち自身が引きうけなければならない原罪なのである。
<前田愛“子どもたちの時間”―『都市空間のなかの文学』>