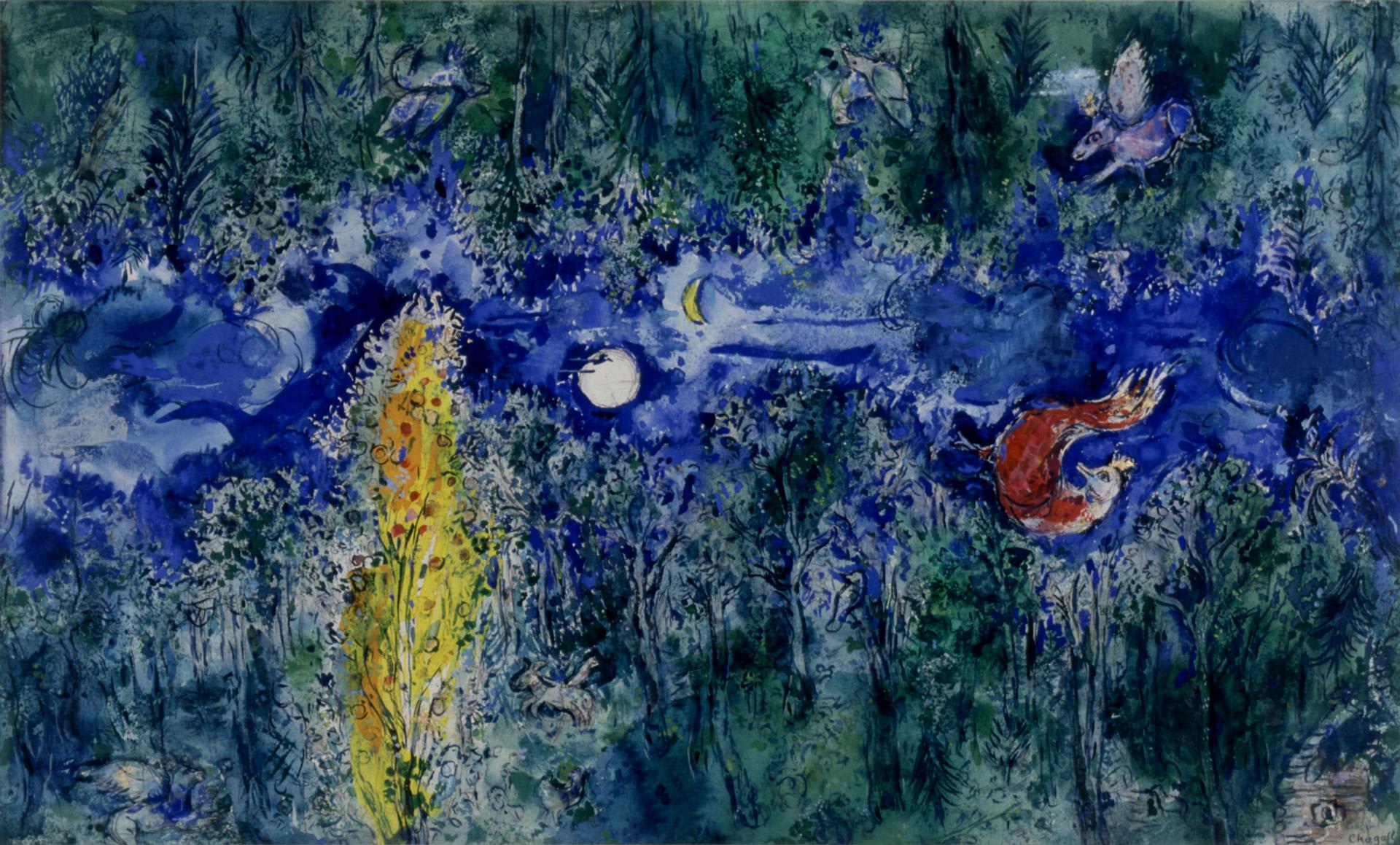
★ 女は庭仕事の手をとめ、立ち上がって遠くを見た。天気が変わる。<M.オンダーチェ:『イギリス人の患者』>
★ 日が長くなり、光が多くなって、太陽がまるで地平線を完全に一周しようとするかのように、だんだん西に、いくつもの丘の向こうに沈んでいくとき、あたしの胸はじんとする。<ル・クレジオ:“春”>
★ 雨がつづいた。それは烈しい雨、ひっきりなしの雨、なまあたたかい湯気の立つ雨だった。<レイ・ブラッドベリ:“長雨”>
★ ぼくらはゆっくりと、恐竜たちの間を出たり入ったりしつづけた。足と足の間を、腹の下を、くぐり抜けた。ブロントザウルスのまわりを一周した。ティラノザウルスの歯を見上げた。恐竜たちはみな、目のかわりに青い小さなライトをつけていた。
そこには誰もいなかった。ただぼくと、母と、恐竜たちだけがいた。<サム・シェパード:『モーテル・クロニクルズ』>
★ 喜びとともに息を凝らした。やはり彼だ。短いようで、長い時間だった。人けの絶えようとする、周囲の目からも奇妙なほど隔絶されている庭の中央で、指先にしばし、大きな複眼と透き徹った四枚の翅を載せていた。<平出隆:『猫の客』>
★ だまされやすい人たちは全員サンタクロースを信じていた。しかしサンタクロースはほんとうはガスの集金人なのであった。<ギュンター・グラス:『ブリキの太鼓』>
★ ユダヤ人は古代の神殿の祭壇で動物を犠牲に捧げ、キリストは十字架に死に、城壁上の流血はその後もたえ間なくつづいた。エルサレムは世界のいかなる都市とも似ず、流血の呪いの中を生きてきたのである。それでも古代ヘブル語のエルシャライムは、「平和の都」を意味するのだが。またその最初の住民はオリーヴ山に斜面に住みつき、爾来オリーヴの小枝は和合の世界的象徴となった。歴代の預言者たちは人間のための神の平和を、ここでいくどとなく宣言し、この地を都と定めたユダヤの王ダヴィデはエルサレムを敬って祈願した。「エルサレムの平和のために祈れ」。<D.ラピエール&L.コリンズ:『おおエルサレム!』>
★ 愛と死。この二つの言葉はそのどちらかが書きつけられるとたちまちつながってしまう。シャティーラへ行って、私ははじめて、愛の猥褻と死の猥褻を思い知った。愛する体も死んだ体ももはや何も隠そうとしない。さまざまな体位、身のよじれ、仕草、合図、沈黙までがいずれの世界のものでもある。<ジャン・ジュネ:“シャティーラの四時間”>
★ 平野には豊に作物が実っていた。果樹園がたくさんあり、平野の向こうの山々は褐色で裸だった。山では戦闘が行われていた。夜になると砲火の閃くのが見えた。暗闇のなかで、それは夏の稲妻のようだった。けれども夜は涼しく、嵐がくる気配はなかった。<ヘミングウェイ:『武器よさらば』>
★ 希望なきひとびとのためにのみ、希望はぼくらにあたえられている。<ベンヤミン:“ゲーテの『親和力』”>
★ 午前一時。皆、寝静まりました。カフェー帰りの客でも乗せているのでしょうか、たまさか窓の外から、シクロのペダルをこぐ音が、遠慮がちにカシャリカシャリと聞こえてくるほかは、このホテル・トンニャット全体が、まるで深海の底に沈んだみたいに、しじまと湿気とに支配されています。<辺見庸:『ハノイ挽歌』>
★ 二日前に雪が降り、京都御所では清涼殿や常御所の北側の屋根に白く積もって残るのを見かけた。大きな建物だから寒かろうと覚悟して行ったが、冬暖かい青空で、光に恵まれた昼となった。<大仏次郎:『天皇の世紀』>
★ どんより鉛色に曇った空の下、山あいから列車が抜け出てくる。女の声「あんなに表日本は晴れていたのに、山を抜けたら一ぺんに鉛色の空になっている」<早坂暁:『夢千代日記』>
★ 多摩川河畔(昼)リモコン飛行機がとんでいる。スーパー“昭和48年8月”<山田太一:『岸辺のアルバム』>
★ 万治三年七月十八日。幕府の老中から通知があって、伊達陸奥守の一族伊達兵部少輔、同じく宿老の大条兵庫、茂庭周防、片倉小十郎、原田甲斐。そして、伊達家の親族に当たる立花飛騨守ら六人が、老中酒井雅楽頭の邸へ出頭した。<山本周五郎:『樅ノ木は残った』>
★ 虚構の経済は崩壊したといわれるけれども、虚構の言説は未だ崩壊していない。だからこの種子は逆風の中に播かれる。アクチュアルなもの、リアルなもの、実質的なものがまっすぐに語り交わされる時代を準備する世代たちの内に、青青とした思考の芽を点火することだけを願って、わたしは分類の仕様のない書物を世界の内に放ちたい。<真木悠介:『自我の起源』あとがき>
★ 日本を統ぐ(すめらぐ)には空にある日ひとつあればよいが、この闇の国に統ぐ物は何もない。事物が氾濫する。人は事物と等価である。そして魂を持つ。何人もの人に会い、私は物である人間がなぜ魂を持ってしまうのか、そのことが不思議に思えたのだった。魂とは人のかかる病であるが、人は天地創造の昔からこの病にかかりつづけている。<中上健次:『紀州』 終章“闇の国家”>
★ 現象学はバルザックの作品、プルーストの作品、ヴァレリーの作品、あるいはセザンヌの作品とおなじように、不断の辛苦である――おなじ種類の注意と驚異とをもって、おなじような意識の厳密さをもって、世界や歴史の意味をその生まれ出づる状態において捉えようとするおなじ意志によって。こうした関係のもとで、現象学は現代思想の努力と合流するのである。<メルロ=ポンティ『知覚の現象学』序文>
★ そこでは、汗の一滴一滴、筋肉の屈伸の一つ一つ、喘ぐ息の一息一息が、或る歴史の象徴となる。私の肉体が、その歴史に固有の運動を再生すれば、私の思考はその歴史の意味を捉えるのである。私は、より密度の高い理解に浸されているのを感じる。その理解の内奥で、歴史の様々な時代と、世界の様々な場所が互いに呼び交わし、ようやく解かり合えるようになった言葉を語るのである。<クロード・レヴィ=ストロース:『悲しき熱帯』>
★ 哲学がもし、考えること自体について考える批判的な作業でないとしたら、今日、哲学とはいったいなんだろうか。また、すでに知っていることを正当化するというのではなく、別のしかたで考えることが、どのようにして、また、どこまで可能なのかを知ろうとするという企てに哲学が存するのでないとしたら、今日、哲学とはいったいなんだろうか。<ミシェル・フーコー:『快楽の活用』>
★人間が意志をはたらかすことができず、しかしこの世の中のあらゆる苦しみをこうむらなければならないと仮定したとき、彼を幸福にしうるものは何か。
この世の中の苦しみを避けることができないのだから、どうしてそもそも人間は幸福でありえようか。
ただ、認識の生を生きることによって。<ウィトゲンシュタイン:“草稿1914-1916”>
★ そのとき、匂いが蘇った。新しい紙と印刷インクの匂いだ。それが彼を取り巻いていた。三十年暮らした中国の村では、活字はどれも黄ばんだ紙に印刷されていた。
もう一度、思い切りその匂いをかいだ。そのとたん、胸がつかえた。胃が暴れ、何かが喉にこみ上げてきた。歯を食いしばってそれを止めると、涙がわっと溢れでた。<矢作俊彦:『ららら科学の子』>
★ 「きみはだれだ? きみはどこへ行くのか? きみはなにを探しているのか? きみはだれを愛しているのか? きみはなにが欲しいのか? きみはなにを待っているのか? きみはなにを感じているのか? きみにわたしが見えるか? きみにわたしの声が聞こえるか?」<ミシェル・ビュトール『心変わり』>
★ 昔し美しい女を知っていた。この女が机に凭れて何か考えている所を、後から、そっと行って、紫の帯上げの房になった先を、長く垂らして、頸筋の細いあたりを、上から撫で廻したら、女はものう気に後ろを向いた。その時女の眉は心持八の字に寄っていた。それで目尻と口元には笑が萌していた。同時に恰好の好い頸を肩まですくめていた。文鳥が自分を見た時、自分は不図この女の事を思い出した。この女は今嫁に行った。自分が紫の帯上げでいたずらをしたのは縁談の極まった(きまった)二三日後である。<夏目漱石:“文鳥”>
★ だが、あらゆる部族の名前がある。砂一色の砂漠を歩き、そこに光と信仰と色を見た信心深い遊牧民がいる。拾われた石や金属や骨片が拾い主に愛され、祈りの中で永遠となるように、女はいまこの国の大いなる栄光に溶け込み、その一部となる。私たちは、恋人と部族の豊かさを内に含んで死ぬ。味わいを口に残して死ぬ。あの人の肉体は、私が飛び込んで泳いだ知恵の流れる川。この人の人格は、私がよじ登った木。あの恐怖は、私が隠れ潜んだ洞窟。私たちはそれを内にともなって死ぬ。私が死ぬときも、この体にすべての痕跡があってほしい。それは自然が描く地図。そういう地図作りがある、と私は信じる。中に自分のラベルを貼り込んだ地図など、金持ちが自分の名前を刻み込んだビルと変わらない。私たちは共有の歴史であり、共有の本だ。どの個人にも所有されない。好みや経験は、一夫一婦にしばられない。人工の地図のない世界を、私は歩きたかった。<M.オンダーチェ:『イギリス人の患者』>
★ 空から光が一面の透明な滝となって、沈黙と不動の竜巻となって落ちてきた。空気は青く、手につかめた。青。空は光の輝きのあの持続的な脈動だった。夜はすべてを、見はるかすかぎり河の両岸の野原のすべてを照らしていた。毎晩毎晩が独自で、それぞれがみずからの持続の時と名づけうるものであった。夜の音は野犬の音だった。野犬は神秘に向かって吠えていた。村から村へとたがいに吠え交わし、ついには夜の空間と時間を完全に喰らいつくすのだった。<マルグリット・デュラス:『愛人(ラマン)』>
★ ぼくの死はぼくを裸にしてしまい、ぼくはぼろ切れ一つさえも身にまとっていることはできまい。ぼくがやって来たように手ぶらで、ぼくは帰ってゆくのだ、手ぶらで。<ル・クレジオ :“沈黙”―『物質的恍惚』>
★ むかしのことを思い出すと、心臓がはやく打ちはじめる。<ジョン・レノン:“ジェラス・ガイ”>
★ それでもジョバンニはどこでも降りない。銀河鉄道のそれぞれの乗客たちが、それぞれの「ほんとうの天上」の存在するところで降りてしまうのに、いちばんおしまいまで旅をつづけるジョバンニは、地上におりてくる。
ひとつの宗教を信じることは、いつか旅のどこかに、自分を迎え入れてくれる降車駅をあらかじめ予約しておくことだ。ジョバンニの切符には行く先がない。ただ「どこまでも行ける切符」だ。<真木悠介『自我の起源 愛とエゴイズムの動物社会学』“補論2”>
★ だが飛行機がふたたび雲から出て揺れもなくなると、2万7千フィートのここで鳴っているのはたくさんのベルだ。たしかにベルだ。ベン・ハンスコムが眠るとそれはあのベルになる。そして眠りにおちると、過去と現在を隔てていた壁がすっかり消えて、彼は深い井戸に落ちていくように年月を逆に転がっていく―ウェルズの『時の旅人』かもしれない、片手に折れた鉄棒を持ち、モーロックの地の底へどんどん落ちていく、そして暗闇のトンネルでは、タイム・マシンがかたかたと音をたてている。1981、1977、1969。そしてとつぜん彼はここに、1958年の6月にいる。輝く夏の光があたり一面にあふれ、ベン・ハンスコムの閉じているまぶたの下の瞳孔は、夢を見る脳髄の命令で収縮する。その目は、イリノイ西部の上空に広がる闇ではなく、27年前のメイン州デリーの、6月のある日の明るい陽の光を見ている。
たくさんのベルの音。
あのベルの音。
学校。
学校が。
学校が
終わった!
<スティーヴン・キング『 IT 第2部 』>
★ 思想史が人間の思想および感情――理性的な議論および激情(パッション)の爆発――をともに取扱うものであることは、あらためていうまでもない。書くこと、話すこと、現実の行為、伝統、などにあらわれる人間の表現の全範囲が、思想史の領域内にある。まったくのところ、野獣の叫び声より判然たる人間の言表なら、ある意味では、そのすべてが思想史の主題になると考えられる。<スチュアート・ヒューズ『意識と社会』>
★ 知識人とは亡命者にして周辺的存在であり、またアマチュアであり、さらに権力に対して真実を語ろうとする言葉の使い手である。<エドワード・W・サイード『知識人とは何か』>
★ 魔女1 この次3人、いつまた会おうか?かみなり、稲妻、雨の中でか?<シェクスピア:『マクベス』>




















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます