保坂和志の『朝露通信』の面白さを、あまり小説を読まない人に薦めるにはどう説明すればよいのだろう。小説内で主人公が自虐的に「あんな、だらだらした文章で何も起きない話ばっかり書く人が……」と語っているのは芥川賞以来の世間的な評価なのかもしれないが、じゃあ「テキストを楽しむ小説もあるんだよ」というとそれは正確な説明ではない気もする。
実際に、何も起きないことはなく、文ごとに何かが起きている。他の小説以上に凹凸が激しいからじつは読むのに疲れる。なにも起きないから疲れるのではなく、起きすぎているから疲れるのだ。その間に、決定的なギミックを仕掛けてくるから余計にしんどい。だから、お金の勘定に心を亡くしていたり、心に世俗の錨のようなものを抱えていると、最初のページを開くが億劫になる……。って、そんな小説、読むの辛いだけじゃん。いや、それでもその第一歩を踏み越えれば、確実にやめられなくなる。密度?確かにそうだけれど、「密度が面白い」って、ますますハードルが高くなるよなあ。
じつは、「…何も起きない話ばっかり書く人が……」には続きがあって、それは「そんなに落ち着きがないなんて、意外だ。」というものだ。そしてこう続く。「意外ではない、だらだらしていると言われる文章が退屈しないとしたら細かく忙しなく動いているからだ」。どう?突然くるでしょ。ハッとするでしょ。こういう挟み方も保坂和志の小説の魅力のひとつだけれど、書かれていることにも魅力を説明するための糸口がある。
まず「退屈」の問題。もちろん保坂の小説だって長いものだと読み淀むことはある。しかし、それは「退屈だから」と言う理由ではなく、「退屈しないことに疲れた」からだ。疲れないがぎりいつまでも読み続けたくなる。そこに、ストーリーが面白くない「退屈」とか、ウソっぽいといった「退屈」は存在しない。それは、書かれているように「細かく忙しなく動いている」ことに起因するのだろう。「細かく忙しなく」はともかくとして、「動いている」。話題があちこち連鎖していくといったストレートな動き方はもとより、なんか「動いている」。もしかしたら「止まっていない」といった方が正しいのかもしれない。
大きなテーマをもつ小説であったり、事件を解決しなければならないような小説は、じつは解説のために「止まらざるをえない」ことがある。場合によってはその瞬間に「退屈」が到来する。保坂の小説は、答えのないテーマで書かれているから終わりようもなく(正確に言うと書かれているのは「問い」だから)解説のために立ち止まることはないし、毎日起きている「事件」はあくまで「事件」であって、「謎」ではないから解題の必要もない。日常が止まることなく動いている。そのなかで、何かが深まっていく。経験が深まっていくし記憶や追想が深まっていく。言葉が深まっていく。生活とはそういうものだ。
そんなことが書かれた小説なんだけれど、いやそんなことは書かれていないのかもしれないけれど、「僕は泣きそうな大声をワーワー上げて、一塁に座り込んだ。「こうだ!こうしろ!」石井君は頭の上でグローブを構える格好をした、僕は言われるまま頭の上でグローブを開いた、走ってくる石井君は間に合わず、そこで下からポォンと投げた、球は見事に僕のグローブに入った。」といったようなことは書かれている小説です。ちなみに、読点の打ち方は写し間違いではありません。どう?保坂和志。
実際に、何も起きないことはなく、文ごとに何かが起きている。他の小説以上に凹凸が激しいからじつは読むのに疲れる。なにも起きないから疲れるのではなく、起きすぎているから疲れるのだ。その間に、決定的なギミックを仕掛けてくるから余計にしんどい。だから、お金の勘定に心を亡くしていたり、心に世俗の錨のようなものを抱えていると、最初のページを開くが億劫になる……。って、そんな小説、読むの辛いだけじゃん。いや、それでもその第一歩を踏み越えれば、確実にやめられなくなる。密度?確かにそうだけれど、「密度が面白い」って、ますますハードルが高くなるよなあ。
じつは、「…何も起きない話ばっかり書く人が……」には続きがあって、それは「そんなに落ち着きがないなんて、意外だ。」というものだ。そしてこう続く。「意外ではない、だらだらしていると言われる文章が退屈しないとしたら細かく忙しなく動いているからだ」。どう?突然くるでしょ。ハッとするでしょ。こういう挟み方も保坂和志の小説の魅力のひとつだけれど、書かれていることにも魅力を説明するための糸口がある。
まず「退屈」の問題。もちろん保坂の小説だって長いものだと読み淀むことはある。しかし、それは「退屈だから」と言う理由ではなく、「退屈しないことに疲れた」からだ。疲れないがぎりいつまでも読み続けたくなる。そこに、ストーリーが面白くない「退屈」とか、ウソっぽいといった「退屈」は存在しない。それは、書かれているように「細かく忙しなく動いている」ことに起因するのだろう。「細かく忙しなく」はともかくとして、「動いている」。話題があちこち連鎖していくといったストレートな動き方はもとより、なんか「動いている」。もしかしたら「止まっていない」といった方が正しいのかもしれない。
大きなテーマをもつ小説であったり、事件を解決しなければならないような小説は、じつは解説のために「止まらざるをえない」ことがある。場合によってはその瞬間に「退屈」が到来する。保坂の小説は、答えのないテーマで書かれているから終わりようもなく(正確に言うと書かれているのは「問い」だから)解説のために立ち止まることはないし、毎日起きている「事件」はあくまで「事件」であって、「謎」ではないから解題の必要もない。日常が止まることなく動いている。そのなかで、何かが深まっていく。経験が深まっていくし記憶や追想が深まっていく。言葉が深まっていく。生活とはそういうものだ。
そんなことが書かれた小説なんだけれど、いやそんなことは書かれていないのかもしれないけれど、「僕は泣きそうな大声をワーワー上げて、一塁に座り込んだ。「こうだ!こうしろ!」石井君は頭の上でグローブを構える格好をした、僕は言われるまま頭の上でグローブを開いた、走ってくる石井君は間に合わず、そこで下からポォンと投げた、球は見事に僕のグローブに入った。」といったようなことは書かれている小説です。ちなみに、読点の打ち方は写し間違いではありません。どう?保坂和志。












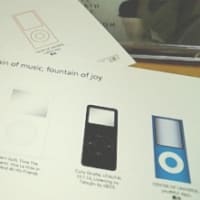
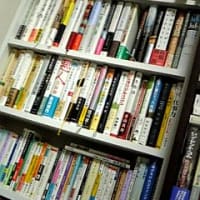
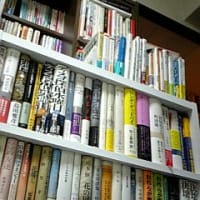

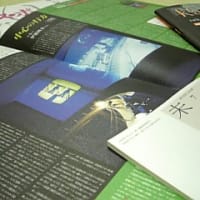

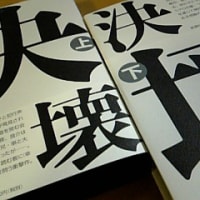

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます