すでにいろいろな形で評価を下されている、SANKEI EXPRESSについて、手に入りにくくなる前に。
 □GOOD
□GOOD
●旧態にある新聞社においてこの試みじたいは面白い。企画を実行までもっていけるところは産経新聞社らしい。
●コンセプトが明らかで一貫している。もはや若い世代では、ネットがあるから新聞は購読していないです、という人も増えているが、そういった人たちに「紙としての新聞」に目を向けてもらう、という考え方に対してにさまざまな具体策を集中させた。掻い摘んだ記事、手に馴染むサイズ、駅売り70円という価格設定、記事のエンタテイメント性など。
ただし、新聞の場合、こういったターゲット設定が奏功するかはどうかはわからない。どちらかというと、思いっきり失敗してることのほうが多い。たとえば「TOKYO Lady Kong(東京レディコング)」。最近もほかになんかあったような気がする。無くなるんじゃないか、と急いで買いに行ったあれはなんだったけ。ああ、そうだ朝日だ。『SEVEN』だ。どっかに残っていないかなあ。
 ●手順を踏んだマーケティング。とりあえず、首都圏・京都市の宅配でスタートしたのでしたっけ。一ヶ月たったいまでは、大阪では駅売りで買えます。販売地域・チャネルについてはさまざまなオプションはあっただろうけれど、テスト的にスタートしたのは正解。
●手順を踏んだマーケティング。とりあえず、首都圏・京都市の宅配でスタートしたのでしたっけ。一ヶ月たったいまでは、大阪では駅売りで買えます。販売地域・チャネルについてはさまざまなオプションはあっただろうけれど、テスト的にスタートしたのは正解。
●厚い。32ページ。これは新聞好きにとってはたまらない魅力。紙面提携もしている「USA TODAY」なんて、最近はわからないけれど、昔は別冊につぐ別冊で凄まじい厚みになっていたものだ。
●読むところはある。この手のもの創刊時には、結局「読むところないねえ」というのが致命的な課題になることが多いが、さすがに日刊紙だけあって読むところはある。もし、時間はたっぷりあるのにポケットには小銭しかない、というときには、ぜひ。
●佐藤優のコラムなんてのも載っています。読者からのコメントに対する回答、個人に対する意見など、筆致がブログ風なのが面白い。というか、ブログの転載?……うわあ「ビジネスアイ」からの転載だ。
●ワン・ソース・マルチユース。2~3日前に、たとえばZAKZAKなどでアップされていたコラム記事がそのまま転載されている。正しいかどうかは別として、賢い使い方ではある。
●美しい新聞。同紙の広告戦略のとおり、手が汚れない、というのは結構大きなベネフィットではある。新聞ではないけど「ビッグコミックスペリオール」なんてのは酷くって、読んだあとに真っ黒になった手に愕然とすることも多いので。
●ネットとの連動。編集長と記者が「いまのところ」しっかりとブログを書いている。真偽のほどはわからないが、コメントでの受け答えも行っている。
●DTPでの効率化を目指しているところが見て取れる。これは、読者サイドのGOODではないが、「フジサンケイビジネスアイ」同様、制作システムへの「トライアルじたい」は好ましい。ところで、「SANKEI EXPRESS」もJANコードをとっているのだろうか。
□NO GOOD
●まず、ターゲット設定。これは選択の問題なので正しい答えはないわけだが、当面、企業としての新聞社は新聞の危機より、トータルで新聞社の危機を考えたほうがいい。確かに「若者の活字離れ」はいつの時代においても手軽に合意が得られやすい問題ではあるが、課題抽出が手軽なものほど、解決の答えが導き出しにくいものはない。ここは若年層というより、むしろ、数年後には駅売りの「サンスポ」「夕刊フジ」の部数が激減することを考えれば壮年対策も必要という選択しもあったかもしれない。壮年の埋め合わせを若年で、と考えたのかもしれないけれど、その場合、宅配スタートはいちおう間違ってはいる。リタイア向けに、サンスポもフジもぶっこんだぶ厚い宅配日刊紙なんて発想もあるかもしれないけれど、こればかりはやはりギャンブルするしかない選択だ。もっとも、チャネルについて、す早いコレクトは行っているようなので、これはなかなか興味深い。
●ヨコ組み。ぼくは何が何でもタテ組みというほどの信者ではないが、このヨコ組みはまったくいただけない。新聞というものは、そもそも斜め読みが基本ということを考えたとき、やはりヨコ組みでは、飛ばし読みができないということを露呈してしまった。
同じヨコ組みであっても、もう少し読みにくさをカバーできるような、レイアウトやタイポグラフィを熟慮する必要はあっただろう。
●美しくない。美しい、といっておいてなんだが、紙面のデザインについてはまったく美しくない。スカスカ感が否めないのは、きっと「白場」の微妙なバランスだろう。罫線とかちょっとしたデザインエレメントが下手なパワーポイントみたいだ。「フジサンケイビジネスアイ」のときもそうだったが簡易DTPの限界?いや、じつはこれもむしろヨコ組みレイアウトの限界かもしれない。
●アートと称するが、アートでもなんでもないエンタテイメントページが半分以上を占める。アートならいいんだけれどね。もちろん黒谷友香の大きな写真だって間違ってはいないけれど、それはWEBでいいです。
●ワン・ソースをマルチユースしすぎ。フジサンケイグループの文字媒体のダイジェスト版といっても言いすぎではないような気もする。もっとも、「持ち歩くためにWEBをプリントアウトしたもの、それがSANKEI EXPRESSです」というなら話は別だが。
●もし、これを新聞というなら、さすがフジサンケイグループだといわざるをえない。記事の「選択と集中」というのは聞こえがいいが、そこには確実に確信犯的なもの、ないしは恣意が介在するわけで、社説により意思を表明するならともかく、記事の選別による意思の分別はたとえ悪意とか計算がないとしてもあまり正しくはない。また、現実的にはいわゆる五大紙については新聞というのはなにも情報を仕入れるだけのものではなく、複眼的な視点を知る場であることも重要になっていて、ここを端折るということはやはり新聞としての機能を放擲しているといわざるをえない。もっとも、プロモーション・キャッチフレーズを除いては、「SANKEI EXPRESS」のことを「新聞」とは言っていないわけだけれど。
 □GOOD
□GOOD●旧態にある新聞社においてこの試みじたいは面白い。企画を実行までもっていけるところは産経新聞社らしい。
●コンセプトが明らかで一貫している。もはや若い世代では、ネットがあるから新聞は購読していないです、という人も増えているが、そういった人たちに「紙としての新聞」に目を向けてもらう、という考え方に対してにさまざまな具体策を集中させた。掻い摘んだ記事、手に馴染むサイズ、駅売り70円という価格設定、記事のエンタテイメント性など。
ただし、新聞の場合、こういったターゲット設定が奏功するかはどうかはわからない。どちらかというと、思いっきり失敗してることのほうが多い。たとえば「TOKYO Lady Kong(東京レディコング)」。最近もほかになんかあったような気がする。無くなるんじゃないか、と急いで買いに行ったあれはなんだったけ。ああ、そうだ朝日だ。『SEVEN』だ。どっかに残っていないかなあ。
 ●手順を踏んだマーケティング。とりあえず、首都圏・京都市の宅配でスタートしたのでしたっけ。一ヶ月たったいまでは、大阪では駅売りで買えます。販売地域・チャネルについてはさまざまなオプションはあっただろうけれど、テスト的にスタートしたのは正解。
●手順を踏んだマーケティング。とりあえず、首都圏・京都市の宅配でスタートしたのでしたっけ。一ヶ月たったいまでは、大阪では駅売りで買えます。販売地域・チャネルについてはさまざまなオプションはあっただろうけれど、テスト的にスタートしたのは正解。●厚い。32ページ。これは新聞好きにとってはたまらない魅力。紙面提携もしている「USA TODAY」なんて、最近はわからないけれど、昔は別冊につぐ別冊で凄まじい厚みになっていたものだ。
●読むところはある。この手のもの創刊時には、結局「読むところないねえ」というのが致命的な課題になることが多いが、さすがに日刊紙だけあって読むところはある。もし、時間はたっぷりあるのにポケットには小銭しかない、というときには、ぜひ。
●佐藤優のコラムなんてのも載っています。読者からのコメントに対する回答、個人に対する意見など、筆致がブログ風なのが面白い。というか、ブログの転載?……うわあ「ビジネスアイ」からの転載だ。
●ワン・ソース・マルチユース。2~3日前に、たとえばZAKZAKなどでアップされていたコラム記事がそのまま転載されている。正しいかどうかは別として、賢い使い方ではある。
●美しい新聞。同紙の広告戦略のとおり、手が汚れない、というのは結構大きなベネフィットではある。新聞ではないけど「ビッグコミックスペリオール」なんてのは酷くって、読んだあとに真っ黒になった手に愕然とすることも多いので。
●ネットとの連動。編集長と記者が「いまのところ」しっかりとブログを書いている。真偽のほどはわからないが、コメントでの受け答えも行っている。
●DTPでの効率化を目指しているところが見て取れる。これは、読者サイドのGOODではないが、「フジサンケイビジネスアイ」同様、制作システムへの「トライアルじたい」は好ましい。ところで、「SANKEI EXPRESS」もJANコードをとっているのだろうか。
□NO GOOD
●まず、ターゲット設定。これは選択の問題なので正しい答えはないわけだが、当面、企業としての新聞社は新聞の危機より、トータルで新聞社の危機を考えたほうがいい。確かに「若者の活字離れ」はいつの時代においても手軽に合意が得られやすい問題ではあるが、課題抽出が手軽なものほど、解決の答えが導き出しにくいものはない。ここは若年層というより、むしろ、数年後には駅売りの「サンスポ」「夕刊フジ」の部数が激減することを考えれば壮年対策も必要という選択しもあったかもしれない。壮年の埋め合わせを若年で、と考えたのかもしれないけれど、その場合、宅配スタートはいちおう間違ってはいる。リタイア向けに、サンスポもフジもぶっこんだぶ厚い宅配日刊紙なんて発想もあるかもしれないけれど、こればかりはやはりギャンブルするしかない選択だ。もっとも、チャネルについて、す早いコレクトは行っているようなので、これはなかなか興味深い。
●ヨコ組み。ぼくは何が何でもタテ組みというほどの信者ではないが、このヨコ組みはまったくいただけない。新聞というものは、そもそも斜め読みが基本ということを考えたとき、やはりヨコ組みでは、飛ばし読みができないということを露呈してしまった。
同じヨコ組みであっても、もう少し読みにくさをカバーできるような、レイアウトやタイポグラフィを熟慮する必要はあっただろう。
●美しくない。美しい、といっておいてなんだが、紙面のデザインについてはまったく美しくない。スカスカ感が否めないのは、きっと「白場」の微妙なバランスだろう。罫線とかちょっとしたデザインエレメントが下手なパワーポイントみたいだ。「フジサンケイビジネスアイ」のときもそうだったが簡易DTPの限界?いや、じつはこれもむしろヨコ組みレイアウトの限界かもしれない。
●アートと称するが、アートでもなんでもないエンタテイメントページが半分以上を占める。アートならいいんだけれどね。もちろん黒谷友香の大きな写真だって間違ってはいないけれど、それはWEBでいいです。
●ワン・ソースをマルチユースしすぎ。フジサンケイグループの文字媒体のダイジェスト版といっても言いすぎではないような気もする。もっとも、「持ち歩くためにWEBをプリントアウトしたもの、それがSANKEI EXPRESSです」というなら話は別だが。
●もし、これを新聞というなら、さすがフジサンケイグループだといわざるをえない。記事の「選択と集中」というのは聞こえがいいが、そこには確実に確信犯的なもの、ないしは恣意が介在するわけで、社説により意思を表明するならともかく、記事の選別による意思の分別はたとえ悪意とか計算がないとしてもあまり正しくはない。また、現実的にはいわゆる五大紙については新聞というのはなにも情報を仕入れるだけのものではなく、複眼的な視点を知る場であることも重要になっていて、ここを端折るということはやはり新聞としての機能を放擲しているといわざるをえない。もっとも、プロモーション・キャッチフレーズを除いては、「SANKEI EXPRESS」のことを「新聞」とは言っていないわけだけれど。










 ことのことは、もはや号数としては本年最後となってしまう
ことのことは、もはや号数としては本年最後となってしまう ●佐藤友哉の『1000の小説とバックベアード』は一見すると、なにかのパロディのようにしか見えない。架空の職業、やみという敵対集団の存在、展開の主導を握ってしまう女性の唐突な登場は、まぎれもなく村上春樹だし、後半にいたって言及される、けっして表現することのできない死への諦念や『日本文学』の擬人化、太宰(だざいの変換候補の一番目が堕罪だなんて!)の重用はまさに高橋源一郎だ。さらに、本文とほとんどまったく無関係と思われる形で配置されているチャプタータイトルは、それを列挙するとわかるが、確実に「作家になりたい人のための小説入門」である(「作家志望者はまず無職になれ」「こまったら新キャラクターを登場させよ」「古典は必読だが読みすぎるな」…)。いったい本気で書いているのかちょっとしたおふざけなのか。
●佐藤友哉の『1000の小説とバックベアード』は一見すると、なにかのパロディのようにしか見えない。架空の職業、やみという敵対集団の存在、展開の主導を握ってしまう女性の唐突な登場は、まぎれもなく村上春樹だし、後半にいたって言及される、けっして表現することのできない死への諦念や『日本文学』の擬人化、太宰(だざいの変換候補の一番目が堕罪だなんて!)の重用はまさに高橋源一郎だ。さらに、本文とほとんどまったく無関係と思われる形で配置されているチャプタータイトルは、それを列挙するとわかるが、確実に「作家になりたい人のための小説入門」である(「作家志望者はまず無職になれ」「こまったら新キャラクターを登場させよ」「古典は必読だが読みすぎるな」…)。いったい本気で書いているのかちょっとしたおふざけなのか。 「弁証法」「全体図」さらには「読書」といったキーワードに展開していくに至り、あれ、結構まっとうなこといっているよなあ、といささかの驚きを覚えつつも、朝一番で、購買意欲までボーっとしていたので買うまでにはいたらなかった。そのあとも、いちおう気になってはいて、いくつかの書店で軽く物色はしていたのだけれど、この手のコンビニムックは宿命的にパッとでてパッと消えるものだという先入観もあり、しかも所詮はコンビニムックだしなあ、と思い、なかば忘れかけていたところ、まさに偶然らしい偶然で繋がったというわけだ。
「弁証法」「全体図」さらには「読書」といったキーワードに展開していくに至り、あれ、結構まっとうなこといっているよなあ、といささかの驚きを覚えつつも、朝一番で、購買意欲までボーっとしていたので買うまでにはいたらなかった。そのあとも、いちおう気になってはいて、いくつかの書店で軽く物色はしていたのだけれど、この手のコンビニムックは宿命的にパッとでてパッと消えるものだという先入観もあり、しかも所詮はコンビニムックだしなあ、と思い、なかば忘れかけていたところ、まさに偶然らしい偶然で繋がったというわけだ。 大きなつくりの本であっても、そこ語られている、「私心を捨てる」ことについての考え方は、私のような小さい人間が物事を判断していくときのひとつの拠り所にはなるだろう。
大きなつくりの本であっても、そこ語られている、「私心を捨てる」ことについての考え方は、私のような小さい人間が物事を判断していくときのひとつの拠り所にはなるだろう。 こういった形で仕事への立ち位置を丹念に語るものが参考になる場合もあるし、一方でその勢いだけで、おいおまえなにを挫けているのだ、と諭すようなものもある。最近では波頭亮という経営コンサルタントが著した
こういった形で仕事への立ち位置を丹念に語るものが参考になる場合もあるし、一方でその勢いだけで、おいおまえなにを挫けているのだ、と諭すようなものもある。最近では波頭亮という経営コンサルタントが著した 予想どおり、珍しく一気に読み終えることができたんだけれど、結局のところこれは
予想どおり、珍しく一気に読み終えることができたんだけれど、結局のところこれは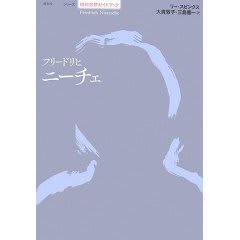 ちょうど中村書店に青土社の現代ガイドブックシリーズ
ちょうど中村書店に青土社の現代ガイドブックシリーズ :珍しく『わが悲しき娼婦たちの思い出』を短時間で完読することができたのは、マルケスの語りに加え、木村榮一の訳の負うところも大きいだろう。『わが悲しき…』は、事前の触れ込みでは、なんとなく「淫らさ」みたいなものが強調されていて、それなら少しうんざりするなあと思っていたのだが、そこはマルケス、人生という世界を肯定し、純度高くろ過した。その前段階ともいわれる『コレラ…』もまた楽しみだ。
:珍しく『わが悲しき娼婦たちの思い出』を短時間で完読することができたのは、マルケスの語りに加え、木村榮一の訳の負うところも大きいだろう。『わが悲しき…』は、事前の触れ込みでは、なんとなく「淫らさ」みたいなものが強調されていて、それなら少しうんざりするなあと思っていたのだが、そこはマルケス、人生という世界を肯定し、純度高くろ過した。その前段階ともいわれる『コレラ…』もまた楽しみだ。 :パワーズの村上評を読み逃していたので、こちらもよい形の本にしてくれた。つい最近、清水良典のたいへん興味深い『村上春樹はくせになる』を読んだあと、そのくせを思い出し『羊をめぐる…』なんかを再読したりしたのだが、村上春樹はやはり面白い。読み返すたびにここまで異なる視座が提供される長編小説はほかにはあまりない、ということを実感した。
:パワーズの村上評を読み逃していたので、こちらもよい形の本にしてくれた。つい最近、清水良典のたいへん興味深い『村上春樹はくせになる』を読んだあと、そのくせを思い出し『羊をめぐる…』なんかを再読したりしたのだが、村上春樹はやはり面白い。読み返すたびにここまで異なる視座が提供される長編小説はほかにはあまりない、ということを実感した。