


先日、友人と三鷹の国立天文台に見学に行った。売店で「組み立て式天球儀」というものを買った(国立天文台については、近々また行くつもりなので、別途書きたい)。
本体は星座を印刷した濃い青色の、北と南の半球に分かれた、たいへん複雑な形の紙で、それを折って内側からセロテープで止めて行って立体にして、最後にその二つの半球を嵌め込み式に組み合わせる。半球は天頂(北半球なら北極星のあるところ)は正五角形、その下の中緯度のところが5個の正六角形、低緯度のところは正五角形と正六角形が互い違いに5個ずつ組み合わされて、二つの半球合わせて32面になっている。
数学的でないアタマのぼくには、どうして五角形と六角形の組み合わせで模擬的にせよ球体ができるのかよくわからない。
これを読んでいてすぐに気が付いた方もいるだろうが、ぼくは組み立ててみてやっと気付いた。これはサッカーボールだ!(あのボールを最初につくった人は誰だろう。すごく頭の良い人だったんだな。)
さて、かなり苦労して出来上がったものは、つなぎ目のところに来る星、例えばわし座のアルタイル(七夕の彦星)が二重星になってしまったり、黄道がずれてしまったり、不細工なものになった(ぼくは小中と図画工作の成績が2だった)が、何はともあれ、天球ではあるので、達成感はある。
完成したものを眺めていてふと気が付いた。星座の左右が逆になっている! 例えばさそり座は実際の空では頭が右、尾が左のS字形だが、天球儀では尾が右、頭が左の逆S字になっている。左右逆に組み立ててしまったのか? と思ったが、印刷は片面にしかされていないのだから、もちろんそんなことは無い。
考えてみれば、ぼくはいま、通常は内側から見ている天球を外側から見ているのだから当たり前のことだ。満天の星を見る機会というのは、いまではごくまれに、山登りに行って深い山の中で夜を過ごす時、ぐらいしかないが、その時ぼくは天球という仮想の球の中心にいて、空を、正確には空の一部を、“見上げ”ているごくちっぽけな存在だ。天球儀を見るとき、ぼくは逆に天球の外にいて、天全体を“見下ろす”ことができる、限りなく大きな存在になっている。
天の川というものは、見上げる時なるほど川のように見えるものだが、じつは天球を二分してぐるりと取り巻いている帯なのだ。その帯はゆるやかに蛇行して、たしかに所どころ氾濫した川のように広がっている。
「取り巻いて」と今書いたのを急いで訂正しておこう。もちろん、宇宙空間で天の川は真ん中までぎっしりと星で詰まっている。いま球形のものを思いつかないが、平たいもので言えば、シベリアケーキの餡のように。そして実は、シベリアケーキのように見えるのは、カステラと餡のような別のものではなくて、ただ単に星の分布の密度が濃いか薄いかの違いなのだ。
・・・シベリアケーキなどを持ち出さずに、宮沢賢治を思い出せばよかったのだ。「銀河鉄道の夜」の冒頭、「午后の授業」で理科の先生がジョバンニたちに見せるレンズ型の模型が、銀河系宇宙だ(ぼくたちもその内部にいる)。そしてそのレンズの表面の方向が星空、直径方向が天の川だ。
そして、つい先日亡くなった社会学者の見田宗介氏の言葉を借りれば:
「〈模型〉とはこの場所の中に無限を包み込む様式である」
天球儀は銀河系宇宙の、もう一つの模型だ。最近ぼくは地球儀を見ると、気候変動やロシアのウクライナ侵攻や、果ては人類の滅亡まで思い浮かんで、実にやり切れない気持ちになるのだが、天球儀はそのような憂いや苦悩を、しばしの間、取り払ってはくれなくても、薄めてはくれる。やっと呼吸ができるような穏やかな気持ちにさせてくれる。時には、現実から意識を逸らしてみることも必要だ。そのことばかり考えていると、鬱になってしまう。
人間は、想像力があれば、あるいはそれを起動させるきっかけになる物や事さえあれば、無限に小さな存在にでも、大きな存在にでもなることができる。今日は、銀河系宇宙全体を俯瞰している大きな鳥になったつもりでいよう。










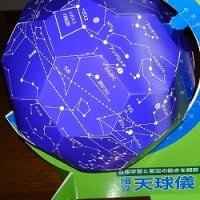














※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます