12日(日)その2.昨日開かれた東京シティ・フィル「第370回定期演奏会」の感想は「その1」に書きました モコタロはそちらに出演しています。是非ご訪問ください
モコタロはそちらに出演しています。是非ご訪問ください





昨夜、NHKホールでN響5月度Aプロ定期演奏会を聴きました プログラムは①パンフィリ「戦いに生きて」(日本初演)、②レスピーギ「ローマの松」、③同「ローマの噴水」、④同「ローマの祭り」です
プログラムは①パンフィリ「戦いに生きて」(日本初演)、②レスピーギ「ローマの松」、③同「ローマの噴水」、④同「ローマの祭り」です 指揮はN響首席指揮者 ファビオ・ルイージです
指揮はN響首席指揮者 ファビオ・ルイージです
私はAプロでは2日目の会員ですが、「東響定期演奏会」と日時が重なったため、N響を1日目の公演に振り替えました 振り替え後の自席は1階L12列12番、左ブロック最後列の右からも左からもど真ん中です
振り替え後の自席は1階L12列12番、左ブロック最後列の右からも左からもど真ん中です 前回振り替えた時と同じ席だと気が付きました。正直言って奥に入った席は苦手です
前回振り替えた時と同じ席だと気が付きました。正直言って奥に入った席は苦手です ついでに言うと、会員席より1つランクが下の席です
ついでに言うと、会員席より1つランクが下の席です しかし、振り替えなので仕方ありません
しかし、振り替えなので仕方ありません

オケは14型で、左から第1ヴァイオリン、第2ヴァイオリン、チェロ、ヴィオラ、その後ろにコントラバスという並び コンマスはマロさんこと篠崎史紀です
コンマスはマロさんこと篠崎史紀です
1曲目はパンフィリ「戦いに生きて」(日本初演)です この曲はイタリア生まれのリッカルド・パンフィリ(1979~)が、2017年にフィレンツェ五月音楽祭管弦楽団の委嘱により作曲、同年12月31日にルイージの指揮で世界初演されました
この曲はイタリア生まれのリッカルド・パンフィリ(1979~)が、2017年にフィレンツェ五月音楽祭管弦楽団の委嘱により作曲、同年12月31日にルイージの指揮で世界初演されました
ルイージの指揮で演奏に入りますが、聴きにくい現代音楽ではなく、比較的耳に馴染みやすい音楽でした どちらかと言うと、それぞれの楽器が発する音の響きを純粋に楽しむような音楽で、特に後半は美しさを感じました
どちらかと言うと、それぞれの楽器が発する音の響きを純粋に楽しむような音楽で、特に後半は美しさを感じました
満場の拍手のなかカーテンコールが繰り返され、1階客席のほぼ中央辺りに座っていたパンフィリがルイージによって紹介され、盛んな拍手を浴びました
2曲目はレスピーギ:交響詩「ローマの松」です この曲はオットリーノ・レスピーギ(1879-1936)が1923年から24年にかけて作曲、24年12月14日にローマで初演されました
この曲はオットリーノ・レスピーギ(1879-1936)が1923年から24年にかけて作曲、24年12月14日にローマで初演されました 第1曲「ボルゲーゼ荘の松」、第2曲「カタコンブ付近の松」、第3曲「ジャ二コロの松」、第4曲「アッピア街道の松」の4曲から成ります
第1曲「ボルゲーゼ荘の松」、第2曲「カタコンブ付近の松」、第3曲「ジャ二コロの松」、第4曲「アッピア街道の松」の4曲から成ります
なお、「ローマ三部作」は、作曲年からは「ローマの噴水」「ローマの松」「ローマの祭り」の順になりますが、指揮者ルイージは、抒情的な「ローマの噴水」を挟み、両端に派手な2曲を置くことで、一繋がりの交響曲のような形で演奏したいとし、演奏順を入れ替えました
オケは14型のまま。ステージ下手にはチェレスタ、ピアノ、ハープがスタンバイし、ステージ上手の2階辺りのパイプオルガンにもオルガニストがスタンバイします
ルイージの指揮で第1曲「ボルゲーゼ荘の松」の演奏に入ります 冒頭から弦・管・打楽器に、チェレスタ、ハープ、ピアノが加わり、壮麗かつ色彩感豊かで壮大な音楽が奏でられます
冒頭から弦・管・打楽器に、チェレスタ、ハープ、ピアノが加わり、壮麗かつ色彩感豊かで壮大な音楽が奏でられます 第2曲「カタコンブ付近の松」では低弦による重心の低い演奏が繰り広げられる中、トランペットの抒情的なソロが素晴らしい
第2曲「カタコンブ付近の松」では低弦による重心の低い演奏が繰り広げられる中、トランペットの抒情的なソロが素晴らしい 第3曲「ジャ二コロの松」はピアノの分散和音に続きクラリネットのソロが演奏されますが、抑制を利かせた松本健司の演奏が素晴らしい
第3曲「ジャ二コロの松」はピアノの分散和音に続きクラリネットのソロが演奏されますが、抑制を利かせた松本健司の演奏が素晴らしい 名演奏と言っても良いでしょう
名演奏と言っても良いでしょう また、弦楽セクションの艶のある響きが印象的です
また、弦楽セクションの艶のある響きが印象的です 最後にナイチンゲールの鳴き声が鳥笛で演奏されますが、客席のあちこちから聴こえてきます
最後にナイチンゲールの鳴き声が鳥笛で演奏されますが、客席のあちこちから聴こえてきます 自席からは演奏者が確認できませんでしたが、どことどこで吹いていたのだろうか
自席からは演奏者が確認できませんでしたが、どことどこで吹いていたのだろうか 素晴らしい囀りでした
素晴らしい囀りでした 第4曲「アッピア街道の松」では池田昭子のイングリッシュホルンの演奏が冴えています
第4曲「アッピア街道の松」では池田昭子のイングリッシュホルンの演奏が冴えています そして、ステージ上の金管楽器群とパイプオルガン席にスタンバイしたバンダ(トランペット、トロのボーン各2本)との相乗効果により壮大な大伽藍を築き上げました
そして、ステージ上の金管楽器群とパイプオルガン席にスタンバイしたバンダ(トランペット、トロのボーン各2本)との相乗効果により壮大な大伽藍を築き上げました
満場の拍手とブラボーが飛び交い、カーテンコールが繰り返されました そして、20分間の休憩に入りましたが、2階中央席辺りから男性の大きな怒鳴り声が聴こえてきました
そして、20分間の休憩に入りましたが、2階中央席辺りから男性の大きな怒鳴り声が聴こえてきました 周囲の人はびっくりしたと思います
周囲の人はびっくりしたと思います 何があったのか分かりませんが、季節の変わり目には、ちょっとしたことでカッと火が付く発火点の低い人物が出没するようになります
何があったのか分かりませんが、季節の変わり目には、ちょっとしたことでカッと火が付く発火点の低い人物が出没するようになります おそらくその種族の一員だと思われますが、コンサートホールは、出演者が大きな声で歌うことはあっても、聴衆側が大きな声を張り上げて怒鳴るようなことはあり得ません
おそらくその種族の一員だと思われますが、コンサートホールは、出演者が大きな声で歌うことはあっても、聴衆側が大きな声を張り上げて怒鳴るようなことはあり得ません 来るべき場所を間違えたのでしょう。恥ずかしいです。大の大人が
来るべき場所を間違えたのでしょう。恥ずかしいです。大の大人が

プログラム後半の1曲目はレスピーギ:交響詩:「ローマの噴水」です この曲は1916年に作曲、1917年3月11日にローマで初演されました
この曲は1916年に作曲、1917年3月11日にローマで初演されました 第1曲「夜明けのジュリアの谷の噴水」、第2曲「朝のトリトンの噴水」、第3曲「昼のトレヴィの噴水」、第4曲「たそがれのメディチ荘の噴水」の4曲から成ります
第1曲「夜明けのジュリアの谷の噴水」、第2曲「朝のトリトンの噴水」、第3曲「昼のトレヴィの噴水」、第4曲「たそがれのメディチ荘の噴水」の4曲から成ります
この曲では、第1曲「夜明けのジュリアの谷の噴水」におけるオーボエの演奏が印象的でした 第2曲「朝のトリトンの噴水」では、弦楽器群が勢いよく水しぶきを上げる様を切れ味鋭い演奏で表現していました
第2曲「朝のトリトンの噴水」では、弦楽器群が勢いよく水しぶきを上げる様を切れ味鋭い演奏で表現していました 第4曲「たそがれのメディチ荘の噴水」では、ラストで静かに鳴らされる鐘の音が印象に残りました
第4曲「たそがれのメディチ荘の噴水」では、ラストで静かに鳴らされる鐘の音が印象に残りました
最後の曲はレスピーギ:交響詩「ローマの祭り」です この曲は1928年に作曲、1929年2月21日にトスカニーニ指揮ニューヨーク・フィルにより初演されました
この曲は1928年に作曲、1929年2月21日にトスカニーニ指揮ニューヨーク・フィルにより初演されました 第1曲「チルチェンセス」、第2曲「五十年祭」、第3曲「十月祭」、第4曲「主顕祭」の4曲から成ります
第1曲「チルチェンセス」、第2曲「五十年祭」、第3曲「十月祭」、第4曲「主顕祭」の4曲から成ります
ステージ上手2階のパイプオルガン席にトランペット3本のバンダがスタンバイします 下手にはピアノが控え、4手で演奏されます
下手にはピアノが控え、4手で演奏されます
ルイージの指揮で第1曲「チルチェンセス」の演奏に入ります 冒頭からバンダを交えた切れ味鋭い衝撃的な演奏が展開します
冒頭からバンダを交えた切れ味鋭い衝撃的な演奏が展開します たった3本のトランペットの別働隊ですが、これが効果抜群です
たった3本のトランペットの別働隊ですが、これが効果抜群です 第3曲「十月祭」では今井仁志のホルン、マロさんのヴァイオリン独奏が素晴らしく、マンドリンの演奏も聴けました
第3曲「十月祭」では今井仁志のホルン、マロさんのヴァイオリン独奏が素晴らしく、マンドリンの演奏も聴けました 第4曲「主顕祭」は弦・管・打楽器総動員によるアグレッシブな演奏により祭りの喧騒が描かれました
第4曲「主顕祭」は弦・管・打楽器総動員によるアグレッシブな演奏により祭りの喧騒が描かれました
この曲は6日前のLFJ音楽祭(井上道義 ✕ 新日本フィル)で聴いたばかりです あの演奏は爆演でしたが、この日のルイージ ✕ N響の演奏も負けず劣らず熱く素晴らしい演奏でした
あの演奏は爆演でしたが、この日のルイージ ✕ N響の演奏も負けず劣らず熱く素晴らしい演奏でした
恒例によりカーテンコールを写メしておきました


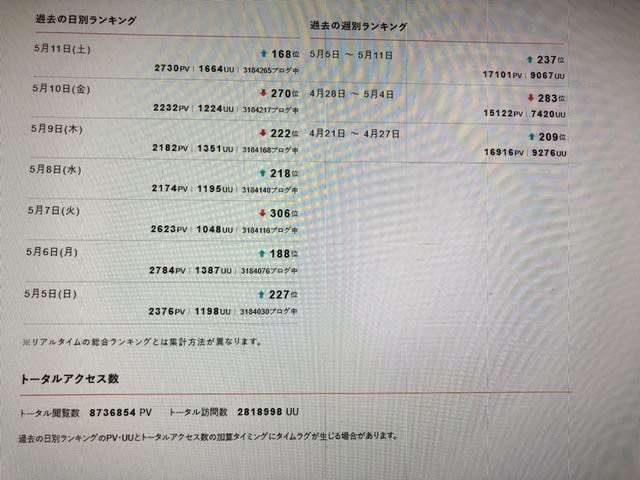

























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます