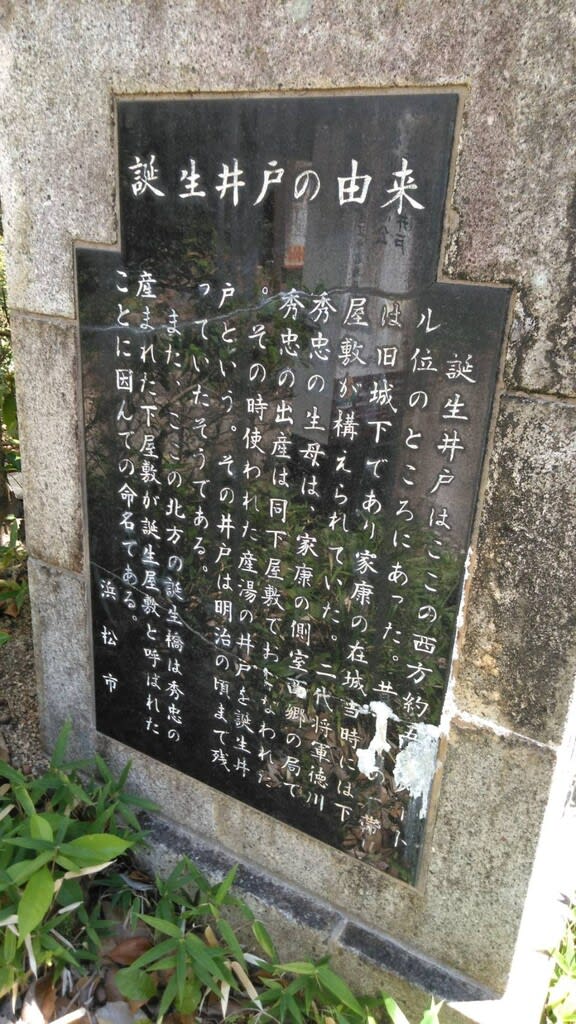会員のカトケンです。
行ってまいりました!京都府へ引っ越してきて、昨夏1日鈍行を乗り継ぎ、一路大津へ。大津京駅で降り、まずは尾花川の膳所藩士「川瀬太宰先生邸宅趾」(=写真)。杉浦重剛謹書、裏面に「大正十一季四月三日/有志の寄附金を以てこれを建つ/尾花川靑年會」と刻む。
行ってまいりました!京都府へ引っ越してきて、昨夏1日鈍行を乗り継ぎ、一路大津へ。大津京駅で降り、まずは尾花川の膳所藩士「川瀬太宰先生邸宅趾」(=写真)。杉浦重剛謹書、裏面に「大正十一季四月三日/有志の寄附金を以てこれを建つ/尾花川靑年會」と刻む。

慶応元年(1865)閏5月、将軍家茂入京に際し、地雷で襲おうとした膳所藩士たち。新選組佐野七五三之助らが京から出動したところ、川瀬の妻幸が少々お時間をといふ間に夫へ宛てた同志の書簡を燃やし、証拠隠滅。川瀬はその後処刑されたーー
川瀬の住まいのあった通り、尾花川は道沿いに昔ながらの住宅が残っていて雰囲気があった(=写真)。そこから三井寺(=写真)の横にある大津市歴史博物館へ徒歩でものの10分くらいだろうか。「京極高次」展を鑑賞。


丹後国峰山藩の殿様京極家の本家であり、将軍家光の伯母常高院の嫁ぎ先として興味があった。
高次の置かれた秀吉と家康との絶妙な距離感、明智光秀との絡みもあって、戦国大名を個別に見ると様々な動きがあり、そのダイナミズムに触れた気がした。大河ドラマにしても、十分1年持つ生涯ではないかと思った。
その日は客足も大勢で、福田千鶴先生の講演会が催され、その時間になったら展示室の人たちがドッといなくなった。小弟はといふと、申し込み忘れてしまっただけである。
ただし、展示がじっくり見られた上、常設展では大津京の復元模型なども堪能。また博物館の過去の展示図録が充実しており、ちょうど大河ドラマ「麒麟がくる」の年に催された展示図録を求め、少し前に訪れた丹波篠山と光秀の関係なども分かり、収穫であった(写真は博物館からの琵琶湖の眺め)。
高次の置かれた秀吉と家康との絶妙な距離感、明智光秀との絡みもあって、戦国大名を個別に見ると様々な動きがあり、そのダイナミズムに触れた気がした。大河ドラマにしても、十分1年持つ生涯ではないかと思った。
その日は客足も大勢で、福田千鶴先生の講演会が催され、その時間になったら展示室の人たちがドッといなくなった。小弟はといふと、申し込み忘れてしまっただけである。
ただし、展示がじっくり見られた上、常設展では大津京の復元模型なども堪能。また博物館の過去の展示図録が充実しており、ちょうど大河ドラマ「麒麟がくる」の年に催された展示図録を求め、少し前に訪れた丹波篠山と光秀の関係なども分かり、収穫であった(写真は博物館からの琵琶湖の眺め)。

そこから琵琶湖疏水の大津側の口を見つつ(=写真)、川瀬太宰の墓を探したがたどり着けなかった。これは次回の課題としたい。京都へ抜ける街道沿いにある場所にあるはずなのだが、よう探せなかった。

気を取り直して最終目的地、土佐藩出身で明治新政府に全国の仲間と抵抗した堀内誠之進の墓を目指した。小弟の卒論を参考文献に掲げてくださった遠矢浩規先生の著書『明治維新勝者の中の敗者ー堀内誠之進と明治初年の尊攘派』(山川出版社、令和3年刊)に載った月見山墓地にある墓碑である。
滋賀県庁の南側の通りを東へ行き、大きな通りの少し手前に月見山墓地への参道がある(=写真)。民家に突き当たって左側に進むと墓地へ通ずる道がある(=写真)。


東海道線が見え、ホテルアルファワンを背にやや茶色みがかった自然石の墓が他の墓に挟まれるように建っていた(=写真)。JR大津駅から徒歩で十分行ける距離にあった。

薩摩の横山安武(森有礼の兄)など自ら身体を張って反抗するなど、できたばかりの明治政府を転覆しようとした堀内のような人たちは大勢にはならなかったが、かなり全国展開しており、それだけ明治政府が初期から民衆のためになっていない政治を行い、馬脚を露わしていた証であろう。
土佐と近江の関係は、山内一豊が長浜城主を務めたり、その母法秀尼の墓が近江国坂田郡(滋賀県米原市)にあるなど深いものがあるから、堀内の墓もまた1つその関係に1ページを加えた史跡として刻まれよう。
だいぶ時代が錯綜するが、幕末のみならず戦国時代の土佐関係が絡むと京都でも一豊とその夫人見性院や、見性院から一豊へ石田三成の挙兵を伝えた家臣田中孫作の墓が妙心寺大通院にあるし、明治にも琵琶湖疏水建設に尽力した坂本則美や河田小龍との関係も相まって話題が尽きない。
坂本則美は、このほかにも兄則敏がつくった堕胎・圧死の悪い習慣を矯正するための組織「しんしん社」(漢字は言偏に先の繰り返し)の社長となり、その経営に尽くした人で、高知県議、京都から衆議院議員にも出ている。その後、鉄道や炭鉱会社の社長を務めた。大徳寺芳春院に墓があるというが、見学できるのだろうか。龍馬以外の土佐の坂本にもこうした注目すべき人物がいる。
河田小龍については、昨年11月に高須の高知県立美術館で20年ぶりに絵の展示が催された。岡豊の高知県立歴史民俗資料館と桂浜の高知県立坂本龍馬記念館と3館同時開催と云ふまたとない小龍祭りであったが、残念ながらこの絶好の機会を逸してしまったーージョン万の漂流記を絵を交えて記した『漂巽紀畧』の著者であることはもとより、坂本龍馬・近藤長次郎・新宮馬之助ら亀山社中から海援隊になる海の漢たちを育てた師匠の足跡にもっと光が当たってもよかろう。小龍の墓は等持院にある。
幕府側からみた琵琶湖疏水として、田辺朔郎やその岳父北垣国道を以前このブログでも取り上げたが、案外土佐の人が関わっていて面白い。
高知県令も務めた鳥取出身の北垣と坂本龍馬、おそらく千葉重太郎との関係からできた人脈と思うが、その辺りも絡んできてなおさら興味深い。
ともあれ、ようやく目的を果たし、帰途に就いたが果たして、堀内誠之進ゆかりの土佐の墓も訪ねてみたいと思い、また新たに土佐での深掘りを続けたくなった。関西に来ると、土佐が一段と近く感じた。
さて、来たる2/8(土)第27回土佐史談会関東支部例会「長宗我部氏と土佐の自然」(東京都立大大学院生吉澤林助氏による講演)、ぜひお越しください。東京都港区新橋の酒菜浪漫亭15:30〜。お待ちしております。
*******************************************************************
★ガイドブック『探墓巡礼 谷中編~箱館戦争関係人物を歩く~』のご注文は下記フォームよりお申込みください。
★ガイドブック『探墓巡礼 谷中編~箱館戦争関係人物を歩く~』の告知チラシを公開しています。
★下記SNSにて当会の最新情報を更新しています。是非フォローください。
*******************************************************************