NHK文化センターの講座「フィンランドを知る」が、フィンランド大使館を会場に開講された。
まずアンナ・グスタフソン大使夫人による「フィンランドの女性について」の講義。
大学はやりたいことを求めて専攻を2度かえながら8年在学、そして外務省でバリバリ仕事をしていたアンナさん。子育て真っ最中のお母さんでもある彼女の体験や、日本とフィンランドの比較も含めてのお話はとても興味深かった。世界で最初に女性問題に取り組み、いまや大統領も首相も女性、国会議員の4割は女性、閣僚の半数は女性という国の歴史と現状を伺い知ることができた。フィンランド女性というと強いイメージがあるが、通訳の下村さんの説明では、「実はとっても奥ゆかしい女性なんです」。
そして私の「音楽でフィンランドの紹介」。
前半はカンテレの起源である5弦、後半は16弦を演奏。フィンランド民謡やオーロラ、森、自然をテーマにした曲を選び、トークも交えての時間。
そしてお楽しみティータイム。
ブルーベリータルト
カレリアパイ
キャベツのパイ
シナモンロール
私たちはフィンランドカラーで。
カンテレメンテナンス講座を開催した。講師の松島洋氏は建築家、ご自身もカンテレを嗜む。カンテレに故障がでるとアドバイスや修理をお願いしていたが、このたび<カンテレメンテナンス講座>として、カンテレの構造の勉強、お手入れ方法、そして弦の張替えを行った。

今回は、10年以上使っているものから3年までの5・10(11)弦の小型カンテレが対象。30年前にプレゼントされた手作りカンテレ、20数年前の卒業旅行の思い出がつまったカンテレ、そして今はないメーカーやビルダーの手によるカンテレもあり、16台のカンテレは7社製。
松島さんの丁寧な手技で、午前中から暗くなるまで続いた。弦の張替え、ペグや調弦金具の微調整、本体の歪みの修正・・・、ピカピカにお化粧直ししたカンテレの音色はさっきまでとは別物のように、いい音がする。「さあ、また頑張りましょう!」とカンテレを大事にかかえ、心地よい気分で会場をあとにした。
今週はカンテレウイーク。
(日)10・11弦グループクラス
秋の交流会にむけてアンサンブルの練習を始める。弾きためた曲の中から候補を選び、曲決め。10弦(11弦)のアンサンブルのほかに、10弦+5弦の3部編成にアレンジした曲も加えることになった。
(水)5弦、10弦、11弦、16弦、26弦のレッスン
仕事帰りにかけつける人が多い第3水曜日。Sご夫妻は妻5弦、夫10弦でそれぞれ弾いているが、デュエットがすばらしい。「さすがご夫婦」の息ピッタリだが、「お互いこっそり練習しているのよ」。Nさんは5弦を始めてまだ数か月、「5といえどもむずかしい。でも面白い~」とひたすら励む日々らしい。11弦のMさんは「上手になりたいから毎日一生懸命弾いています」。26弦は東海道線下り組、横浜・大船・平塚・・・と偶然同じ方向へ帰る。ソロのほかに、時間を合わせて練習する成果は<カンテレオーケストラ>と称して壮大な曲に取り組む。いわゆるアンサンブルとはまた違った感じで、楽しめる。
(土)5弦グループクラス
5弦が大好きな人ばかり。5本の可能性に面白さを感じ、テクニックを磨き、響きと音楽性を追求する。今回はクラス後に<カンテレメンテナンス講座>を開催し、弦の張替えとその他のメンテナンスを研修する。
私も皆さんと一緒にカンテレを楽しむ。アレンジを加えたり、即興を入れたり、またアンサンブルでは足りないパートに回ることも。小型から大型までカンテレの魅力をたっぷり味わう今週、カンテレ三昧!
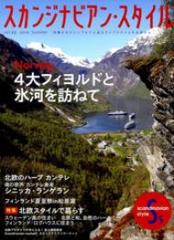
待っていた雑誌『スカンジナビアン・スタイル』をポストに見つけた。5月に来日した ノルウェーのミュージシャン、シニッカ・ランゲラン が紹介されている。編集部から「取材したい」とのご連絡をいただき、 コミュニティカフェでのコンサート&ワークショップ と 東京コンサート の2回取材にいらした。
雑誌名のとおりスカンジナビア=北欧を取り上げた雑誌。洗練されたシンプルで上品なライフスタイルを北欧から提案する幅広い視点に、私は創刊からのファン。
25号(2010 Summer)は以下の内容。
Norway 4大フィヨルドと氷河を訪ねて
特集 北欧スタイルで暮らす
(スウェーデン風の住まい・北欧と和、自然のハーモニー フィンランドログハウスに住まう)
北欧のハープ・カンテレ 魂の歌声 カンテレ奏者シニッカ・ランゲラン
フィンランド夏至祭 in 松原湖
北欧プロダクツが手に入る! 誌上通信販売 スカンジナビアンマーケット
パラパラみていて、知人を発見。 3年前セントレア中部国際空港のトーク&コンサート でご一緒した、道田聖子さん が載っている。スウェーデン人のご主人と住む家は北欧そのもの、「いいなぁ、こんな暮らし」。そして今ごろスウェーデンでゆったり夏休みを過ごしているはず。
発売したばかり。その後お買い物ついでに近所の本屋さん数店でチェック、どこでも並んでいた。
840円・イーストリーム発行。
日曜日は 10弦カンテレクラス だった。このクラスはかれこれ10年以上続いているクラスで、日本フィンランド協会カンテレ同好会 が母体となっている。「このグループはもう何年?」に何気なくカンテレを裏返したら、ビルダー(製作者)のサインと1999年の日付入り。「きゃ~、もう10年以上」と、Yちゃん、Sママ、T子さん、Aurinkoさんなど数名が絶叫。遅れてN子ちゃん、そしてまだはじめて数か月のKさんが「そんなにィ!」とびっくり。
レッスン曲は、私の新曲<kehtolaulu/2010kesa こもりうた・2010夏>。「なんかフィンランドっぽいよね~」の感想に、私だってそう思っている。30年以上もフィンランドと濃厚なお付き合いをしていれば、感覚は無意識のうちにフィンランドになってくる。10弦、11弦、16弦で練習。「涼しげ。いい、この曲」と言われ、作曲者としては本当にうれしい。
Yちゃん「きっと今日のブログはこのテーマだよね。皆なかなか弾けなかった。むずかしいって言ってるって書かれるよね~」 私「そんなことないわょ。皆さん上手って書く」と応戦。ブログ愛読者のT子さん「ブログの文章まで皆で考えちゃう、楽しい」。そうなんです、私のカンテレ仲間(一応、生徒さんたち)は本当にステキな楽しい仲間たち。
ところでこの曲、夕方から一緒だった音楽家に聴かせたら「いいねぇ」とほめられ、気をよくしている。なかなか厳しい評価もくだすので、ほっとした。カンテレ仲間たちはそれぞれレパートリにするそうで、大好きな仲間たちに感謝している。
昨秋は皆でフィンランドへ演奏旅行
最近曲をかいている。かいているというより「わいてくる」の方が正確な言い表しかもしれない。通勤の電車で、ぶらぶら歩きながら、夕食を作りながら・・・、日常のあらゆる場面で浮かぶ音楽、音。その都度、いつも持ち歩いている五線紙ノートに暗号のように書き留める。
今日はカンテレ曲2題。ひとつは<RAKKAUDELLA・愛をこめて>、もうひとつは<KEHTOLAULU・こもりうた>。どちらも一瞬にしてできた曲で、次々メロディフレーズや音がわいてきた。それは「内なるもの」から醸し出される勢いで、どちらもおおいに気に入っている2曲。
作曲科に進もうかと思った時期もあったので、一応ひととおりの知識はある。作曲は「曲を作る」から、できあがったものはやっぱりクラシック系。4小節×4段、起承転結のある曲は優等生の唱歌のよう。和音進行やリズムなど、持てる知識や経験を駆使して整えてしまう。でも最近は「曲を作る」より、「音楽がわいてくる」が多いので、イメージ先行になっている。嬉しいとき、楽しいとき、気分がいいとき、そして悲しいときにもわいてくる音楽がある。でも辛いときや苦しいときにはなぜかわいてこない。
さきほどの2曲、もしこれを歌にするならと、友人の音楽評論家に「曲と詩、どちらがさき?」と聞いたら「多くは曲かな」。ふ~ん、そうなのぉ。基本的にカンテレ演奏用にかいたメロディだが、もしステキな歌詞(歌詩)を提供してくれるなら、と詩人の友人に聴かせてみようと思う。
今月の5弦カンテレクラスの課題は<鐘のポルカ>。フィンランドの古い民謡を、カンテレの大御所であるMartti Pokelaが5弦用にアレンジした曲は、5弦学習者には必須の1曲である。
楽譜上の音はそうでもないが、そこに隠されたテクニックは並大抵のものではない。ハーモニクス(オクターブ)は1オクターブも2オクターブもある。2オクターブは「でな~い! やりにくい! 音がかたい、綺麗な音じゃない」と悪戦苦闘。人差し指奏法の記号は「エッ、これは右手? 閉じてる方だから左手?」。楽譜にある数字は、カンテレの弦の本数の1~5と指番号(本数)の1~5と紛らわしい。この記号は爪側だっけ? ・・・ とひとつひとつ確認しながら進める。
私はこの曲が大好きで、5弦カンテレを演奏するときは必ず選曲する。ポルカは風に舞うような軽快な音楽。このテクニックは早く弾いてこそ活かされるものだから、ポケラの録音を聴いて、その超人的な演奏にため息が出るほどだった(もちろん今でも!)。自分で納得がいく仕上げに半年はかかり、さらに私の音楽性を加えて作り上げるのに珍しく時間を要した難曲である。
1時間半のレッスンはあっという間に過ぎていく。「むずかしい。でもすごくいい曲だから弾けるようになりたい」の感想に、「この曲はじっくり取り組みましょう」「帰ったら早速復習ね~」。
フィンランドのカンテレ奏者で、5弦も得意とする
ヴィルマ・ティモネン (2006年11月)
ミンナ・ラスキネン (2009年11月) 
たちも、東京でのコンサートやワークショップでポケラを取り上げた。<鐘のポルカ>に限らず「ポケラは本当にむずかしい。ポケラは天才」と絶賛していたことを思い出す。
<鐘のポルカ>は5弦カンテレの醍醐味を存分に味わえる曲。「だから5弦がいちばん好き!」とその他に10~36弦をかけ持ちする人が多いクラスだが、こよなく5弦を愛する13年目のクラス。
<カンテレと筝のアンサンブル>、エヴァ・アルクラ と 中井智弥さん のコンサートを聴いた。CD「楊貴妃」の発売記念のツアーで、全国展開している。今月初めフィンランド大使館で行われたトークショーで演奏も聴いているが、そのときは3曲のみだった。
エヴァが演奏するのは39弦エレクトリックカンテレ。フィンランドでもこの楽器を演奏する人は少なく、エヴァはその第一人者ともいうべく、トップレベルの演奏家。エヴァの演奏は優雅で、まるで蝶が舞っているよう。またテクニックもすばらしく、知性と理性に裏づけされた音楽が醸し出される。
二人が出会ったのは5年前、その場に居合わせた私は二人の成長を、まるで子育てする母の気持ちで見守り、エールを送ってきた。カンテレと筝? 最初はその音量や音質の違いにどこに接点を見出すのかと思っていたが、二人は演奏を重ねるごとに「お互いの楽器や気持ちを思いやり、音楽を作りながら」(中井さんの言葉)、見事に華ひらいた。そしてまだまだ華が大きく大きく広がることを予感させる演奏だった。エヴァは来日するたびに「智弥とあわせるのが楽しみ」と言っているが、二人の音楽に対するあつい想いはますます燃え上がっている。若い二人のエネルギッシュな音楽への取り組みとその真摯な姿勢に、次を期待し、そして大きな拍手とエールを送る。
カンテレクラスでは、毎回ソロの曲といくつかのパートに分かれるアンサンブルの曲を課題にしている。今までは同じ大きさ(弦の本数)のカンテレでアンサンブルを組むことが多かったが、最近は様々な大きさのアンサンブルを楽しんでいる。
土曜教室・5弦グループや日曜教室・10(11)弦グループは、同じ種類でテクニックを駆使して楽しんでいる。この2クラスはかけもちの人が多いので、「両方もってきちゃった」ということもしばしば。また平日教室は、小さな5弦から大きな36弦までのカンテレがでたり入ったりという利点を活かして、異種類の組み合わせができる。5弦+11弦+26弦、11弦+36弦、組み合わせによってはドッペルコーラス、26弦×数台のダイナミックアンサンブル、早い人が残り遅い人を待って全員集合で5~36弦まで7台集合ということもある。
「楽しい~」と、フィンランドの伝統曲では民族ダンスのステップも踏んでみる。日本の曲のアレンジやオリジナル曲もある。作曲家の友人から委嘱曲ができてきたし、他の作曲家数人にも依頼している。「カンテレの特性を最大限に活かした曲をお願い」と注文したら、「じゃぁ、カンテレを練習しなきゃ・・・」と私のカンテレを貸し出し中。
「これいい! 今度の交流会(発表会)はこれやりましょう」と少しずつふえていく。レパートリーが広がり、ますますカンテレを楽しむ。
ノルウェーの シニッカ・ランゲラン からメールが届いた。「古代日本にもカンテレプレイヤーがいた」というタイトルで、写真つき。「はぁ?」と思いながらメールを読み進むと・・・
I found this wonderful kanteleplayer in Tokyo National Museum, terra cotta 6 th century. She is lovely. I think it is marvelous and I dont know if the kantele people know about this. Did you know about her? I asked if it was ok to take a picture and took with my mobilcamera.
たしかに! カンテレを演奏しているように見える。国立博物館はよく行くけれど、常設は多分2回くらいしかみたことがなく、あまり覗かない。この展示の“彼女”にも全く記憶がない。失礼しましたぁ。「今度上野に行ったときはお寄りしましょ」とカンテレ仲間に言ったら、「今度ではなくすぐ行きましょうよ」と、早速行くことにした。“彼女”は何を奏でているのかしら。
「夏のフィンランドを弾いてくれませんか」との依頼をいただいた。演奏とトークの1時間プログラムを考える。夏の曲はたくさんあるから、すぐに構成がうかぶ。この30年間で集めた歌の楽譜は本棚1つ分あるので、楽譜をひっぱりだしたら、リビングの床いっぱいに足の踏み場もないほどになった。歌の楽譜は、歌詞を吟味しながら景色や情景を思い起こせるので、曲のイメージをつかみやすい。カンテレ用にアレンジを加えて、おおまかな内容を作ってみた。
カンテレ弾きながら、歌いながら、夏のフィンランドに思いを馳せる。
フィンランドを感じる小さなカフェ<Cafe Kieli>で、カンテレコンサートが開催される。当日店主のMiさんからご案内をいただいた。
<Cafe Kieli+Kanteleミニコンサート>
<Cafe Kieli+Kanteleミニコンサート>
フィンランドの素朴な焼き菓子たち
コーヒーはArabiaのヴィンテージカップに注いで
大好きなカンテレの音に耳を傾ける
私にとって最高に贅沢なひととき
6月10日(木)の夜、1日カフェ店主となったMiが
そんな時間を
皆様にもちょっと、おすそ分けしちゃいます
フィンランドを感じる小さなカフェ Cafe KIELI
どうぞ遊びに来て下さい☆
***
日時:6月10日(木) Cafeオープン 17:00~ Kantele演奏 19:00~
場所:池袋 禁煙カフェMODeL T (東京都豊島区西池袋3-33-17 立教大学近く)
料金:ライブチャージ¥500+ワンオーダー
■Kantele演奏
Päivi Ollikainen(パイヴィ・オッリカイネン)
ヘルシンキ生まれ。
カンテレ奏者&シンガー。
コンサートカンテレをパーカッシヴに用いる独自のスタイルで、ポップスやジャズの弾き語りを得意としている。
現在、シベリウス音楽院より北海道教育大学に留学中。
※注意事項:
店内・店外すべて禁煙となります
愛煙家の皆様、ご協力をお願い致します
※上記は現時点での情報です
開催日までに変更が生じる可能性があります
パイヴィの演奏は、
日本カンテレ友の会 総会(1月・札幌)で聴いた。
大ファンというマイケル・ジャクソンをはじめ、カンテレ弾き語りやカンテレをパーカッションのようにリズミックに弾きこなす奏法。長年、民族調やクラシック調で弾いている私には、唐突で衝撃的な印象だった。でも演奏が進むにつれ、音楽はフィーリングも大切な要素だから、「色々なアプローチがあっていい」と思えるようになっていた。
フィンランドのシベリウスアカデミー(音楽院)では、音楽教育が専門。楽器専攻にカンテレを選択しているパイヴィだからこその演奏を楽しみにしている。
フュッセンのレストランで南ドイツの郷土料理を堪能していたら、突然音楽が聴こえてきた。「エッ? カンテレ?」とその音色に振り向くと、カンテレのような楽器。でもカンテレではなさそう・・・
弾き手は70代の男性。
優しい音色に、食事の手をとめて聴き入る。
楽器の名前は<チター>。あの『第三の男』で有名な楽器。
「カンテレはチターの仲間」という紹介がよくあるが、実際の演奏をみたのは初めてだった。チューニングのやり方もカンテレと同じようだが、弦の張りが緩めなのか、もう少しやわらかい淡い音色がしている。
地元の民族音楽を中心に30分のBGMコンサート。ビアホールか居酒屋だったら一緒に《エーデルワイス》を歌ったのだが、格式あるレストランではそうもいかず・・・。
カンテレはフィンランドの伝統民族楽器。日本でも東京、北海道を中心に愛好家が多く、2年前 <日本カンテレ友の会> が 設立された。副理事長のひとりとして事務局(理事長はフィンランド在住でフィンランドカンテレ協会会長のEva Alukla)をあずかる私のところには、様々のお問合せや全国各地からの演奏依頼も多く、カンテレが少しずつ広まっていることを嬉しく思う。
先日 Sinikka Langeland(シニッカ・ランゲラン) というノルウェーのミュージシャンからメールが届いた。彼女はフォークソング(民族音楽)、ジャズ、クラシックと幅広く活躍している 世界的なミュージシャン。フィンランドのシベリウス音楽院で勉強していたこともあり、音楽活動のひとつにカンテレ奏者の顔もある。「5月に来日するので、是非交流やコンサートをしたい。よろしく!」という内容。すごい! そして「ヒェ~」と慌てて走り回る。以下のようにコンサートが決まったので、速報でお伝えする。
<Sinikka Langeland カンテレコンサート in TOKYO>
日時:2010年5月23日(日)14時開演
於:Salon’d TOSHIN (東京駅八重洲口)
お問合せ:オフィスフーガ (music-fuga@n07.itscom.net 044-722-6062)
詳細は決まり次第発表。
<Sinikka Langeland 札幌公演>
日時:2010年5月28日(金)19時開演
於:コンカリーニョ
料金:3000円(前売り)、3500円(当日)
お問合せ:Green Pigeon Music(greenpigeonmusic@gmail.com 090-6218-7045)
詳細は、こちら (あらひろこさんのブログ)
このほかにも、カンテレクラスでのレッスンや地域コミュニティ活動でのワークショップなど企画中。
恒例のカンテレ交流会も今年で3回目。東振フーガ教室、日本フィンランド協会カンテレ倶楽部、カンテレ市ヶ谷(旧・東京YWCA砂土原センターカンテレクラス)などの生徒さんたちが集まり、賑やかに開催した。
発表・親睦・交流が目的の会で、今回は5弦、10弦、11弦、16弦、26弦のソロ、アンサンブルの演奏。生徒さんのほかに、入会希望者やフィンランドからのお客様も交えて、カンテレを楽しんだ。
10弦でフィンランドの民族ダンスの曲。
会友・盲導犬ハックも傍らでうっとり。
5弦の有名な曲<教会の鐘>には26弦で鐘の音を。
<嘆きの少女>にますます磨きがかかるYさんは、
フィンランドで新調したトナカイ柄の衣装で。
「老後の楽しみに」と長い人は10年選手の5弦アンサンブル。
さまざまな大きさのカンテレを身近に感じながら、あちこちでカンテレ談義。「ちょっと弾かせて!」と26弦の生徒さんは「5弦って面白い」。「大きいのもいいわね。半音レバーつきの16弦に挑戦しようかしら」「初めてであがってしまった・・・。来年はもっと頑張りま~す」
フィンランド演奏旅行チームも、現地での演奏を再現。そして演奏の合間に探したフィンランドグッズがもれなくあたるお土産抽選会、会食・・・とカンテレとフィンランドを楽しんだ一日だった。









