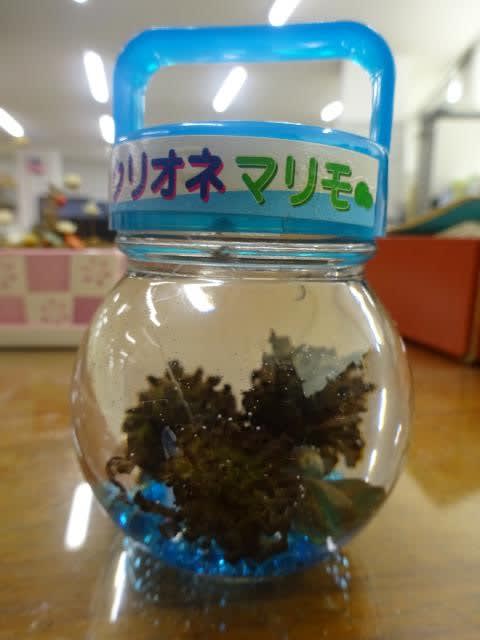クロアチアで最古かつ最大の国立公園。
入口は2ヶ所あるが、この入口1はいつもこの様な長蛇の列となり、
1時間程入園するのに待つこともあるそうだ。
我々はガイド付きグループということで待つこともなくスイスイと入れた。

当湖群は1949年に国立公園に指定。
1979年にはユネスコ世界遺産に登録された。
面積は29,630.8ha、最高地点1278.5m、最低地点368.5mの高低差がある。
園内には多数の小さなものも含めると湖が16以上もあり、
Veliki Slapという滝は78mあり、クロアチアで最も高い滝だ。
湖ゾーンには8つのツアーコースがあり、ハイキングコースが完備されている。
ところでこのサングラスがよく似合う美人女性が我々のガイドさんです。

入口から少し歩くと突然、この滝が目に飛び込んできた。
思わず皆が、「ウォー!」との感嘆の声。
目の前には幻想的な光景が拡がっていた。




マラ・カペラ山脈とリチロ・プリェシャヴィッツァ山脈に囲まれた
プリトヴィッツェ湖群にある一番大きい滝が
このヴェリキ・スラップ(大滝)だ。
ここは一生に一度は訪れたい世界の絶景にも選ばれている、
癒しの楽園と言われている。


私達は8つのツアーコースの中でもハイキング初級クラスの
歩行距離2kmコースを歩いた。
木道はちょっと狭いがしっかり整備されて
素晴らしい光景が目の前に拡がり続いた。


ここはトラバーチ障壁で隔てられたターコイズ色の湖が
多数あることで知られている。
特徴として国立公園の国際的重要性を高めたカルスト地形は
水文地質学的性質によりドロマイトが水を保持し、
石灰質堆積物中に峡谷が出来上がった。

この断面表示を見ると湖が段々畑状態になり、
多くの大小の湖を形成したのがわかる。

この整備された木道を歩く、
クロアチアのサッカーユニホームを着た青年とブルーシャツの少年。

透明度が高い湖水は、その時々の太陽の光、
水中のミネラル量によって様々に色が変化するそうだ。


多数の動植物が生息する森林や草地が豊かに広がる地域、
公園のほぼ80%が森林で覆われている。
上の写真をよく見るとジグザグに道があり、
多くの人達が歩いているのが豆つぶのように見える。


透明性の高い湖の中を見ると所々に小魚の群れを発見することができる。
この魚はチャブというコイの仲間の魚らしい。




公園の一番大きな滝、ヴェリキ・フラップのたもとに着いた。
この場所は広場になっており、歩いた疲れを癒す休憩所に丁度よい。
そして目の前に滝が落ち、オゾンに満ちていて、
その中で人々はなぜかテンションが上がっていた。
ひょっとしてここの名物オジサンか?
パンツ一枚でヘラクレスの様に弓を引くポーズをいつまでも続け、
人々にウケていた。





この国立公園は深い森に映えるエメラルドグリーンの
湖と湖を結ぶ滝が最大の見せどころで
特に丁度行った6月~8月の夏がベストシーズンとか。
気温が30度を超えることがまれなこの時期、
ズバリ夏が1年で一番輝く時期と言われている。
いやー、本当に最高でした!!


落差10mと小さな滝だがオペラ歌手の名を取ったミルカ・トルニナの滝。


湖畔は上湖と下湖に分かれて、まだ石灰華の形成過程にある。
下湖群から上湖群へは約20分程度のボートで渡る。
このボートに乗る為の長蛇の列ができていた。
又ここには疲れを癒す為の休憩所、広場、トイレがあり、
多くの人々がリラックスして休んでいた。



これが乗るのにウェイティングした船と到着しそうな船着場。
海外旅行でこれだけハイキングする旅も珍しい。
とてもリフレッシュできた時を過ごせた。