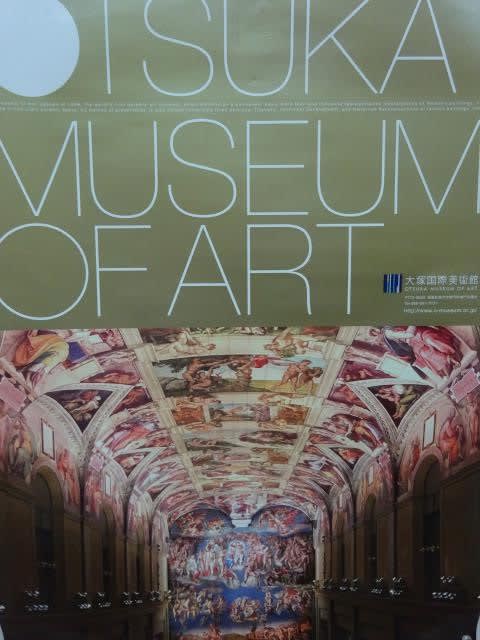今までそれとなく何度も来た日比谷公園。今回は時間が
ゆったりあり、しみじみとじっくり広い園内を歩いてみた。
唯残念だったのは時間帯が夕方で写真が全体的に暗めになってしまった。
ここは10ヶ所ある門の内の日比谷交差点の角の有楽門。

日比谷公園は幕末までは松平肥前守等の屋敷地で、
明治初期には陸軍練兵場となっていたところだった。
当初から近代的な「都市公園」として計画・設計・造成された
本格的な公園であると同時に、日本初の「洋式庭園」として
明治36年(1903年)6月1日に開園した。(開園面積161.636㎡)
文化の先駆者としての公園設計者(本多静六等)の
意気込みが随所に感じられる。

この石垣は、江戸城外郭城門の1つの日比谷御門の一部の
日比谷見附跡。城の外側から順に、高麗門・枡形・渡櫓・番所が
石垣でかこまれていたが、石垣の一部だけがここに残っている。

ここは日比谷公園ができる前は濠であった。その面影を残すために
公園造成時に池としたもので、全体を上から見ると「心」の字を
くずした形をしているところから心字池と呼ばれている。
遠くに雪吊りが見える。金沢兼六園の小型版だ。

都心のど真ん中にオオアオサギ(?)がいたのにはビックリした。
さすがここは都会のオアシス、まだ自然が残っている。


日比谷公園からは一際目立つ真新しい超高層ビルが
目に迫ってきた。このビルは3月29日にグランドオープンする
TOKYO MIDTOWN HIBIYAだ。キャッチコピーは
芸術文化、エンターテイメントの街「日比谷」が花開くだ。


日比谷公園の管理事務所として明治43年(1910年)11月に
竣工したドイツ・バンガロー風のしょう落な建物。昭和51年(1976年)
より公園資料館として内部を改造して使われているフェリーチェガーデン。
管理事務所がこんなお洒落とはやはり明治はすごい時代だ。

今回の日比谷公園探訪で一番の発見はこの地が仙台藩祖
伊達政宗が江戸参勤の折、寛永13年(1636年)5月、
70才の生涯を閉じた所だと知ったことだ。ここは仙台藩の
上屋敷があったところで、政宗の時代に家康が3度、
秀忠と家光がそれぞれ4度。ここを訪れ、もてなしを受けたことが記録に残っている。


ペリカン噴水から見た第一花壇。ここは日本最初の洋式庭園として
残されたドイツ風の沈床花壇だ。バラを主体に植栽され、
花壇中央にはシュロノキが植わっている。


桜門の隣りにある日比谷茶廊。ここは1949年(昭和24年)
創業の老舗ガーデンレストランだ。おそらく日本で最も
古いガーデンレストランで自然の心地良い風を感じながら
過ごすことができる。なぜか入口の所にタイのタクシー
「トゥクトゥク」が置いてあったのが気に成った。

昭和13年にイタリアから東京市に寄贈された「ルーパロマーナ」
(ローマの牝狼)。ローマ建国の大業を成し遂げた
ロムルス・レムス兄弟の有名な伝説に基づいた像だ。

日比谷公園の梅林は大噴水広場のそば小音楽堂の
西側にある。白梅・紅梅とも例年2月中旬に見頃になる。
この日2月10日は開花したばかりか。今年の冬は既に
2回も雪が降り、寒い日が続いている由。

日比谷野外音楽堂は、我が国初の野外音楽堂として
1905年(明治38年)に完成した。大正12年9月の関東大震災で
倒壊したが、後日再築。1983年(昭和58年)には
大音楽堂と同時期に改築されて現在に至っている。客席数は1075席。



噴水広場にある大噴水は日比谷公園の最大のシンボルだ。
毎日AM8:00からPM9:00までの稼働、28分間周期で
24景を楽しめる。噴水池は上中下段の三段構造。池の直径は30m、
主噴水の吹き上げ高さは12mに達する。このエリアは
テレビや雑誌などの撮影のポイントとしてしばしばメディアに登場する。
噴水アップの向こうには日比谷公会堂(2枚目写真)、
そして帝国ホテル(3枚目写真)が見える。

日比谷公会堂は後藤新平東京市長の主張に安田善次郎が
共鳴し巨額の350万円を寄付して、1929(昭和4年)に竣工した。
かつては東京では事実上唯一のコンサートホールとして
プロフェッショナルのオーケストラの演奏会やリサイタルなど
多く開かれた。しかし音響に問題があるとして講演会、
イベントなど音楽会以外の利用が増えた。1960年10月12日
浅沼稲次郎暗殺事件はここの立会講演会で起きた。


銀座で食堂を経営していた小坂梅吉が日比谷松本楼として
1903年6月1日にオープン。当時としては珍しい洋風レストランとして
人気が集まった。その後関東大震災により焼失。そして復活したが
太平洋戦争が始まると、軍の陣地、海軍省の将校宿舎となり、
終戦後はGHQ宿舎として接収された。1971年(昭和46年)
11月19日、沖縄返還協定反対デモが日比谷公園で激化し
(日比谷暴動事件)、中核派の投げた火災瓶の直撃を受け
焼失の憂き目にあった。現在の3代目松本楼の
オープンは1973年(昭和48年)9月26日再スタートを切った。

松本楼入口の隣りには「首賭けイチョウ」という大木生えている。
園内でもとりわけ大きなこの木は推定樹齢400~500年、
幹周りは7mもある。元々、現在の日比谷交差点あたりにあって
道路拡張のための伐採寸前にあったところを、本多博士が
「私の首を賭けても」といって明治35年に移植させた。
このイチョウは日比谷公園のシンボルとして今や人々に親しまれている。

この石橋は、芝増上寺霊廟の旧御成門前桜川にあけてあった
石橋の一つで、道路構築の時、ここに移したと伝えられている。
素朴なうちわにも力強く、江戸時代の掘りの深さを漂わせている。


雲形池の中にある鶴の噴水。この噴水は、明治38年頃、
東京美術学校(現在の東京芸大)の津田信夫、岡崎雪声両氏に
依頼製作したもので、公園等での装飾用噴水としては、
日本で3番目に古いもの。(1番目は長崎諏訪神社、2番目は
大阪箕面公園)水面に薄氷が張り鶴の像につららが下がる景色は
当公園の冬の風物詩となっている。1月の大雪のニュースでも
この鶴の氷結した姿が度々報道されていた。

とても眺めのよいレストラン「日比谷パレス」。旬の食材を
使った複数のコース料理が用意されている。パーティーなどで
使えるランチタイム限定の貸切りプランもある。

木材を基調にした明るいカジュアルな店「日比谷グリーンサロン」。
店内にテラス席も完備。カレー、パスタ、中華丼、うどんとそばなど
和洋折衷のメニューを提供している。
2F、3Fは緑と水の市民カレッジになっている。

一般には「野音(やおん)」の名で親しまれている大音楽堂。
椅子席2664席、立見席450席、さまざまなアーティストの
コンサートに使われる。他に5月1日のメーデーや市民団体の
集会などよくニュースに出てくる。

日比谷図書文化館は明治41年開館と、古い歴史を誇る。
現在の建物は昭和32年10月3日に落成した。
特徴的な三角形の平面は土岐善磨の発案とされる。

日比谷図書文化館と日比谷公会堂の間にある一軒家レストラン、
「南部亭」。緑に囲まれた落ち着いた空間で、正統派の
フランス料理が楽しめる。昭和30年12月開店。
http://www.nambu-tei.com/

「花とみどりを通じて、真に豊かな社会づくりに貢献する」を
企業理念に、業界のリーディングカンパニーとして様々な
事業を展開する「日比谷花壇」。当社は明治4年(1872年)
葛飾区堀切で庭園業を始めた。昭和25年(1950年)
日比谷公園店を出店、12月に日比谷花壇設立した。今や売上高
213億円(2016年9月決算)従業員1500人を擁する業界の雄。


公園にはベンチがつきもの。第二花壇前にズラリ並んだ
ベンチの背もたれに小さなプレートを発見。よく見ると
思い出ベンチと称して、コメントを書いて寄付したみたいだ。
そういえば2015-7-18付のブログに掲載した井の頭恩賜公園
(小さな旅-10)にも思い出ベンチがあったのを思い出した。
何枚か読むとそれぞれの人生の思いが入ったものを
ベンチが背負っていると感じた。