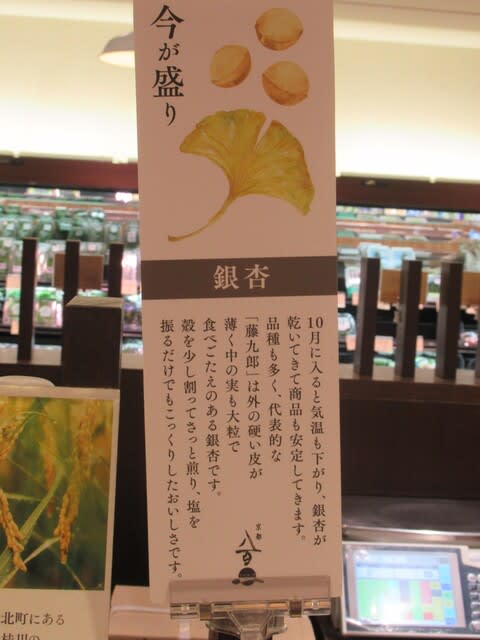関越自動車道、月夜野インターチェンジより車で約8分、
水上インターチェンジより約13分の所にある
ガラスのテーマパーク「月夜野びーどろパーク」がある。
ここは1903年(明治38年)に創業した上越クリスタル硝子(株)が経営している。
http://www.vidro-park.jp/

1960年代後半あたりから上越クリスタル硝子(株)工場脇に直営店を設営。
水上温泉郷への観光客が立ち寄るようになり、ドライブイン的な施設へ整えられていく。
これが現在の月夜野びーどろパークの前身となった。
現在は配置図に書かれているように
①ガラス成形工場 ②吹きガラス体験工房 ③ガラス体験工房
④クリスタルB館 ⑤クリスタルA館 ⑥グラスアート美術館
⑦クリスタル物産館 ⑧地ビールレストラン ⑨カフェ・ド・ヴェール
⑩ガラス原料の砂場 ⑪ファクトリーアウトレット など
「見る・体験・ショッピング・食べる」が楽しめるガラスのテーマパークになっている。

オリジナル作品から世界のガラスを集めた展示即売ショップのクリスタルA館。
ここには、ここでしか出会えないガラスがある。
また、この建物には古代2000年の昔のローマンガラスやアール・ヌーヴォー、
アール・デコ、ピカソデザインのガラスなど
国内外の著名な現代ガラス作家の作品を数多く展示している
グラスアート美術館もある。




1階のガラスショップには使う人の楽しさを考えて造られた
花瓶、グラス、食器など実用的アイテムの
オリジナルティあふれる製品を集めて展示即売している。
スミダマンは陶器や磁器などよりもガラス器の方が好きで
一通り見て歩いてワクワク感を感じてしまった。



特に目が止まってしまった工芸品的花瓶。
品の良い白ベースに金の飾りものが付いたものと
黒の細かい格子模様にやはり金の飾りものが付いた渋いもの。
お値段は税別で2万5,000円。
本気で衝動買いしそうになりました。
結局買いませんでしたけど。

1990年(平成2年)に開園したグラスアート美術館は2階にあり
美術工芸品を中心とした壺や置物が展示してある。



2階工芸サロンではガラス作品の販売や企画展・催事を開催している。
企画展は「月夜野工房のクラフト」・・・昭和から令和へ技の伝承


また、名工と色彩工芸硝子と題した常設展示は黄綬褒章や卓越技能章(現代の名工)を
受賞した職人(8名)の作品や個性的デザイナーの作品を展示販売している。
豊富なガラス色の組み合わせと高いガラス工芸技術を駆使した
色彩工芸硝子を見ることができる。


イタリア・チェコをはじめとするガラス先進国のコレクションを一堂に集めた
芸術的作品を無料で見学することができる。




ここからは「グラスアート美術館」(入館料550円)。
古代2000年前のローマングラスやアール・ヌーヴォー、ピカソデザインのガラスなど
国内外の著名ガラス作家の作品(3枚目:ミュラー兄弟、
4枚目:アール・ヌーヴォー期を代表するエミール・ガレ)。

これは4世紀頃、ケルン近郊のMUNGER SDORFで発見された色模様の盃。



これは私が大好きなフランスのルネ・ラリック(1860-1945)の作品。
東京白金にある東京都庭園美術館(旧朝香宮邸)の正面玄関にあるガラスリレーフ扉を思い出す。
ラリックのガラス工芸品は素材は乳白色で半透明のオパルセント・グラスを使い、
動物、女性像、花などのモチーフを好んで用いたデザインが特色だ。

ガラス成形工房、吹きガラス体験工房、ファクトリーアウトレットが入っている
上越クリスタル硝子の工場全景。
見学者は1年間で30万人も来るそうだ。
また、当社の製品は中尊寺(瑠璃色ガラスビーズ復元)来賓館赤坂離宮で
昭和43年から続いた改修工事で花弁型ホヤなど約70種、
数千点の照明用ガラスを復元製作。
国会議事堂(大正9年起工)や、皇居二重橋街路灯、正倉院宝復刻品など
多くの場所で照明器具に使われている。




パーク内にはガラスでできたオブジェがたくさんある。
かわいい動物たちや美味しそうなケーキやビール、
今にも動き出しそうなお魚、サンタクロースまで。
どこかにイモムシ君も隠れているらしい。
ここはインスタスポット。
インスタ映えするガラスのオブジェがたくさんある。









熱いガラスを自由にあやつる職人の技を目の当たりに見ることができる
「ガラス成形工房」。
灼熱のガラスを風船玉のように膨らまし、
オリジナルのグラスや一輪挿しなどが作れる吹きガラス「体験工房」。
全国一の手作りガラス工場で日本のトップクラスの職人の技を無料で見学することができた。


試作品や色違い、品寸法違いなどのアウトレット商品がたくさんある
掘り出し物コーナー「ファクトリーアウトレット」。
もしかしたら世界で1つだけのレアものがあるかも。


ガラス素材を使った様々な体験(サンドブラスト、絵付け、
ホットワーク、カラーサンドキャンドルなど)ができる「ガラス体験工房」。
そしてガラスでできたアクセサリーやかわいい人形、インテリア小物など、
目移りしちゃうものがいっぱいあるクリスタルB館。

地元の新鮮漬物をはじめ、みなかみ町ならではの特産品を
数多く取り揃えた「クリスタル物産館」。
旅のお土産を買うのにちょうど良い。


ガラス製の屋根のテラスで一息。
オリジナルグラス付きの地ビールをはじめ各種ドリンク・ソフトクリームなどが
用意されている「カフェ・ド・ヴェール」。





ランチはここの地ビールレストラン「ドブリーデン」でとることにした。
当店はチェコのブルワリーとの提携によるおいしい地ビールと
シェフ自慢のオリジナル料理を楽しめるという触れ込みだ。
コロナ感染防止の為のテーブルの仕切りはガラスプロの店としては素人っぽい
日曜大工的な木の仕切りで営業していて空気を壊した造りだ。


それに比べ天井の照明器具はさすがプロ。
ガラス製の同じ型、大きさで色違いというメルヘンチックなセンスの良さ。
テーブル上のコップ、ナプキン入れ等も他では見られない素敵なもの。
この落差がすごく気になってしまった。


メニューは幅広く、蕎麦、うどん、洋食があり、メニューを見てハッと気が付いたのが
「そうだ、この地は真田家の領地だ(沼田城が近い)。
だから真田六文銭なる、そば・うどんメニューがあるのか!」


通常メニュープラス今月のおすすめメニューが2種。
チキンのカツサンドとエビフライのカレーと、ちょっと一捻りしたメニューだ。
それから当然、地ビールの月夜野クラフトビール5種。
全体的雰囲気とは違いメニューをチェックすると何か期待してしまう。


ごはんにフライドポテトとおもちをトッピングしてチーズをたっぷりかけた
とろ~りアツアツの焼きカレー「ポテもちカリー」1,000円。
旨い、美味しい、グッド、ヴォーノ!
まさに期待に十二分に応えてくれた。
プラスそばピザというのも食べてみたかったナ~。