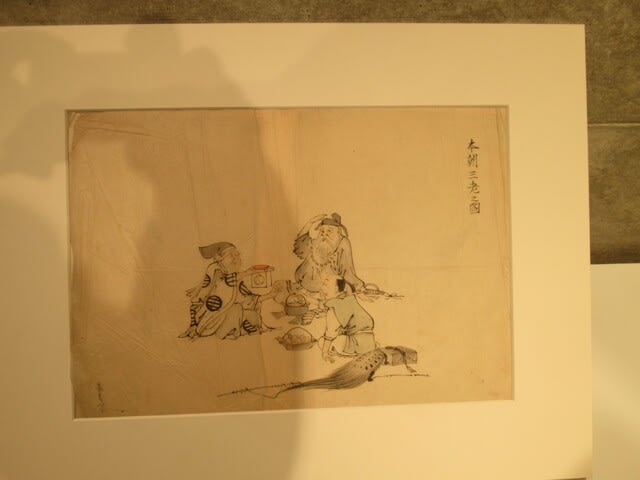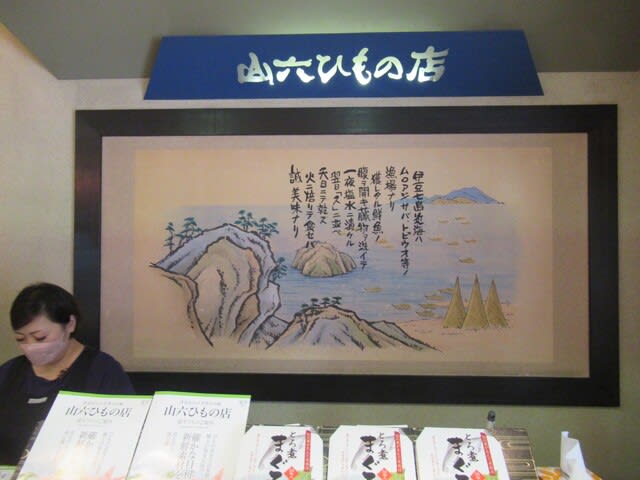鳩居堂京都本店は御池通に近いところの寺町通に面している。
この寺町通は豊臣秀吉による京都改造によって
通りの東側に寺院が集められたことから名付けられた。
当店は本能寺の隣りで、この通り付近には古美術店、画廊、古書店などが多くある。
https://kyukyodo.co.jp/shop/index.html


こちらが2020年11月28日に106年ぶりに建て替えられた鳩居堂の本店。
この鳩居堂の歴史がすごい。
1180年(治承4年)源頼朝が熊谷直実の軍事的活躍を称え「向かい鳩」の家紋を送った。
直実は1186年(文治2年)に平敦盛を討つなど活躍するが、
1193年(建久4年)に出家して法然の弟子となり「蓮生(れんせい)」と名乗った。
1663年(寛文3年)直実から数えて20代目の子孫を称する直心(じきしん)が
薬種商として現在の場所に店舗を用いて創業したのが始まり。



当店は創業357年の老舗。
関東の人は鳩居堂というとすぐ日本一地価の高い銀座鳩居堂を思い浮かべるが、
実は京都発祥の地ということだった。
今回のは建築的に素晴らしい建物だが、店舗のレイアウトや商品の配置を
できるだけ以前と同じようにして什器も6割以上
昔から使用しているものを修繕して使用している。
12代目の熊谷直久さん曰く「建物は新しくなったが、それに気づかないほど街に馴染み、
お客様や寺町通を通行される方から以前と変わらないねと言っていただけるのも嬉しいです」と。




当店はお香、書画用品、はがき、便箋、金封、和紙製品を中心に
2,000点以上の商品を取り扱っている。
さらに通年1万点以上の商品が登録されており、今回のリニューアルに伴い、
ディズニーとのコラボレーション商品など新商品も登場している。
4枚目の写真に写っている鬼瓦の紋様にあるのが「向かい鳩」の商標だ。

漢方薬や薬の原材料である薬種の輸入先である中国より、
書画用文具の輸入販売を始め寛政元年(1789年)頃から頼山陽や池大雅など
文人墨客の研究・製造が始まった。
筆が並ぶ商品棚の上に「筆研紙塁皆極精良」の文字は頼山陽揮毫のもので
「筆も硯も紙も墨も皆すばらしい」という意味だとか。


以前の店舗は1階のお店と2階が倉庫だったので今回の新しい店舗は
天井を高くして1階のみとし、天井から自然光を取り入れるトップライト、
壁面はガラス張りで明るく開放的な建物になっている。
実に京都らしく素敵で素晴らしいそのディテールにうっとりと浸ってしまうようだ。

また、ご覧のように壁、天井に細かく細工された木片が組み込まれ、
木特有の人の温もり優しさが伝わってくる。
照明器具もこれだけだと平凡だが、店内全体に配置されと、なんとも言えずお洒落になる。


今回の建て替えで新たに造られた中庭。
左奥に植えられたシンボルツリーは秋になると美しく紅葉するらしい。

帰りがけに目に付いたのがブリキに亜鉛メッキ(?)されたような樋と木建具のレール。
昔懐かしい素材だが、すごく新しさを感じ新鮮な意匠になっている。

本店の斜め向かい側にある営業店で、こちらも新しく建て替えられた。
ところでこの鳩居堂という屋号は、儒学者・室鳩巣が「詩経」の召南の篇にある
「維鵲有巣・居鳩居之」より採って命名したもので、
カササギの巣に托卵する鳩の様子から「店はお客様のもの」という
謙譲の心で経営すべきの意が込められた屋号であるという。

こちらの営業所の意匠も基本、本店と同じで寺町通を挟んで相乗効果を出している。
設計は千代田区九段南にある内藤廣建築設計事務所。
作品としては鳥羽市立海の博物館、旭川駅、
富山県美術館、とらや赤坂店などがある。


こちらのお店の約1/4くらいのスペースには喫茶コーナーがある。
白のテーブル、赤と黒の椅子、いわゆるレッズカラーのお洒落な空間が魅力的だ。
ここでは一保堂茶舗の冷たいほうじ茶と
フレンチレストランMotoiのマカロンカカオと木苺のマカロンが385円でいただける。




こちらの店舗は本店とは違い、気軽に聞香、香道体験ができ、
イベントコーナー的なエリアになっている。
鳩居堂が目標にしているのは、日本の伝統文化を守り伝え、育てていくこと。
お店にあるさまざまな商品を手に取り、体験することで、
その文化を少しでも知ってもらえたらと考えているとか。
素晴らしいコンセプトだ。


店舗のディスプレイ、展示の企画創造力も感心してしまうほど素晴らしいが、
スミダマンの仕事柄上、この建物の設計ポリシー、
そして具体的なディテールが本当にチャーミングで感心してしまう。
その参考に店内に展示されていた立面図、断面図、矩計図などアップしてみました。


その内装仕上げは本店と同じだが、こちらの店の空間の方が販売商品がないためか、
すっきりしていて建物の魅力が前面に押し出ているような印象だ。


ほれぼれする木造内装のディテールをお楽しみください。

これは久々に見た木造建築の傑作だ。
こちらのディテールは様々な木目の天井桟木と壁のなんともいえない味のある化粧石。
すごい設計だと見とれてしまった。

この営業店の裏側には鳩居堂と書かれた高い建物がある。
用途は何の建物かわからない。