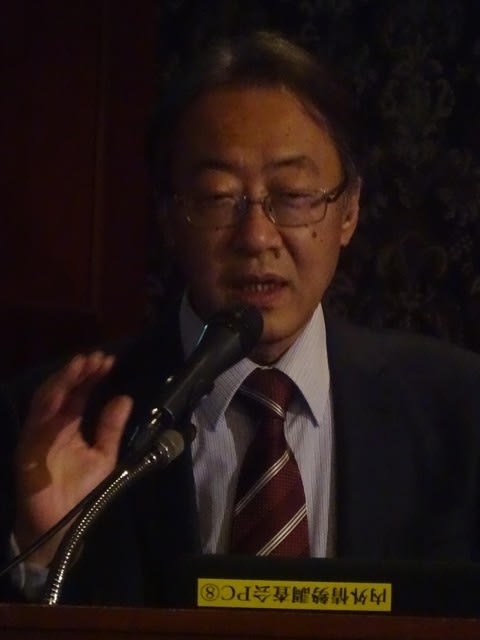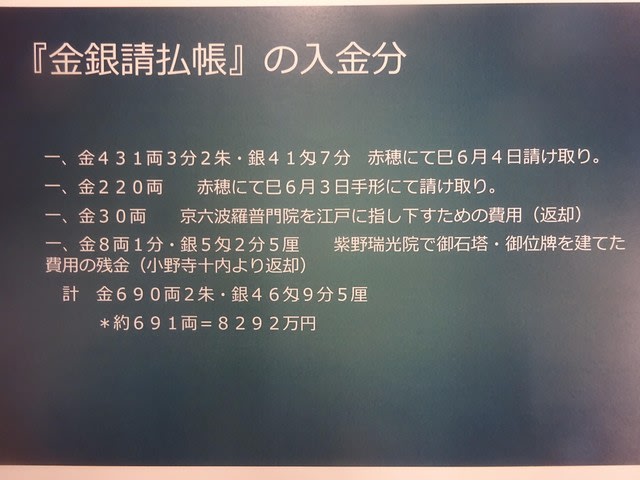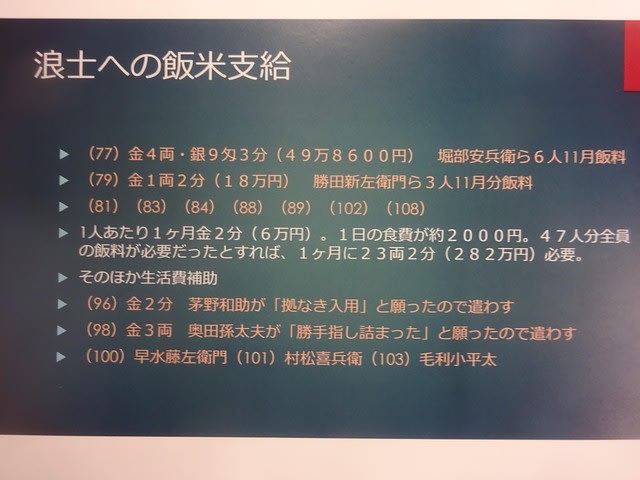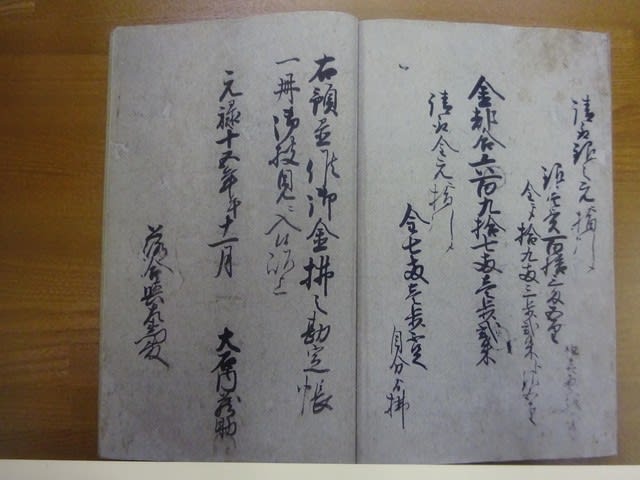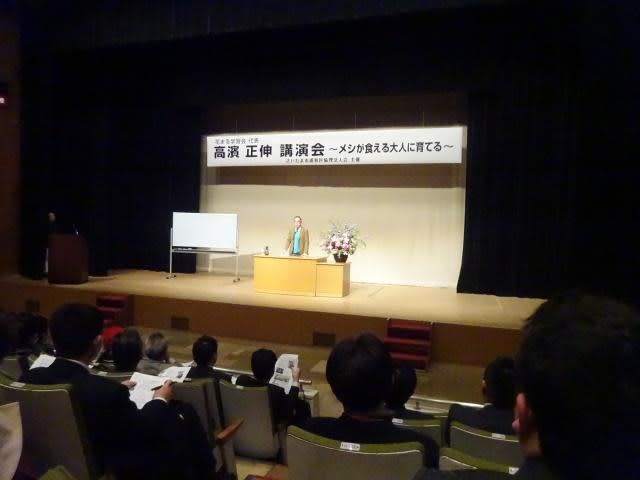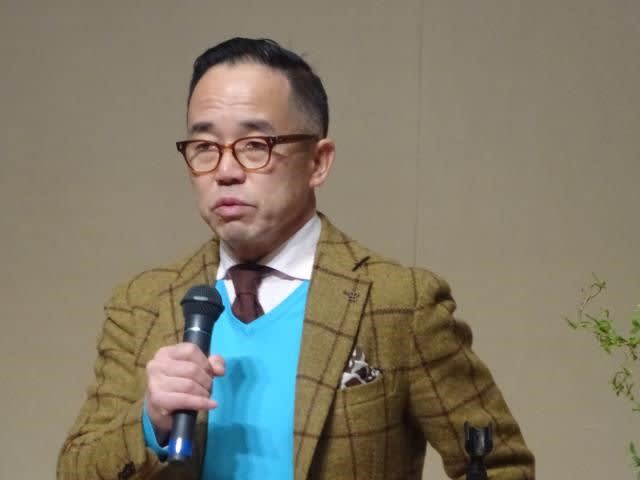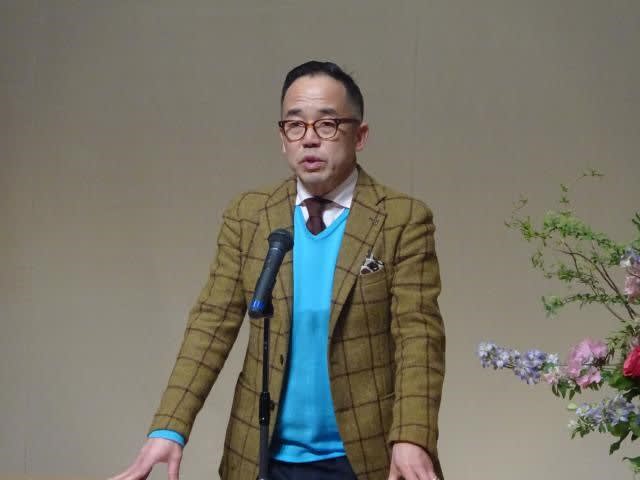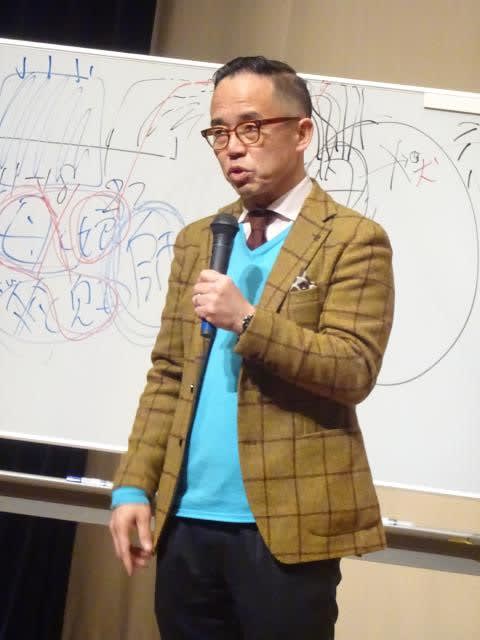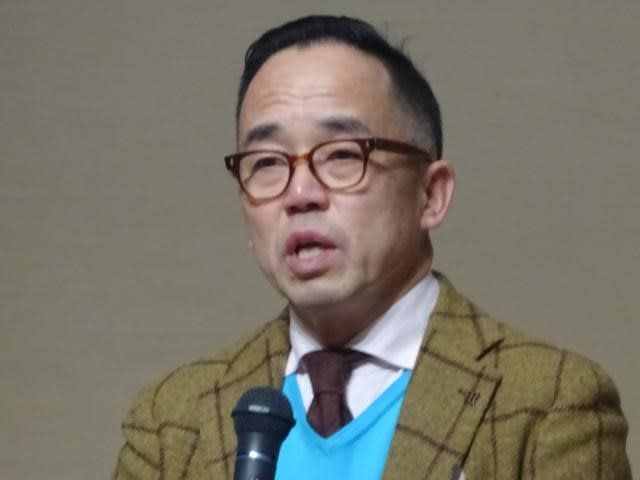塩田潮氏は1946年(昭和21年)生まれ、高知県出身。
70年、慶應義塾大学法学部政治学科卒業。
月刊「文藝春秋」記者などを経て、83年に独立してノンフィクション作家に。
同年「霞が関が震えた日」で第5回講談社ノンフィクション賞を受賞した。
この日の講演の演題は「2021年の菅政権の行方」です。
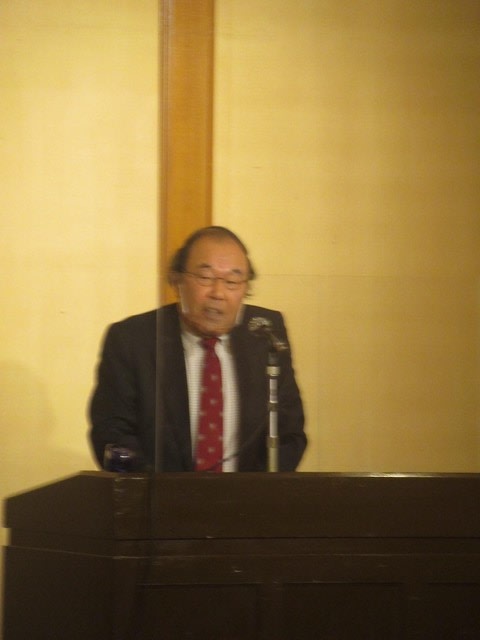
菅首相のイメージは臨時、代打、一年限定といったもの。
又、地味、女房役、華がないが失言が一回もなく、安定感・信頼感があり、
田中角栄以来のたたき上げという人気もあって歴史4位の高い支持率でスタートした。
しかし、菅流のやり方、考え方が国民に浸透しないと低迷内閣になるだろう。
一方、突然の辞意表明した安倍晋三総理は氏曰く、ヤル気をなくした、憲法改正はあきらめたと。
菅総理の素顔の特色は、秋田県出身で初、無派閥出身、又、戦後以降、
佐藤栄作、小渕恵三に続いてのノンアルコール首相、
海部俊樹以来の大都市選挙区(横浜)出身の首相とか。なるほど!
又、経歴については菅は東京には何かあるのではと秋田から出てきた。
法政大時代はノンポリ。しかし何もなかった。
選挙運動で感動、生きる道を見つけた。
法政時代に中村梅吉に相談して横浜出身の小此木彦三郎代議士を紹介受け秘書に。
その時代の一番うれしかったことは秘書になったこと。
辛かったことは秋田との訣別だなと。
その後、一年生議員時代に梶山静六から、
自分の思いを強く持って自己実現をすること、官僚には騙されるなと教わった。
2002年に自民党総務会で北朝鮮万景峰号の政策で安倍晋三と出会った。
2005年、総務副大臣の時、竹中平蔵大臣と一緒になり、
総務省内部全部は菅さんにお願いしますと言われ、原型が出来あがった。
すごい統率力と地頭の良さを発揮した。

菅は基本、構造改革路線。
外交・マクロ経済政策は安倍路線の継承。
ポイントポイントは人にヒアリングをし、お手本は小泉流。
菅と小泉は似ている所があり、究極の自由人、しがらみを嫌う。
小泉は1点突破で全面にだが菅は一部体質転換して全体体質へ。
過去に(2016年10月)北朝鮮のミサイル予告があった時、
防衛省はどうしても間に合わないと言ったのに対し菅はなんとしても間に合わせろとの指導力を発揮。
これが菅流の神髄だ。
菅の政策実行はミクロに切り込む。
安倍のアベノミクスはマクロでは成功したがミクロでうまくいかなかった。
それは霞ヶ関はミクロ政策の牙域で政治には触れさせたくない。
このタテ割りの日本型社会主義に菅は介入、切り込もうとしている。
政と官の攻防戦の中でミクロ政策だけで良いのか?新しい所得政策は?
マクロ政策については学識、知見が不足している。
広げる努力が必要などの課題がある。
又、菅の政治志向は国益に関しては一切妥協しない。
人事権を持ってコントロールする。
権力闘争では生き抜く、生き残るという生命力がすごい。
そして約束を守る、裏切らない、徹底して尽くす。
弱点としては国家観などのグランドデザインが見られない。
民意との結託を図る等がある。

野党に関しては新党合流してもブームは起きない。
なぜか?思惑が見抜かれている。
この合流は選挙互助会だからだ。
最大の懸念は55年体勢を崩した努力が水の泡になってしまうこと。
新しい55年体制は、理念、路線の明確な旗がある事。
日本の将来像を持っている人を得ること。
そして大きな仕掛け、提案能力、攻撃力の矢を持つことだ。