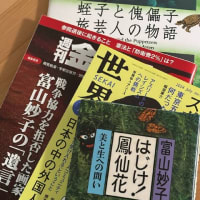ハノイへの行き帰りに、ナオミ・オレスケス+エリック・M・コンウェイ『世界を騙しつづける科学者たち』(上・下)(楽工社、原著2010年)を読む。
原題は『Merchants of Doubt』であるから、『懐疑論の商売人』とでもいったところ。邦題は、どのような科学者が「世界を騙す」のか曖昧になっており、直訳の方が良いものだったかもしれない。「懐疑論」とは、決して知的で正当な議論から出てくるものではなく、一部の権力にとって好ましくない事実に向けられたものであることが多く、また、歴史修正主義とも共通する面があることからも、そのような観点で視なければならない言説が多くなってきているからだ。

本書には、何人かのキーとなる(元)科学者たちが登場する。何人かは、原爆の開発に従事していた。かれらは冷戦の申し子であった。すなわち、アメリカ陣営・資本主義陣営を是とし、そのための軍事開発に賛成・参加し、ホワイトハウス、右派的な色がついたシンクタンク、利益を守りたい産業界の資金によって活動を行い続けた。かれらにとってみれば、環境保護とは「赤い根を持つ緑色」に他ならないのだった。
かれらのターゲットとしては、タバコの健康影響、酸性雨、オゾン層破壊、地球温暖化、化学物質の環境影響などが選ばれてきた。それぞれ、科学的な手続きによる成果の積み重ねによって、仮説から、対策を講じなければならぬ問題へと移り変わってきたテーマばかりである。ところが、懐疑論者たちは、その手続きと成果とを意図的にねじ曲げ、プロパガンダを繰り広げた。これが如何にデタラメかつ悪質なものであったかを、本書は、執拗なほどに検証している。
メディアが、科学的知見そのものにではなく、安っぽい人間ドラマや、争いといったものに飛びつくことは、日本でも欧米でも変わらない現象のようだ。懐疑論者は数としては圧倒的に少なく、また、言説も劣っているにも関わらず、「論争」が仕立て上げられることによって(たとえ非論理的な悪罵のたぐいであっても)、メディアは両者の主張を「バランス」を取って報道し、市民はそれを信じてしまう。まさに懐疑論者の自作自演のようなものだ。
残念ながら、この手法は科学だけではない分野でよく採用されている。たとえば、沖縄の「集団自決」を歴史修正主義者たちが攻撃したとき、この史実は、歴史教科書から、それが「両論ある」という理屈によって消し去ろうとされたことがあった。なお、「大江・岩波裁判」については、最高裁における歴史修正主義者の敗訴という形で決着が着いている。しかし、歴史修正主義者たちにとってみれば、騒動を起こすだけで「半分目的を果たした」のだった。
著者は、環境問題への懐疑論者はすなわちリバタリアンであり、資本主義の失敗を決して認めない者たちだとみなしているようだ。しかし、これには少々無理がありそうに思える。環境経済の手法は、負の外部性を経済に取り込もうとするものでもあるが、そのためか、そういったものに対する著者の評価はやや曖昧になっているように読める。たとえば、酸性化の原因となった硫黄酸化物・窒素酸化物を対象とした「キャップ・アンド・トレード」が、政策として成功であったのかどうかについては、本書では、揺れ動いて定まっていない。
アメリカにおける地球温暖化に対する懐疑論は、本書で示される文脈に沿って読まれるべきものだが(ノーム・チョムスキーもそのことを繰り返し指摘している)、日本においては、それが奇妙にねじれている。日本の温暖化政策が原子力推進とセットで進められてきたために、陰謀論好きな一部のリベラルたちによって、懐疑論が投げかけられてしまった。すなわち、日米の懐疑論者が右と左とに分かれてしまうという奇妙な現象である。もっとも、両者ともに非論理・非科学の沼にはまっていることは共通しているようだ。
膨大な取材と検証に基づく力作である。推薦。
●参照
ノーム・チョムスキー+ラリー・ポーク『複雑化する世界、単純化する欲望 核戦争と破滅に向かう環境世界』
ノーム・チョムスキー+ラレイ・ポーク『Nuclear War and Environmental Catastrophe』
ノーム・チョムスキー講演「資本主義的民主制の下で人類は生き残れるか」
ノーム・チョムスキー『アメリカを占拠せよ!』
ジェームズ・ラブロック『A Rough Ride to the Future』
多田隆治『気候変動を理学する』
米本昌平『地球変動のポリティクス 温暖化という脅威』
小嶋稔+是永淳+チン-ズウ・イン『地球進化概論』
『グリーン資本主義』、『グリーン・ニューディール』
吉田文和『グリーン・エコノミー』
ダニエル・ヤーギン『探求』