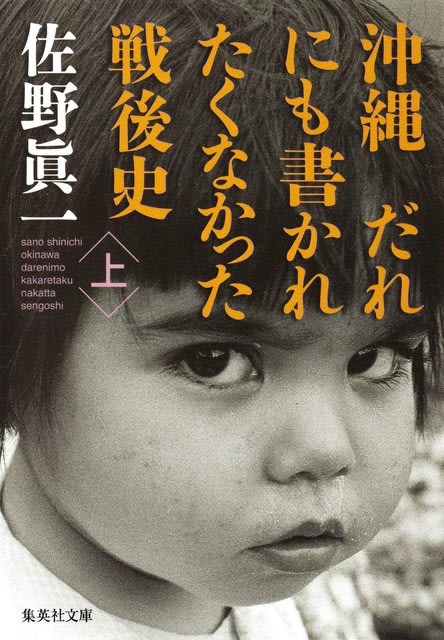桜木町の包丁処たち花(2020/5/24)。マスターがジャズ好きで何度もライヴを行っていたとのことだが、残念ながらこの日でお店をたたんでしまった。料理も雰囲気も最高で、もっと早く知っていればよかった。

Susumu Kongo 金剛督 (ts, fl)
Kaori Komura 香村かをり (チャンゴ、チン)
Kizan Daiyoshi 大由鬼山 (尺八)
驚いたのは金剛さんのテナーの柔軟さ。「アリラン」だけでなく香村さんの打楽器を意識してか韓国の音を出していた。香村さんの叩く強弱には惹きつけられるものがあり、また、即興ゆえかサウンドの連続性よりも多彩さを意識しているように思えた。大由さんの衝撃波には発せられるたびに驚かされた。
終わったあと、桜木町駅のこのへんが良いんだ、飲んで行こうとの金剛さんのお誘いもあり、香村さんと3人で太陽ホエール。愉しかった。



Fuji X-E2、7Artisans 12mmF2.8、XF60mmF2.4
●金剛督
Meg with Reed Dukes@武蔵境810 Outfit Cafe(2019年)
●大由鬼山
林ライガ vs. のなか悟空@なってるハウス(2017年)