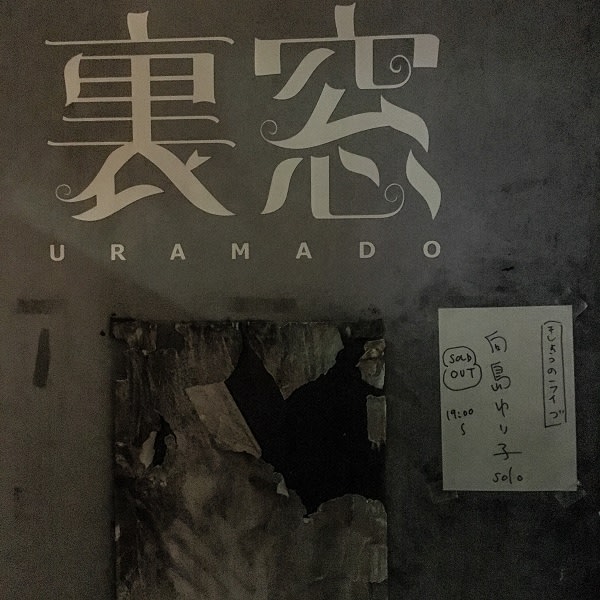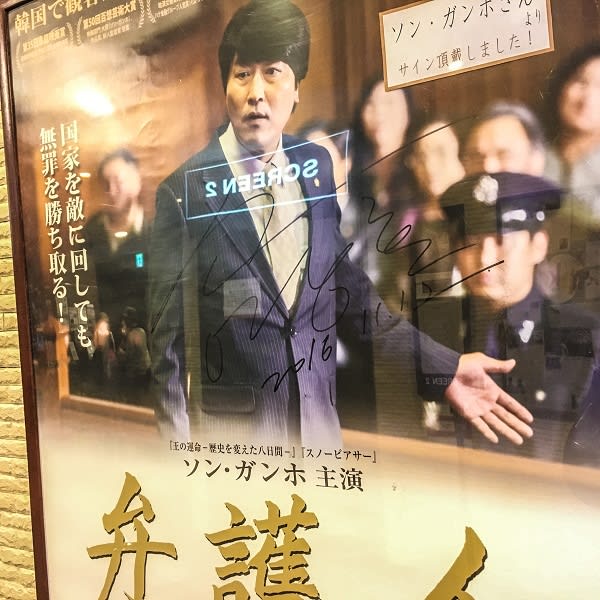福田克彦『映画作りとむらへの道』(1973年)を観る。小川プロのスタッフであった福田氏が、小川紳介『三里塚 辺田』(1973年)の制作現場を撮った1時間弱の記録映画である。

最初に、辺田の歴史や自然をとうとうと話すお爺さんを撮る場面がある。また、『辺田』には使われなかった場面のラッシュが挿入される。90日間も拘留されていた青年行動隊の20人が保釈されたことを、農民放送局が放送塔からアナウンスする夕方の場面であり、その間、カメラは動かない。実にいいフッテージのように思えるのだが、この使い方を巡って、炬燵に座って、小川プロの面々があれこれと議論している。「包める」場面は、カメラは変に動かさないほうがよい、村の人は東京の人と違って退屈しない、一方「包めない」お爺さんの話はアップでカメラも動かしたほうがよい、と。そうか、このような撮影や編集の模索があったのか。
小川プロ作品のように、手段や具体や技を見つめるものとして、撮影と録音の工夫を語る場面があって、これもまた面白い。カメラはエクレールの16ミリ、レンズはアリマウントのシュナイダー、録音は同録の定番ナグラ、マイクはAKG、そして水道管や煙突やクッションなんかを使って工夫し、撮影者が音を聴こえるように飛ばす仕組みもあった。
『辺田』の名場面のひとつは最後の女性たちによる念仏講だが、映画に採用されたものよりも和やかなところもある。途中で、お婆さんたちが福島民謡「相馬二遍返し」を歌っているように聴こえる(そのメロディに「相馬」とも聴こえるし、「ハア イッサイコレワイ パラットセ」という囃子もある)。これに関して、小川氏は、黒澤明『七人の侍』で使われた田植え唄の囃子と一緒だと発言している。『七人の侍』では多くの田植え唄を集めて選んで使ったはずだが、「相馬二遍返し」は田植え唄でもなく場所も違う。さて、どうだったのだろう。
議論で面白いことのもうひとつは、農村における「肝煎役」への注目だ。情報通で、商売上手で、調整ができて、しかし表には出てこない人たち。ここではそういった人たちを、本当の「ヒーロー」だとする。この発想が、のちの『1000年刻みの日時計-牧野村物語』における百姓一揆の場面にも入っているのかもしれない。
映画の最後は、映画の資金作りの苦労について、変に朗らかに描いている。実際にはいろいろなことがあったはずで、当時も今もこれを観て愉快には思えない人たちが少なくないのではないかと思うがどうか。
●参照
小川紳介『1000年刻みの日時計-牧野村物語』(1986年)
小川紳介『牧野物語・峠』、『ニッポン国古屋敷村』(1977、82年)
小川紳介『三里塚 五月の空 里のかよい路』(1977年)
小川紳介『三里塚 辺田』(1973年)
小川紳介『三里塚 岩山に鉄塔が出来た』(1972年)
小川紳介『三里塚 第二砦の人々』(1971年)
小川紳介『三里塚 第三次強制測量阻止闘争』(1970年)
小川紳介『日本解放戦線 三里塚』(1970年)
小川紳介『日本解放戦線 三里塚の夏』(1968年)
『neoneo』の原発と小川紳介特集
大津幸四郎・代島治彦『三里塚に生きる』(2014年)
萩原進『農地収奪を阻む―三里塚農民怒りの43年』(2008年)
鎌田慧『抵抗する自由』 成田・三里塚のいま(2007年)
鎌田慧『ルポ 戦後日本 50年の現場』(1995年)
宇沢弘文『「成田」とは何か』(1992年)
前田俊彦編著『ええじゃないかドブロク』(1986年)
三留理男『大木よね 三里塚の婆の記憶』(1974年)