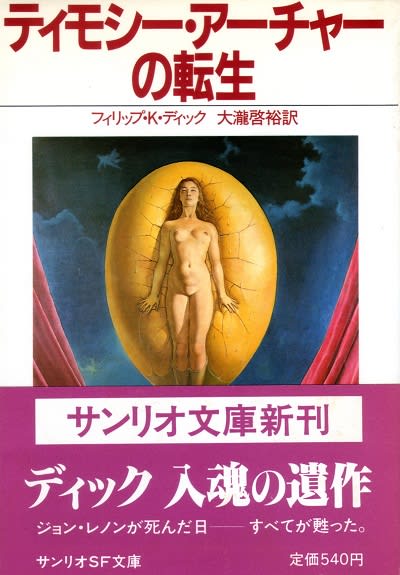鎌田遵『ネイティブ・アメリカン ― 先住民社会の現在』(岩波新書、2009年)を読む。

言うまでもないことだが、アメリカは白人による侵略によって拓かれた地である。「発見」以前から住んでいた先住民は一様ではなく、有名なチェロキー、ナバホ、ホピ、アパッチなど多くの部族がいた(いる)。先住民の部族数は500以上、先住民の血を引く人の数は412万人(2000年)とされるが、これは正確な数字ではない。申告や承認に基づくものであり、漏れも未承認もあるからだ。
アメリカ連邦政府は、19世紀後半から部族員の規定を活発化させ、その結果、先住民の土地や権利は著しく奪われる結果となった。現在では、内務省のインディアン局が先住民の担当部局であり、各部族の居住地(国内に約320)を認め、また、概ね民事の司法権は部族政府に帰属する。しかし、当然ながら、過去の不正により奪われたものは戻っていない。
どうしても、収奪政策と同化政策の様子を、琉球/沖縄など日本の先住民問題と関連づけながら読んでしまう。
●アパッチ族出身のジェロニモは、対白人抵抗闘争が制圧されたあと、最後の居場所を万国博覧会の展示会場に見つけ、自らを見世物とした(1898年、1901年)。この博覧会にはアイヌ民族も「招待」され、好奇の視線に晒された。
→ 大阪での「人類館事件」は1903年であり、ここでも、琉球人やアイヌ人が「展示」された。
●1920-30年代、先住民に対する同化政策が苛烈なものとなった。本名を捨てるよう命じられ、母語を話すと、口のなかに洗剤を入れられ、「悪魔の言語を吐く口」を洗われた。
→ 自発的な改名、方言札
●先住民居留地は貧困で雇用機会がなく、そのことが、米軍への入隊者の多さとなってあらわれた。その流れは、朝鮮戦争、ベトナム戦争、湾岸戦争、イラク戦争へと継承され、先住民の帰還兵数は17万人にも及んだ。また、18歳以上の先住民人口の22%もが帰還兵である(2006年)。
→ 貧困層の入隊
●アメリカのウラン鉱山の9割が先住民居留地やその周辺にある。核実験の場所も同様。
→ 辺境の再生産
●先住民でもないのに、あたかも先住民であるかのように振る舞う人=「ワナビー」が出現した。
→ 願望としての沖縄
もちろんすべてが写し絵になるわけではなく、単純な比較はできない。しかし、少なくとも、先住民を認め、国家のなかで共生していこうとする動きに関して、日本はあまりにも鈍感であり、遅れているということはできる。
●参照
国立アメリカ・インディアン博物館