
(財)海音寺潮五郎記念館は、昨年暮れをもって解散しましたが、
最後の事業として取り組んでいた「海音寺潮五郎 未刊作品集」がようやく出来上がり、
これをもって、財団としてのすべてが終了いたしました。
この未刊作品集に収められている作品は、戦前、戦後まもなくの作品で、
雑誌、新聞などに発表されながら、書籍として刊行されていないものです。
記念館では、発表されたことが分かっていながら、原稿、切抜きがないため内容不明な作品を、
国会図書館や日本近代文学館などで調べて集めてきました。
ついに見つけられなかったものもあります。
本人が生前あえて刊行しなかった作品ですから、本人にとって不本意な作品もあるとは思いますが、
色々な雑誌に何度も再録されている、興味深い作品もあります。
これらの作品は、一般にはまず読むことが出来ません。
そこで、海音寺潮五郎を多くの方に、少しでも知っていただくために、活字として遺すことを、
記念館最後の事業としたわけです。
第1巻:
「仇討ごよみ」
「ままならず」
「空腹武士道」
「薩摩の月」
「慈善」
「蟻の塔」
「大唐一代男」
「運命の川」
「大島逸平」
「牢獄の英雄(大島逸平)」
「いつか夜は明ける」 |
第2巻:
「関の扉」
「火術伝来記」
「白雲の上」
「血にぬれた悲恋」
「霽れゆく霧」
「御醍院父子-薩南の恋」
「秋風道」
「めぐり逢い」
「三日月小僧」
「さんざ時雨」
「鳥も通わぬ」
「豪勇一代」 |
第3巻:
「いなずま」
「江戸のたそがれ」
「金(かね)」
「大義の道」
「日薩草子」
「浪人と花簪」
「薩摩士道記」
「因州ばなし」
「旗本愛怨記」
「生きる道」
「天に沖す」 |
第4巻:
「桐野利秋・第一部」
「桐野利秋・第二部」 |
市販はされていませんが、寄贈先の図書館で読むことが出来ます。
寄贈先のリストはブログ 海音寺潮五郎応援サイト~塵壺(ちりつぼ)~の次の記事に掲載されています。
興味のある方は、ぜひ問い合わせてみて下さい。
 「海音寺潮五郎 未刊作品集」
「海音寺潮五郎 未刊作品集」













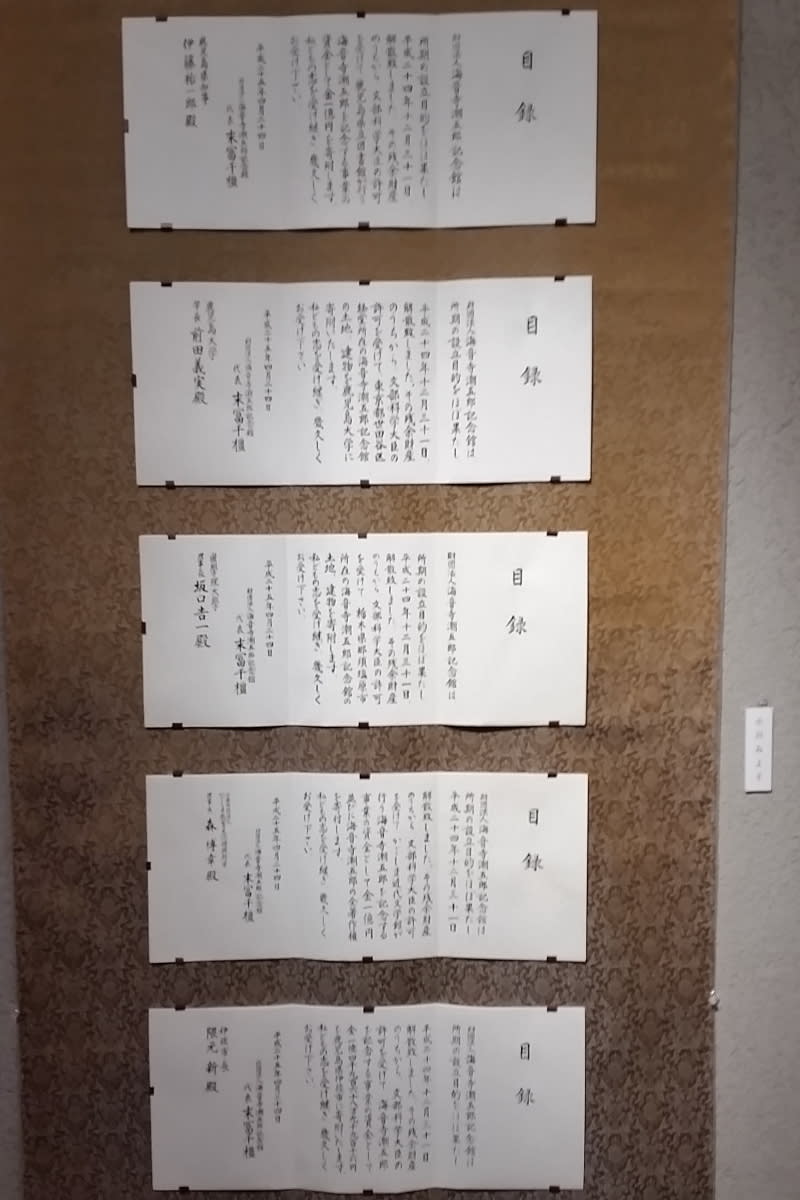








 「
「
 クリック大画像
クリック大画像











 >
>




























