昨年9月にブログをはじめてから、いろいろな変遷を経て、
今では、5つのブログと2つのSNSに加入して、毎日これに関わっている時間は延べ3時間余りにはなるだろう。
日常生活の一部として溶け込んでいる。
毎日、沢山の方に訪れて頂いている。特にアクセス数に拘っている訳ではないが、やはり気にはなるので、スタート以来アクセス数やPV数の管理はしてきた。
このようなことをするのもインターネットは簡単で計算機能もあるし、ただ数字をインプットするだけでいい。
SNSは除いて、5つのブログだけでアクセスの人数が延べ100,000人を記録した。
個人にとって見れば夢のような数値である。PVでいえば、300,000PV前後であると思う。
最初から、主力でやっているgooが当然多くて、gooだけで10月末現在、85、347人のアクセスで244、082PVである。
あと2ヶ月で、goo単独でも100,000人を越えるだろう。
延べ、10万人であるが、実際何人の方なのかははっきりしないが、1000人は間違いなく越えていると思う。
顔が解からないと言えばその通りであるが、
大体、どのような方なのか想像できる。URLのチェックで特定も出来る。
何十人かの方とは、直接お会いできたし、ブログを始めたお陰で再会できた方もいる。
三木市の議員さん方とはブログのお陰で、お会いも出来たし話も出来た。
武雄市長の樋渡さんともお会いできたし、三木と武雄が繋がったりした。
MFJのふれあいミーテングにも出席できた。
今月も三木のアネックスパークであるON ANY SANDA では元全日本チャンピオンのライダーたちが走ったりするきっかけもブログからである。
ひょっとして、三木に蛍の名所が来年の夏に出来たとしたら、これはブログのコメントからである。
最近、お付き合いの出来た「村ぶろ」や「ひょこむ」もIT関連である。
今後、この分野もいろいろと具体的に面白い具体的な展開になるものと思っている。
何故、こんなことを書いてきたかと言うと、
三木市のホームページに藪本市長が書かれている、「ブログを止める理由が」
理解できる部分もあるのだが、どうも納得できないからである。
一番気になったのは、 「現場主義」 という言葉である。
どのような場所や、状況のことを現場と言っておられるのか?
市長や職員と直接顔を合わし膝を交えて話せる人たちだけが対象なのか?
そういう意味では、85000人の市民は殆ど顔は見えないし対象外になってしまうのである。
顔の見えないブログでは、何も実現しないようにも取れるのである。
世の中の流れの先端を走っているブログやSNSを、市民や世の中をリードする立場にある行政の長が、否定するようなことがあってはならないと思うからである。
その運用については、個人個人の意志ややり方があって当然であるが、
このようなシステムは、今後の地方行政などの主流になるべき流れだと思っている。
顔をあわせて、膝を交えて話をする、そのやり方の良さは認めるが、
如何にもそれは数が限られる、延べ10万人に個人で会おうおうと思ったら、一生かかっても不可能だろう。
少なくとも私は 「何かを具体的にするために」 毎日ブログやSNSに3時間も時間を割いているのである。 そこに私流で言えば 「現場」 が存在するからである。
若しそうでなければ、こんなに一生懸命やったりはしないと思う。
今では、5つのブログと2つのSNSに加入して、毎日これに関わっている時間は延べ3時間余りにはなるだろう。
日常生活の一部として溶け込んでいる。
毎日、沢山の方に訪れて頂いている。特にアクセス数に拘っている訳ではないが、やはり気にはなるので、スタート以来アクセス数やPV数の管理はしてきた。
このようなことをするのもインターネットは簡単で計算機能もあるし、ただ数字をインプットするだけでいい。
SNSは除いて、5つのブログだけでアクセスの人数が延べ100,000人を記録した。
個人にとって見れば夢のような数値である。PVでいえば、300,000PV前後であると思う。
最初から、主力でやっているgooが当然多くて、gooだけで10月末現在、85、347人のアクセスで244、082PVである。
あと2ヶ月で、goo単独でも100,000人を越えるだろう。
延べ、10万人であるが、実際何人の方なのかははっきりしないが、1000人は間違いなく越えていると思う。
顔が解からないと言えばその通りであるが、
大体、どのような方なのか想像できる。URLのチェックで特定も出来る。
何十人かの方とは、直接お会いできたし、ブログを始めたお陰で再会できた方もいる。
三木市の議員さん方とはブログのお陰で、お会いも出来たし話も出来た。
武雄市長の樋渡さんともお会いできたし、三木と武雄が繋がったりした。
MFJのふれあいミーテングにも出席できた。
今月も三木のアネックスパークであるON ANY SANDA では元全日本チャンピオンのライダーたちが走ったりするきっかけもブログからである。
ひょっとして、三木に蛍の名所が来年の夏に出来たとしたら、これはブログのコメントからである。
最近、お付き合いの出来た「村ぶろ」や「ひょこむ」もIT関連である。
今後、この分野もいろいろと具体的に面白い具体的な展開になるものと思っている。
何故、こんなことを書いてきたかと言うと、
三木市のホームページに藪本市長が書かれている、「ブログを止める理由が」
理解できる部分もあるのだが、どうも納得できないからである。
一番気になったのは、 「現場主義」 という言葉である。
どのような場所や、状況のことを現場と言っておられるのか?
市長や職員と直接顔を合わし膝を交えて話せる人たちだけが対象なのか?
そういう意味では、85000人の市民は殆ど顔は見えないし対象外になってしまうのである。
顔の見えないブログでは、何も実現しないようにも取れるのである。
世の中の流れの先端を走っているブログやSNSを、市民や世の中をリードする立場にある行政の長が、否定するようなことがあってはならないと思うからである。
その運用については、個人個人の意志ややり方があって当然であるが、
このようなシステムは、今後の地方行政などの主流になるべき流れだと思っている。
顔をあわせて、膝を交えて話をする、そのやり方の良さは認めるが、
如何にもそれは数が限られる、延べ10万人に個人で会おうおうと思ったら、一生かかっても不可能だろう。
少なくとも私は 「何かを具体的にするために」 毎日ブログやSNSに3時間も時間を割いているのである。 そこに私流で言えば 「現場」 が存在するからである。
若しそうでなければ、こんなに一生懸命やったりはしないと思う。










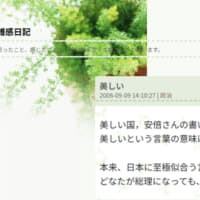


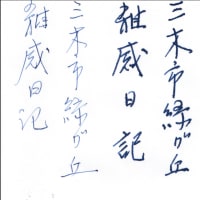






現場、現物を良く見ること。
しかし、バーチャルな世界が効率を上げるとも。
世界のトヨタは先頭きってバーチャル開発に走り、
品質低下から、現物を大事にする様見直したそうです。
どちらも否定できませんが偏らないことだと思います。
ブログで交流、できるだけ会う。古谷さんの姿勢は正しいのでは・・・
いろんな新しいシステムは、その効用があるが故に存在するのだと思っています。
機能しないシステムは自然に消えて行きます。
常に物事の本質、末端を見る目が必要と思います。
それがある意味現場なのですが、従来のタテ型思想でいう現場は、そうでない場合も多いのはいろんな事例で明らかです。
現場だ、末端だと思っていたものが、汚職の根源であったりしました。
タテ型でない、ヨコ一線の世界では、当然反対意見も出てきます。
出来る限り、広い範囲の意見を収集することが必要だと思います。
ともすれば、耳障りのよい言葉の方向にばかり流れるのは危険であると思っています。
止める理由に挙げられているような懸念は、最初からわかっていたと思います。
それともそんなことは、想定していなかった、される前に議論されていなかったということなのでしょうか?
樋渡市長は基本的にコメントには答えないというスタンスを示された上で、ひたすら武雄市のいいところを情報発信するツールとして利用されているように感じます。全国最年少の三条市長のブログでは、まだ慣れないので、トラックバック機能、コメント機能は付けておりませんと表題に掲げておられます。
本人がブログをどのよう使うのかということを割り切って考えれば、それでいいのではないかと思います。
それとも、使い方だけの問題として割り切れるほど簡単に考えてはいけないことなのでしょうか?
PS
私も、shinさんの意見に賛成です。
それと、どうせなら、この際、更新されていないほかのブログも整理されたほうがスッキリするんじゃないかと思ったりしますが???
要は、コンセプトが明確でないままに事を進めるとこうなることが多いのですが、
三木市での経緯を何となく知っていますので、
ブログについては、はじめられる以前からそのような懸念に関しては、市長ご自身が指摘されていました。
従って、その点については私も解かるのですが、
ブログ、とかSNSという仕組み自体と「現場主義」とを対比する形で、「止める理由」になさるのは、どうも納得がいきません。
現場主義というのも、具体的に今の三木市政のどの部分のどのような対応を指しておられるのか、
その辺りが、今後の課題になると思っています。