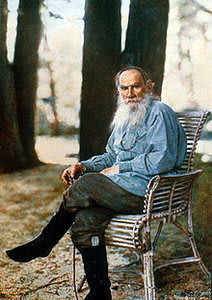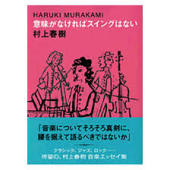以前当ブログでも記したように≪回忌法要≫も七回忌以降は寺院の経済基盤が成り立たなくなるとの理由で
作られたものとの説もあり、日本文化のかなりの部分にいわゆるフォールスメモリー(偽の記憶)が我々の
生活の中に埋め込まれていることが往々にしてあるという。
先日もテレビで話題の 『ぶっちゃけ寺』 という番組の中で、ある仏教僧が≪厄年≫についても江戸時代に
≪語呂合わせ≫ で作られたものだとも語っていた。
例えば厄年の33歳は「散々」から・・などと。 じゃ19歳はとの質問には 『 ん~? 』
だいたいこんなものなのか。 それじゃ信じるものも救われないではないかと思ってしまう。
まぁ そんな屁理屈ばかり言ってもだめだ。
ただ ≪偽の記憶≫ ≪妄想≫というもので我々人間の 文化や 伝統や 風俗が作られてきた面もある
ということは一理あり、そろそろ見直すことも必要ではないか、と私なぞは思ってしまうのですが ・・・。

かの大乗仏典もそのほとんどが≪偽経≫であるという苫米地英人氏なる人もいて、あの有名な『般若心経』
というお経も中国で書かれた≪偽経≫の一つだという。
未だ修行者である観自在菩薩が、釈迦の直弟子である悟った人、すなわち仏陀であるサーリブッダ尊者に対して
教えを説いている・・・というとんでもない形態に成っていると指摘。
舎利弗に舎利子というようにサーリブッダ尊者を卑下しているとも。
それに加え、釈迦は呪文や呪術的なものを禁止していたにも拘らず、『般若心経』自体が呪術的な(マントラ的な)
形態となっているのもおかしい・・・というのだ。
浅野典夫という人の書いた『ものがたり宗教史』という本にもこんな記載があった。
大乗仏典に書かれた教えは全て偉大で ≪仏陀以外にはこのような素晴らしい言葉を述べられるはずがない≫
という理屈を展開して中国から伝えられたようだと。
『般若心経』 『維摩経』 『法華経』 『無量寿経』などのお経の出自も皆このようなものだそうだ。
そうは言っても 自らの命を削って書いた僧たちに、偽経 偽経 と言ってはバチが当たる。
疑うことばかりしていると どうも 入っていけない 自分になるようだ。
当ブログ(般若心経雑感)
作られたものとの説もあり、日本文化のかなりの部分にいわゆるフォールスメモリー(偽の記憶)が我々の
生活の中に埋め込まれていることが往々にしてあるという。
先日もテレビで話題の 『ぶっちゃけ寺』 という番組の中で、ある仏教僧が≪厄年≫についても江戸時代に
≪語呂合わせ≫ で作られたものだとも語っていた。
例えば厄年の33歳は「散々」から・・などと。 じゃ19歳はとの質問には 『 ん~? 』
だいたいこんなものなのか。 それじゃ信じるものも救われないではないかと思ってしまう。
まぁ そんな屁理屈ばかり言ってもだめだ。
ただ ≪偽の記憶≫ ≪妄想≫というもので我々人間の 文化や 伝統や 風俗が作られてきた面もある
ということは一理あり、そろそろ見直すことも必要ではないか、と私なぞは思ってしまうのですが ・・・。

かの大乗仏典もそのほとんどが≪偽経≫であるという苫米地英人氏なる人もいて、あの有名な『般若心経』
というお経も中国で書かれた≪偽経≫の一つだという。
未だ修行者である観自在菩薩が、釈迦の直弟子である悟った人、すなわち仏陀であるサーリブッダ尊者に対して
教えを説いている・・・というとんでもない形態に成っていると指摘。
舎利弗に舎利子というようにサーリブッダ尊者を卑下しているとも。
それに加え、釈迦は呪文や呪術的なものを禁止していたにも拘らず、『般若心経』自体が呪術的な(マントラ的な)
形態となっているのもおかしい・・・というのだ。
浅野典夫という人の書いた『ものがたり宗教史』という本にもこんな記載があった。
大乗仏典に書かれた教えは全て偉大で ≪仏陀以外にはこのような素晴らしい言葉を述べられるはずがない≫
という理屈を展開して中国から伝えられたようだと。
『般若心経』 『維摩経』 『法華経』 『無量寿経』などのお経の出自も皆このようなものだそうだ。
そうは言っても 自らの命を削って書いた僧たちに、偽経 偽経 と言ってはバチが当たる。
疑うことばかりしていると どうも 入っていけない 自分になるようだ。
当ブログ(般若心経雑感)