この本、自伝的食のエッセイ本だが、なかなか面白い。 作家・阿川弘之、ご存じ佐和子の父である。
私も美味な料理教本やエッセイ本は好んで読んできたような気がします。
最初に感動したのは、檀一雄 『壇流クッキング』 でした。 いっぺんに檀さんのファンになり 『美味放浪記』や
『わが百味真髄』 など、立て続けに夢中で読んだものである。
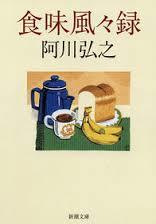

ある目次での笑える美味な話を紹介しよう。 料理名は ≪ひじきの二度めし≫
作家・向田邦子さんが飛行機事故で亡くなった3ヶ月前、雑誌で美味対談した席上のことのようだ。
向田さんが 『食事中いいですか』 と婉曲にそう断って置いて、その<ひじき>の話を始めたという。
『 ひじきは食べても殆ど消化されず、ちょっとふくらんだかたちで体外へ出てきます。
それを集めて、洗ってもう一度煮たのが ≪ひじきの二度めし≫ 最高に美味しいのだそうですよ。
昔 海べで暮らしている貧しい人達にとって、ひじきは大事な食べ物だったのでしょう。
ただで手に入るし、おなかは充分くちくなるし、しかも二度使えて、二度目の方が味が良いのですって。』
これ あの淑女たる向田邦子さんの話ですよ。 流石です。
著者・阿川弘之さんも、
『 微生物が体内でどう関わっているかは解らないが、哺乳動物の腸内を未消化のまま
通過した物質は、食品として絶品になるらしいことはおそらく本当なのだろう。』
そう語ってはいたが、勇気が無いため実行に移せなかったという。 くそっ !
『 黙って食わせてもらわないと ちょっと勇気ないなあ 』 と言ったとか言わなかったとか。
今日は随分と含蓄・品格のある話にまとまったようです。 食前であったなら失礼しました。
私も美味な料理教本やエッセイ本は好んで読んできたような気がします。
最初に感動したのは、檀一雄 『壇流クッキング』 でした。 いっぺんに檀さんのファンになり 『美味放浪記』や
『わが百味真髄』 など、立て続けに夢中で読んだものである。
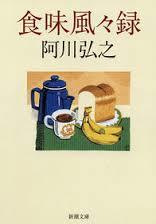

ある目次での笑える美味な話を紹介しよう。 料理名は ≪ひじきの二度めし≫
作家・向田邦子さんが飛行機事故で亡くなった3ヶ月前、雑誌で美味対談した席上のことのようだ。
向田さんが 『食事中いいですか』 と婉曲にそう断って置いて、その<ひじき>の話を始めたという。
『 ひじきは食べても殆ど消化されず、ちょっとふくらんだかたちで体外へ出てきます。
それを集めて、洗ってもう一度煮たのが ≪ひじきの二度めし≫ 最高に美味しいのだそうですよ。
昔 海べで暮らしている貧しい人達にとって、ひじきは大事な食べ物だったのでしょう。
ただで手に入るし、おなかは充分くちくなるし、しかも二度使えて、二度目の方が味が良いのですって。』
これ あの淑女たる向田邦子さんの話ですよ。 流石です。
著者・阿川弘之さんも、
『 微生物が体内でどう関わっているかは解らないが、哺乳動物の腸内を未消化のまま
通過した物質は、食品として絶品になるらしいことはおそらく本当なのだろう。』
そう語ってはいたが、勇気が無いため実行に移せなかったという。 くそっ !
『 黙って食わせてもらわないと ちょっと勇気ないなあ 』 と言ったとか言わなかったとか。
今日は随分と含蓄・品格のある話にまとまったようです。 食前であったなら失礼しました。













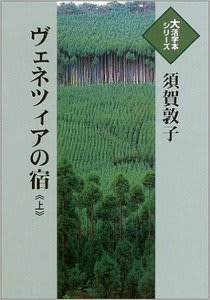
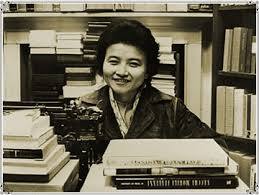

 南シナ海・九段線 海洋仲裁裁判所(オランダ・ハーグ)
南シナ海・九段線 海洋仲裁裁判所(オランダ・ハーグ) 











