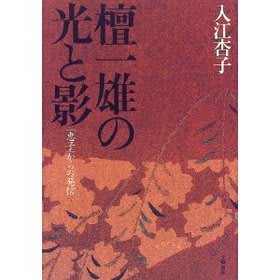≪イコン≫とは ギリシャ語で形とか像という意味。 正教会での宗教絵画・板絵である。
川又一英著 『甦るイコン』という本を手にとり、副題に「ロシアを映し出す鏡」とあったので読んでみた。
イコンを通して捉えた現代ロシアの心と原風景が描かれている。 どう考えてもロシアは深淵だ。
無神論を掲げる共産党政権により教会そのものが否定され、地下に眠っていたイコン。
ペレストロイカによる崩壊をきっかけに甦りつつあるという。
 著者はこういう。 『イコンは路傍の地蔵のようなものだ』、、と。
著者はこういう。 『イコンは路傍の地蔵のようなものだ』、、と。
イコンはルネッサンス絵画に始まる西欧近代美術とはまったく異なるという。
絵画ではあるが署名は加えない。 平面画法で描かれており西欧的な三次元表現を拒み続ける。
ロシアのなかには常に西欧コンプレックスとの相剋劇の歴史があるようだ。
(西欧は国家と教会が覇を競い合い、カトリックとプロテスタントを経て政教分離へと進んでいった歴史。
一方のロシア正教会はというと、ピョートル大帝に始まった西欧文明の移入までは、国家と教会の調和の伝統
を保ち続けていた歴史があった)
『西欧カトリック教会とロシア正教会の違いを把握しない限り、19世紀のアラブ派論客ドストエフスキーが唱えた反カトリシズム
・反西欧は理解できない』、、ともいう。
暗黒の時代、スターリンは西ウクライナをロシア化する為にウクライナカトリックをロシア正教会に組み込ませた。
当然ローマ教皇は当然認めず。その後ペレストロイカ時代を迎え、当時のゴルバチョフはヴァチカンと和解したが、今度はロシア教会が反発。
今 ウクライナをめぐってロシアと西欧がまさに覇権争いをしている。
経済や軍事もですが、その根っこにはこのような宗教をめぐっての深淵な歴史もあったようです。
今回この『甦るイコン』という本を図書館で探し読んだのですが、冒頭から読んでいたら口絵①と口絵②それに口絵③の説明記述はあったのですが、いくら探してもその口絵①②③が無いのです。
よく見たらその口絵が三つ共抜き取られ、④の口絵から始まっていたのです。
(きれいに④から合せた後遺あり)
先日図書館で『アンネの日記』が破られていた事件を思い出しましたが、こんなことってあるんですね。
(下図・抜き取られていた三つのイコンはインターネットより抜粋)



 ハンス・ホルバイン
ハンス・ホルバイン『キリストの遺骸』 ・
グリューネヴァルト『イーゼンハイム祭壇画』 ・
聖使徒ルカ 『ウラジーミルの生神女』
『キリストの遺骸』
屍が横たわり、あばら骨の浮き出表情を失いとても救世主とは思えない。
あのドストエフスキーに「人によってはあの絵のために信仰を失うかもしれない」と言わしめた。
『イーゼンハイム祭壇画』(観音開きの扉の構成)
このキリストも同様に全身死斑で覆われた凄惨な姿で描かれている。
『ウラジーミルの生神女』
右手に幼児を抱き、左手で我が子を救世主であることを示しながらも
子の行く末に待つ受難を予知する、底なし沼のような深い悲哀をたたえた大きな眼。
どれも復活などと信じることができないような ≪ただの人間≫ の死体と慈愛より不安がそこにあるばかり。
抜き取った意味も、人も、わかりませんが これも宗教のなせる業(ワザ)なのでしょうか。
最近 ラフマニノフなどのロシアクラッシックにハマっておりますが、もう少しロシアを探ってみたい そんな気がします。