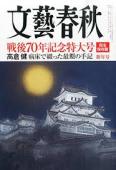2年前・病後ではあったが、ヨーロッパに旅をしたことがあった。
当ブログ・ヨーロッパへの旅(クリックしてみて下さい)
旅は楽しい思い出・あこがれだが、悔いることも多い。
あれも観ておけば、これも調べておけば、あぁそうだったのか、あそこにあったのになぁ、、なんて。
ザルツブルクに旅した時も、近郊・標高1800mほどに側近から贈られたヒットラーの山荘(別荘)があるを知り、
”あのヒットラーがどんな自然を愛したのか”などと良からぬ妄想を抱いたが、ある事情で断念した事があった。

(インターネットから借用~山荘からの眺め・右下にはザウツブルク市街・モーツアルトやサウンドミュージックの舞台でもある)
ヒットラーは高所恐怖症で、たいしてそこには訪ねていない等々これも良からぬ情報を得、当時熱中していた
モーツアルト、市街にある生家やザルツブルク城などを巡る旅一本に絞ったのがその理由であった。
その山荘からの景色なども観ておけばと、ザルツブルクがサウンドミュージックの舞台だとも知らなかった。
旅とは いや 人生とは 悔いばかり。 歌の文句のようにはいかないようです。
観る旅、聴く旅、読む旅、味わう旅、語る旅、そして酒に酔いしれる夢の旅、病床で闘う苦悩の旅もある。
人生すべて旅、、とよく言われるが、行き着く先はどこなのでしょうかねぇ。
旅と言えば、我が山の会(いまは観・酒乱の会に改名?)に旅に明け暮れる仲間がいる。
最近読んだ詩人・リルケにこんな旅の詩があった。 その旅の達人にあてはまるような詩が。
遠くまで世界を巡り 旅ゆくものよ
こころ静かに 悠々とさすらい 歩み続けよ
人の苦悩を君ほどに
知る人はいないのだから
明るい光を放ちながら
君が歩みはじめるとき
悲しみは濡れた眼を
君に向かって開くのだ
その瞳のなかに まるで
解ってくれ! と呼びかけるように
その奥底に
悲しみに満ちた世界がある
かぎりない涙は語る
いつまでも癒され 鎮まることなく
その涙 ひとつひとつに
君の姿が 映っている!
≪ かぎりない涙を 一心に背負って 旅をしてごらん ≫ そんなふうにも聴こえます。
≪ 千里の旅は万巻の書に値する ≫とは今年初めに他界した森本哲郎の言葉。(昨日の道新朝刊コラムより)
世界的な詩人・リルケに 背中を押されるなんて 達人 プレッシャーかな~?(笑)