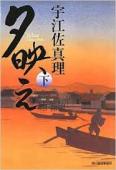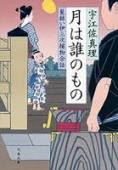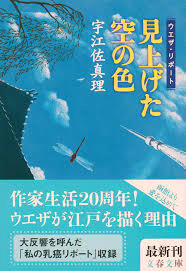先日、シドニィシェルダンのベストセラー小説 『ゲームの達人』 を読んでいた。
(内容は・・スコットランドに生まれたジェミー・マクレガーは16歳の時、一攫千金を夢見て、ダイヤモンドラッシュに沸く
南アフリカに単身旅立つ。そこでバンダミアという人物に会い、だまされて無一文となり、復讐を誓う・・・)
これほどに面白い小説も無い、と夢中で上巻を読んでいたが、復讐後ジェミーが他界する上巻の後半からは
どうもその後の展開について行けず、下巻を読むのを早々断念したほどです。
集中力に欠くせいもあるのだが、どうも私には長編は性に合わないようだ。
さて短編だが、黒虫俊平という人の書いた短編のひとつに 『 ね こ 』 というのがある。
『 空の蒼く晴れた日、ねこはどこからかやって来て、庭の山茶花(さざんか)のしたで居眠りしている。
洋画をかいている友人は、ペルシャでないか、と私に聞いた。 私は、すてねこだろう、と答えて置いた。
ねこは誰にもなつかなかった。
ある日、私が朝食の鰯(いわし)を焼いていたら、庭のねこがものうげに泣いた。
私も縁側へでて、にゃあ、と言った。 ねこは起きあがり、静かに私のほうへ歩いて来た。
私は鰯を一尾なげてやった。 ねこは逃げ腰をつかいながらもたべたのだ。
私の胸は浪うった。 わが恋は容(い)れられたり。
ねこの白い毛を撫でたく思い、庭へおりた。
すると 脊中の毛にふれるや、ねこは私の小指の腹を骨までかりりと噛(か)み裂いた。』
ねこを人間に、いや いかなるものにおきかえることができるのだろうか。
たったこれだけの文章。 これぞ短編。 鋭い。 詩・短歌・俳句の如くだ。
黒虫俊平という名は、あの太宰治が太宰治であるまえのペンネームという。

(内容は・・スコットランドに生まれたジェミー・マクレガーは16歳の時、一攫千金を夢見て、ダイヤモンドラッシュに沸く
南アフリカに単身旅立つ。そこでバンダミアという人物に会い、だまされて無一文となり、復讐を誓う・・・)
これほどに面白い小説も無い、と夢中で上巻を読んでいたが、復讐後ジェミーが他界する上巻の後半からは
どうもその後の展開について行けず、下巻を読むのを早々断念したほどです。
集中力に欠くせいもあるのだが、どうも私には長編は性に合わないようだ。
さて短編だが、黒虫俊平という人の書いた短編のひとつに 『 ね こ 』 というのがある。
『 空の蒼く晴れた日、ねこはどこからかやって来て、庭の山茶花(さざんか)のしたで居眠りしている。
洋画をかいている友人は、ペルシャでないか、と私に聞いた。 私は、すてねこだろう、と答えて置いた。
ねこは誰にもなつかなかった。
ある日、私が朝食の鰯(いわし)を焼いていたら、庭のねこがものうげに泣いた。
私も縁側へでて、にゃあ、と言った。 ねこは起きあがり、静かに私のほうへ歩いて来た。
私は鰯を一尾なげてやった。 ねこは逃げ腰をつかいながらもたべたのだ。
私の胸は浪うった。 わが恋は容(い)れられたり。
ねこの白い毛を撫でたく思い、庭へおりた。
すると 脊中の毛にふれるや、ねこは私の小指の腹を骨までかりりと噛(か)み裂いた。』
ねこを人間に、いや いかなるものにおきかえることができるのだろうか。
たったこれだけの文章。 これぞ短編。 鋭い。 詩・短歌・俳句の如くだ。
黒虫俊平という名は、あの太宰治が太宰治であるまえのペンネームという。