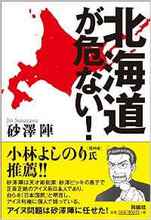年末年始は鳥や昆虫の生態本ばかり読んで、静かに日々を過ごしております。
新年のブログは、まずは福を呼ぶ ≪ ク モ ≫ からのスタートです(笑)。
その姿形からして嫌われ者のクモですが、「朝グモは福を呼ぶ」 って言い伝えもあるそうですよ。
そういえば子供のころ母にうっすらとですが ≪ クモを殺すな ≫ って言われた記憶が・・・。
クモの巣には横糸と縦糸があるが、獲物を捕まえる粘着性があるのは横糸だけのようです。
だから移動する場合はその糸を巧みに外し縦糸を上手く渡る、お見事としか言いようがない。
危険を察したら牽引糸(命綱)を使って咄嗟に下りる。 スーッと糸を垂らして下る、あの糸がそうです。
顕微鏡で観ると一本じゃなく二本の管になっているとか、春の子グモから秋の成人(いや成体)になるまでの
体重とその強度は、三対二と子グモの牽引糸は力学的に丈夫にできているとか、その他諸々。
この本結構面白い。 まぁ読んでみて下さい。 クモ されど クモ って感じです。




芥川龍之介の小説 「蜘蛛の糸」 ご存知ですよね。 お釈迦様が、地獄に住む人(カンタダ)を
救おうと一本の蜘蛛の糸を垂らす物語だが、蹴落としてまで生きようとする人間の持つ業を描いた名作だ。
その芥川さんも目を丸くするようなクモの生態が書かれている。
著者は高分子物理化学者・大﨑茂芳。 世界中から集めたクモたちを研究室に放つ好奇心には恐れ入る。
こんなことがあったという。 誕生した子グモの群れに棒を入れ、取出してからその棒を少し
震わすと、棒から多くの子グモが牽引糸(命綱)を垂らして降りてくる習性を観察していた時のこと。
震わすのを止めると、すべての子グモは安全を察知し登っていく。 すると一匹の子グモが奇妙な行動
をしたというのだ。 最下位でモタモタしていた子グモがいたとき、その子グモを助けに降りていったのだ。
自分が最下位になって、しばらく様子を見てから上へ登っていく。 しかも、その子グモは仲間を
助けるだけではなく、牽引糸をすべて集めるなどの整理整頓まで行っていたという。
考えてみれば人間の歴史は700万年ほどが通説になっているようだが、クモは4億年ともいわれる。
到底勝てっこないのである。 人類は万物の長だと? 都合よくできているもんだ 人間ってのは。
新年のブログは、まずは福を呼ぶ ≪ ク モ ≫ からのスタートです(笑)。
その姿形からして嫌われ者のクモですが、「朝グモは福を呼ぶ」 って言い伝えもあるそうですよ。
そういえば子供のころ母にうっすらとですが ≪ クモを殺すな ≫ って言われた記憶が・・・。
クモの巣には横糸と縦糸があるが、獲物を捕まえる粘着性があるのは横糸だけのようです。
だから移動する場合はその糸を巧みに外し縦糸を上手く渡る、お見事としか言いようがない。
危険を察したら牽引糸(命綱)を使って咄嗟に下りる。 スーッと糸を垂らして下る、あの糸がそうです。
顕微鏡で観ると一本じゃなく二本の管になっているとか、春の子グモから秋の成人(いや成体)になるまでの
体重とその強度は、三対二と子グモの牽引糸は力学的に丈夫にできているとか、その他諸々。
この本結構面白い。 まぁ読んでみて下さい。 クモ されど クモ って感じです。




芥川龍之介の小説 「蜘蛛の糸」 ご存知ですよね。 お釈迦様が、地獄に住む人(カンタダ)を
救おうと一本の蜘蛛の糸を垂らす物語だが、蹴落としてまで生きようとする人間の持つ業を描いた名作だ。
その芥川さんも目を丸くするようなクモの生態が書かれている。
著者は高分子物理化学者・大﨑茂芳。 世界中から集めたクモたちを研究室に放つ好奇心には恐れ入る。
こんなことがあったという。 誕生した子グモの群れに棒を入れ、取出してからその棒を少し
震わすと、棒から多くの子グモが牽引糸(命綱)を垂らして降りてくる習性を観察していた時のこと。
震わすのを止めると、すべての子グモは安全を察知し登っていく。 すると一匹の子グモが奇妙な行動
をしたというのだ。 最下位でモタモタしていた子グモがいたとき、その子グモを助けに降りていったのだ。
自分が最下位になって、しばらく様子を見てから上へ登っていく。 しかも、その子グモは仲間を
助けるだけではなく、牽引糸をすべて集めるなどの整理整頓まで行っていたという。
考えてみれば人間の歴史は700万年ほどが通説になっているようだが、クモは4億年ともいわれる。
到底勝てっこないのである。 人類は万物の長だと? 都合よくできているもんだ 人間ってのは。