※ ワシントンDC/フリップスコレクション(13) ‐ DC&NYの美術館にみる泰西名画選(13)
フリップスコレクション、なぜか、最終回はこの作品でなければ、と思っていた。
旅の案内書 「地球の歩き方」に “ 必見、しっかり見ておきたい ” とあって刷り込まれていたのかも。
その作品とは、ピエール=オーギュスト・ルノワール(1841-1919)の 「舟遊びをする人々の昼食」。
主題は、<イル・ド・フランス>のシャトゥー島、ラ・グルヌイエールにあるレストランのテラスで、舟遊びに興じる人々の昼食の場面。
 余談だがラ・グルヌイエール、パリに程近いセーヌ河畔の新興行楽地、水上カフェがある水浴場だったとか。
余談だがラ・グルヌイエール、パリに程近いセーヌ河畔の新興行楽地、水上カフェがある水浴場だったとか。
69年の夏に友人である<モネ>(1840-1926)と同地で画架を並べ描いた 「<ラ・グルヌイエールにて>」(ストックホルム国立美術館蔵)が知られている。
本作、彼には珍しく、傑作 「<ムーラン・ド・ラ・ギャレットの舞踏場>」(オルセー美術館蔵)と同様に、画家の友人・知人らの姿を集団的に描いている。
夏の昼下がり、葦の合間からヨットが望める陽光溢れるテラスで楽しそうに語らう様子を、彼独特の豊潤な色彩で解放的に描いている。
それとは対照的に、ワインと果物、皿やグラスやナプキンなどが置かれたテーブルを中心に配することによって、作品に奥行を与えている。
ということで小編、フリップスコレクションと別れ、DC・ユニオン駅からアムトラック・アセラでNY・ペン駅とへ向かう。
Peter & Catherine’s Travel. Tour No.1227












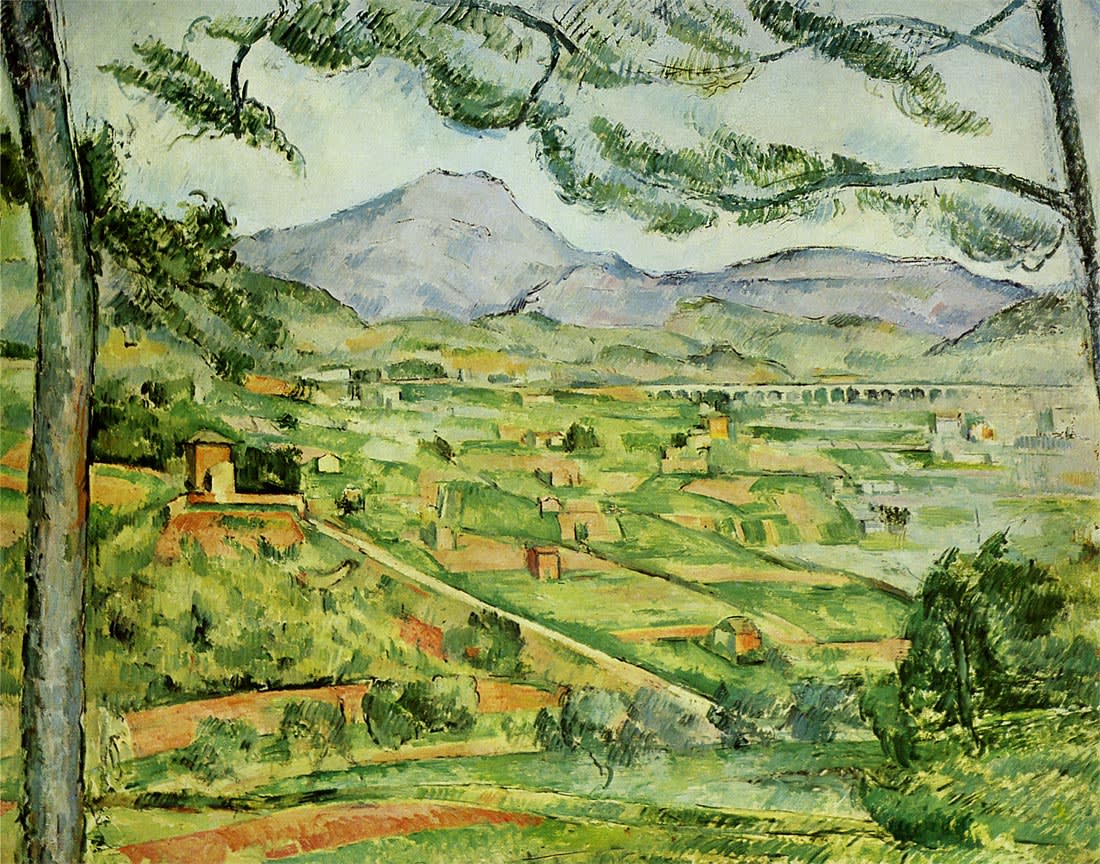


 とて、旅の前にはある程度の知識は仕入れている。
とて、旅の前にはある程度の知識は仕入れている。 主題はいたって簡単、公園の入口の景色だが、この作品には、偶然なのか画家の仕掛けなのか、公園に入って突き当りの小道が別れる辺り、仰向けの顔が描かれている・・・と、言うのである。
主題はいたって簡単、公園の入口の景色だが、この作品には、偶然なのか画家の仕掛けなのか、公園に入って突き当りの小道が別れる辺り、仰向けの顔が描かれている・・・と、言うのである。 投稿氏は、次のように解いている。
投稿氏は、次のように解いている。








