※ ワシントンDC/フリップスコレクション(3) ‐ DC&NYの美術館にみる泰西名画選(3)
貝殻装飾を語源とするロココ様式、そのフランス絵画を代表するジャン・シメオン・シャルダン(1699-1779)。
静物画や風俗画などに、繊細な色彩、柔らかく包み込むような光の表現などで、当時、絶大な人気を博したという。
また、後期印象派のセザンヌ(1839-1906/フランス)やマティス(1869-1954/フランス/20世紀芸術)などにも大きな影響を与えたとされている。
 その<シャルダン>の最初期の作品 「プラムを盛った鉢A」(1728年/62.2 x74.3 cm)。
その<シャルダン>の最初期の作品 「プラムを盛った鉢A」(1728年/62.2 x74.3 cm)。
白い磁器の水差しとプラム、浅い鉢にも盛られたプラム、左隅にもプラム、そして洋梨とその種だろうか、が配されている。
白地に花が絵付けされた水差しの光沢を帯びた輝く質感。
その手前や鉢に盛られたプラムは、鮮度の良さを示す果皮の白い果粉まで微細に描かれ、甘酸っぱい豊潤な香りさえ感じさせるほどに瑞々しい。
本作から35年、円熟期に同じモティーフで描いた傑作 「<葡萄と石榴>」(1763年/47×57cm)や 「<桃の籠>」(1768年/32.5×39.5cm/何れもルーヴル美術館蔵)に比べ、空間構成にややまとまりが欠けるが、それは若い画家が与えられた伸び代というものか?
とまれ、これらの静物画、ここフリップスコレクションが所蔵する 「<生姜ポットとザクロと洋ナシ>」を描いた<セザンヌ>などに大きな影響を与えたことが窺えるのである。
Peter & Catherine’s Travel. Tour No.1208










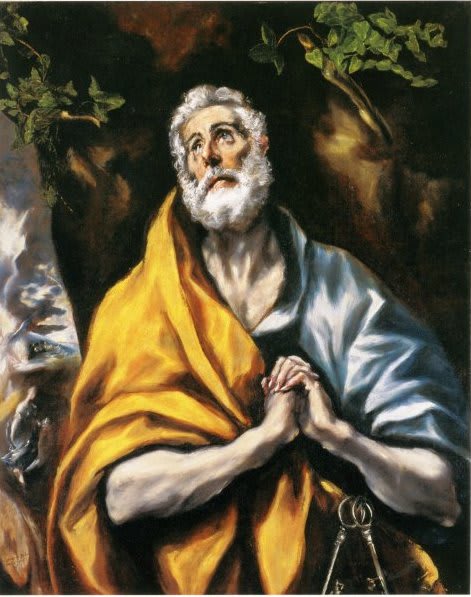
 、絵を前にして足が動かなくなってしまった。
、絵を前にして足が動かなくなってしまった。 、目指す作品があるのだろう、さっさと展示室に入ってしまったけれど。
、目指す作品があるのだろう、さっさと展示室に入ってしまったけれど。
















