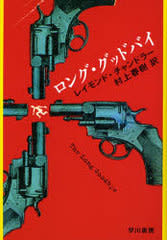反対に、東京くらいの大都市になると、供託金300万円で選挙公報と政見放送で自分の主張をすることができると考えると安いともいえます。
ユニークな選挙公報の中でもとりわけ目を引くのが外山恒一氏。デカイ字で「政府転覆」、その他にも「いまどき政治犯」、「福岡刑務所卒」と過激な文字が並んでいます。
この外山氏の政見放送がネット上で話題を集めています。検索サイトで「政見放送」と入れるだけで、外山恒一氏の政見放送に関する情報が多数ヒットします。You Tube等のサイトで動画を視聴することも可能です。
これが、またぶっ飛びの政見放送です。ただ、内容はともかく、話し方、服装、バックミュージック等計算尽くされた演出も見え隠れします。
扇情的な音楽をバックに「諸君!」と呼びかける演説口調は、ナチスを連想させます。黒のトックリのシャツにスキンヘッドというのも顔を浮かび上がらせ強い印象を残します。
過激な言葉を連発しながら、「最後に言っておく!」、「もし私が当選したら奴らはビビル!」、「俺もビビル」なんて言うくだりなどはユーモアさえ感じさせます。
とにもかくにも、過激な主張が公共電波を使って広く流布され、それがネットを伝ってさらに多くの人々の関心を呼ぶというのは、ネット社会の情報伝達のおそろしいところです。