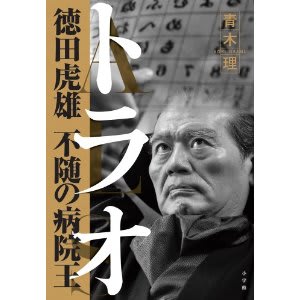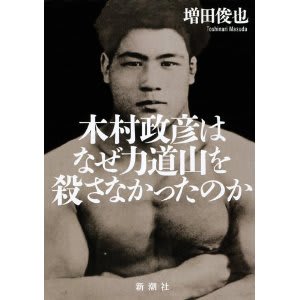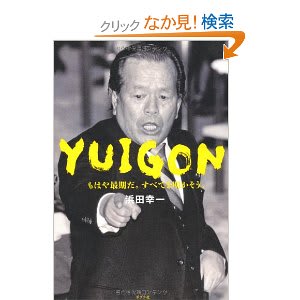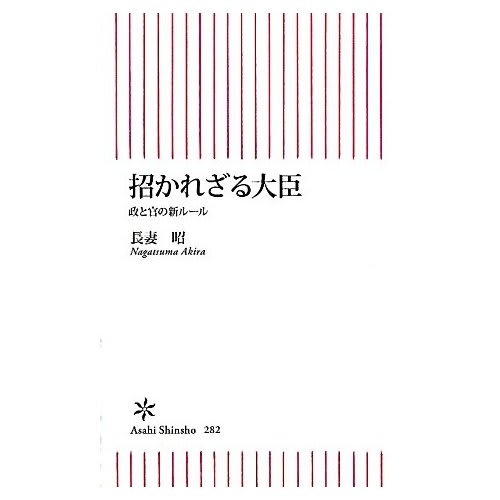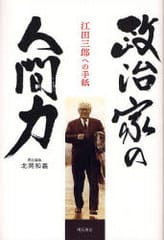「やなせたかし 明日をひらく言葉」
PHP研究所編/PHP文庫
なんのために生まれて
なにをして生きるのか
この哲学的問いかけは、なんとアンパンマンのマーチの一節です。
幼児向けのアニメの主題歌アンパンマンのマーチの詩は、あらためて読み直すと、本当にいい詩です。
東日本大震災の時に、ラジオ番組に、アンパンマンのマーチのリクエストが殺到し、多くの被災者が勇気づけられました。
新幹線の駅のキオスクで偶然、手にしたこの本を読んで、これを作詞したアンパンマンの作者で漫画家のやなせたかしさんが詩人でもあることをはじめて知りました。皆さんは、子どもの頃に誰もが歌ったことのある「てのひらを太陽に」の作詞もやなせさんだと知っていましたか。
未熟児で生まれたやなせさんは、幼少期は劣等感に悩み、実はアンパンマンがブレイクしたのは、70歳の頃だそうです。「なんのために生まれて なにをして生きるのか こたえられないなんて そんなのはいやだ!」という詩には、やなせさんの懊悩が表現されています。
その一つの答えがこんな言葉として表れています。
人間が一番うれしいことはなんだろう?
長い間、ぼくは考えてきた。
そして、結局、人が一番うれしいのは、
人をよろこばせることだということがわかりました。
実に単純なことです。
ひとはひとをよろこばせることが一番うれしい。
私は、これはいい言葉だと思います。たとえば、一所懸命、料理を作って、「おいしい」と食べて、よろこんでくれる人の笑顔を見るのがうれしい。自分の仕事を通して、人をよろこばし、幸せにする、これは、人生の究極の目標かもしれません。
アンパンマンは、正義のヒーローです。やなせさんは「アンパンマンは世界最弱のヒーローだ」と言います。やなせさんの正義についての考え方がまたこれがいい。
悪人を倒すことよりも、
弱い人を助ける。
ぼくが望む正義は、それほど難しことではないのです。
アンパンマンは、自分の顔をちぎって人に食べさせる。
本人も傷つくんだけれど、それによって人を助ける。
そういう捨て身、献身の心なくしては
正義は行えない。
人をよろこばせることが人生の目的、身を捨ててもで弱い人を助ける、いずれも政治家として肝に銘じたい。
PHP研究所編/PHP文庫
なんのために生まれて
なにをして生きるのか
この哲学的問いかけは、なんとアンパンマンのマーチの一節です。
幼児向けのアニメの主題歌アンパンマンのマーチの詩は、あらためて読み直すと、本当にいい詩です。
東日本大震災の時に、ラジオ番組に、アンパンマンのマーチのリクエストが殺到し、多くの被災者が勇気づけられました。
新幹線の駅のキオスクで偶然、手にしたこの本を読んで、これを作詞したアンパンマンの作者で漫画家のやなせたかしさんが詩人でもあることをはじめて知りました。皆さんは、子どもの頃に誰もが歌ったことのある「てのひらを太陽に」の作詞もやなせさんだと知っていましたか。
未熟児で生まれたやなせさんは、幼少期は劣等感に悩み、実はアンパンマンがブレイクしたのは、70歳の頃だそうです。「なんのために生まれて なにをして生きるのか こたえられないなんて そんなのはいやだ!」という詩には、やなせさんの懊悩が表現されています。
その一つの答えがこんな言葉として表れています。
人間が一番うれしいことはなんだろう?
長い間、ぼくは考えてきた。
そして、結局、人が一番うれしいのは、
人をよろこばせることだということがわかりました。
実に単純なことです。
ひとはひとをよろこばせることが一番うれしい。
私は、これはいい言葉だと思います。たとえば、一所懸命、料理を作って、「おいしい」と食べて、よろこんでくれる人の笑顔を見るのがうれしい。自分の仕事を通して、人をよろこばし、幸せにする、これは、人生の究極の目標かもしれません。
アンパンマンは、正義のヒーローです。やなせさんは「アンパンマンは世界最弱のヒーローだ」と言います。やなせさんの正義についての考え方がまたこれがいい。
悪人を倒すことよりも、
弱い人を助ける。
ぼくが望む正義は、それほど難しことではないのです。
アンパンマンは、自分の顔をちぎって人に食べさせる。
本人も傷つくんだけれど、それによって人を助ける。
そういう捨て身、献身の心なくしては
正義は行えない。
人をよろこばせることが人生の目的、身を捨ててもで弱い人を助ける、いずれも政治家として肝に銘じたい。