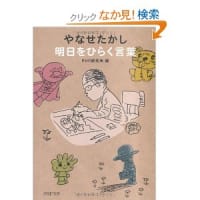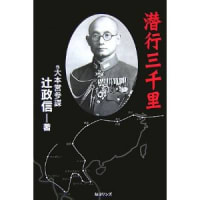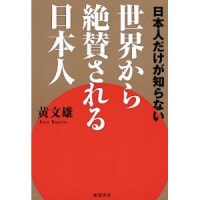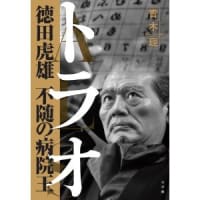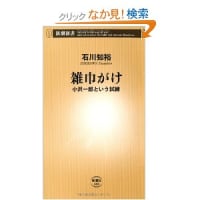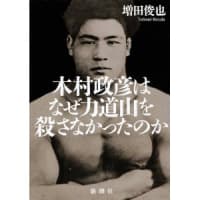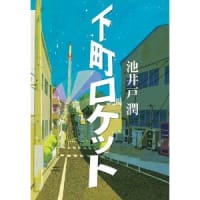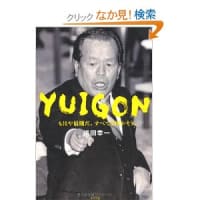「一新塾」と言っても「一新会」とはまったく関係ない。政策学校NPO法人「一新塾」のことです。
GEIL2006の第2次コンサルティングの翌日は、「一新塾」政策提言の中間発表会のコメンテーターの一人としてお招きいただきました。
他の二人のコメンテーターは、一新塾の理事で環境総合研究所代表の青山貞一さん、自民党シンクタンク事務局長の鈴木崇弘さんといずれもこの世界では名前の知れた方々です。
学生やサラリーマン等の塾生による政策提言案のプレゼンとそれに対する講評に入る前には、田中康夫前長野県知事のブレーンの一人である青山さんから田中県政の総括についてのミニ講義があり、また、それを補足する形で、田中側近の一人である作家の佐藤清文さんが簡単な講演を行いました。
私は、残念ながら遅れて行ったので青山さんの講義は聞くことができなかったのですが、佐藤さんの話は大変興味深かったです。
佐藤さんは、まず、作家として田中康夫を文壇と言う古い体質をポストモダンの旗手としてして打ち破った人として位置づけます。そして、小説家としての田中康夫は、そのダンディズム故に群れることを嫌い、他の人とコミニケーションを深化させることができなかったと批判しています。田中康夫は、古い体制を壊すことには成功したが、新たな文学の方向性を示すことができなかったと辛口の評価を下しています。
そして、小説家としての限界は、そのまま政治家としての限界にも当てはまると言います。つまり、「脱ダム宣言」で旧体制を壊したが、その後の新しい政治理念というのを示すことができなかったことが田中知事の最大の失敗だと言うのです。
なかなかおもしろい分析だと思いました。
一新塾の政策提言を聞いて感じたのは次の3つのことです。
まず、「壮大な政策提言はいらない!」
一新塾は、「主体的市民」、「現場主義」を謳っています。官僚が机上で考えたのでは出てこない現場感覚、市民感覚溢れる政策提言が期待されるところです。
第2に「現状分析をしっかりと」GEIL2006を見ていても、問題解決の手法についてアイデアが生まれればあとはディティールの問題です。まず、何が問題なのかを見極め、問題解決へのアプローチを研究すること、最初のステージが不十分だと土台が揺らいでしまいます。
この点、私はよほどの天才でない限り人の考えることに大きな大差はないと思います。まず、自分が思いついたことは、きっと他にも同じことを考えて実行している人がいるはずと思って探してみることが大切だと思います。私が少しネットで検索して見つけることができるような事例を意外に研究していないことは少し残念な気がします。同じ問題意識で実践例があっても、そこに欠けているもの、焦点の当て方の違い等を考えれば何かアイデアが生まれてくるはずです。
私の意見には「でも、やはりオリジナリティーがないと」とのご批判もいただきました。私は、オリジナリティーを否定しているわけではありません。誰も思いつかない素晴らしいアイデアを思いつければそれに越したことはありませんが、例えば、科学者でも先人の研究の積み重ねや他の研究者の先行事例の研究の上に独自の発見が生まれるのだと思います。
第3は「協同」です。例えば、私のような政策秘書を使ってもらえば、必要な統計データや政府の施策に関する情報を入手することも可能です。「市民の手で!」と気負いすぎずに、政治や行政、他のNPO等の市民セクターと協調することで、より実現可能性の高い政策立案が可能になると思います。
一方、今回の政策提言の中には、既に実践として動き出しているものがいくつか見られ、一新塾ならではのアクションに結びつく政策提言と言う点では期待を感じさせるものでした。
GEIL2006の第2次コンサルティングの翌日は、「一新塾」政策提言の中間発表会のコメンテーターの一人としてお招きいただきました。
他の二人のコメンテーターは、一新塾の理事で環境総合研究所代表の青山貞一さん、自民党シンクタンク事務局長の鈴木崇弘さんといずれもこの世界では名前の知れた方々です。
学生やサラリーマン等の塾生による政策提言案のプレゼンとそれに対する講評に入る前には、田中康夫前長野県知事のブレーンの一人である青山さんから田中県政の総括についてのミニ講義があり、また、それを補足する形で、田中側近の一人である作家の佐藤清文さんが簡単な講演を行いました。
私は、残念ながら遅れて行ったので青山さんの講義は聞くことができなかったのですが、佐藤さんの話は大変興味深かったです。
佐藤さんは、まず、作家として田中康夫を文壇と言う古い体質をポストモダンの旗手としてして打ち破った人として位置づけます。そして、小説家としての田中康夫は、そのダンディズム故に群れることを嫌い、他の人とコミニケーションを深化させることができなかったと批判しています。田中康夫は、古い体制を壊すことには成功したが、新たな文学の方向性を示すことができなかったと辛口の評価を下しています。
そして、小説家としての限界は、そのまま政治家としての限界にも当てはまると言います。つまり、「脱ダム宣言」で旧体制を壊したが、その後の新しい政治理念というのを示すことができなかったことが田中知事の最大の失敗だと言うのです。
なかなかおもしろい分析だと思いました。
一新塾の政策提言を聞いて感じたのは次の3つのことです。
まず、「壮大な政策提言はいらない!」
一新塾は、「主体的市民」、「現場主義」を謳っています。官僚が机上で考えたのでは出てこない現場感覚、市民感覚溢れる政策提言が期待されるところです。
第2に「現状分析をしっかりと」GEIL2006を見ていても、問題解決の手法についてアイデアが生まれればあとはディティールの問題です。まず、何が問題なのかを見極め、問題解決へのアプローチを研究すること、最初のステージが不十分だと土台が揺らいでしまいます。
この点、私はよほどの天才でない限り人の考えることに大きな大差はないと思います。まず、自分が思いついたことは、きっと他にも同じことを考えて実行している人がいるはずと思って探してみることが大切だと思います。私が少しネットで検索して見つけることができるような事例を意外に研究していないことは少し残念な気がします。同じ問題意識で実践例があっても、そこに欠けているもの、焦点の当て方の違い等を考えれば何かアイデアが生まれてくるはずです。
私の意見には「でも、やはりオリジナリティーがないと」とのご批判もいただきました。私は、オリジナリティーを否定しているわけではありません。誰も思いつかない素晴らしいアイデアを思いつければそれに越したことはありませんが、例えば、科学者でも先人の研究の積み重ねや他の研究者の先行事例の研究の上に独自の発見が生まれるのだと思います。
第3は「協同」です。例えば、私のような政策秘書を使ってもらえば、必要な統計データや政府の施策に関する情報を入手することも可能です。「市民の手で!」と気負いすぎずに、政治や行政、他のNPO等の市民セクターと協調することで、より実現可能性の高い政策立案が可能になると思います。
一方、今回の政策提言の中には、既に実践として動き出しているものがいくつか見られ、一新塾ならではのアクションに結びつく政策提言と言う点では期待を感じさせるものでした。