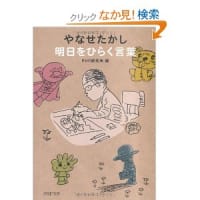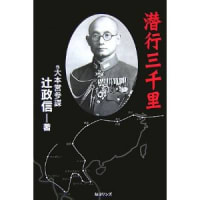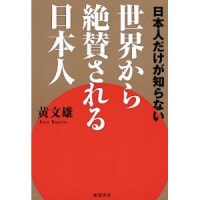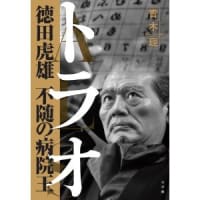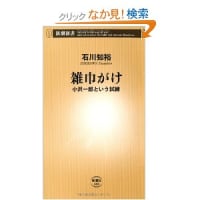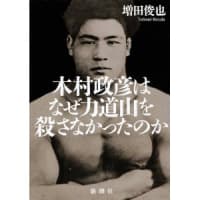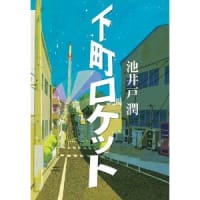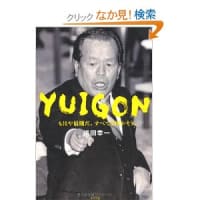現在、自動車をはじめとする日本の製造業は、「6重苦」に直面していると言われています。6つの苦境とは、①円高、②高い法人税、③自由貿易協定の遅れ、④製造業への派遣禁止、⑤CO2の25%削減、⑥震災とそれに伴う電力不足の問題、です。
そんな中、債務上限引き上げ問題について米国議会での対立が深刻化し米国債がデフォルト(債務不履行)になる懸念から、ドル売りが進み、相対的に安全な円を買う動きが加速し、3日の東京外国為替市場では一時、1ドル=76円台に突入し、経済界に激震が走りました。
トヨタは1円で営業利益が300億円吹き飛ぶといわれています。これでは血のにじむようなコスト削減も水の泡に帰してしまいます。
政府が「マーケットの動きを注意深く見守りたい」といった決まり文句を繰り返すだけの中、経済界を中心に苛立ちの声が上がっていました。政府関係者はよく「単独介入しても効果は期待できない」と言います。しかし、世界各国が自国通貨安競争をしている中で協調介入は期待できません。はなから単独介入を否定しては「日本政府は円高に対して打つ手がない。事実上容認している。」という間違ったメッセージを送ることになってしまいます。
まずは「単独介入も辞さない。断固として超円高を阻止する。」という強い姿勢を示すことです。政府が徹底介入を本気で実行すると市場参加者が信じれば、実際に大量介入を行わなくても円高を止めることもできるかもしれない。
もう一つ、私は「為替介入の非不胎化」を主張したいと思います。「為替介入の非不胎化」とは、ドル買い介入によって増えた日銀当座預金を政府短期証券(FB)の売りオペなどによって日銀が吸収することなく、そのまま放置して、ベース・マネーを増加させる政策を言います。
1999年当時にイェール大学の浜田宏一教授が唱えた「非不胎化介入論」がエコノミストの間に大論争を巻き起こしたことがありました。これについては、やや専門的な話になるので個々での説明は省略します。
ただ、99年9月に当時の堺屋経企庁長官が「不胎化しない介入の選択肢の一つ」と述べただけで、円買いの勢いが一時弱まったということもありました。
また、2003年1月~2004年3月にかけて日本政府は合計35兆円の介入を実施しましたが、この時期に日銀が当座預金目標を15兆円引き上げたことが「部分的な介入資金の非不胎化」として、為替レートに円安効果を与えたという観測もあります。
99年以降介入資金の原資となる政府短期証券は、それまでの日銀引き受けではなく市場で引き受けられるようになったので、非不胎化には、単に介入資金を放置するだけでは不十分で、資金供給の拡大を伴う追加的金融緩和を行うことが必要です。
白川総裁は、これまで非不胎化介入について前向きな発言を行っており、同時に今後とも必要であれば追加緩和策を採用していく意向を示してきました。
そうした中、今日4日午前、政府・日銀は、約4ヶ月半ぶりとなる円売り・ドル買いの為替介入を実施しました。一方、日銀も一日前倒しで、金融政策決定会合を開き、追加の金融緩和策として、社債などの資産を買い取る基金の規模を10兆円増額して50兆円にすることを決めました。野田財務相は緊急会見し、「無秩序な動きには断固たる措置を取る」と述べ、日銀の白川総裁も「(介入が)為替相場の安定的な形成に寄与することを強く期待する」との談話を発表しました。
私は、今回の政府と日銀の連携した動きは、評価してよいと思います。今後とも政府と日銀がコミニケーションを密にして協調することが重要です。市場もこれに反応、為替介入が効を奏し、外国為替市場で、ドルが一時80円まで上昇し、3週間ぶりの高値を更新しました。為替介入の効果は一時的との見方もあるが、ワンショットで終わらせることなく、円高阻止の断固たる姿勢を貫くことと、それに呼応した追加的金融緩和を思いきって行うことを引き続き求めていきます。
そんな中、債務上限引き上げ問題について米国議会での対立が深刻化し米国債がデフォルト(債務不履行)になる懸念から、ドル売りが進み、相対的に安全な円を買う動きが加速し、3日の東京外国為替市場では一時、1ドル=76円台に突入し、経済界に激震が走りました。
トヨタは1円で営業利益が300億円吹き飛ぶといわれています。これでは血のにじむようなコスト削減も水の泡に帰してしまいます。
政府が「マーケットの動きを注意深く見守りたい」といった決まり文句を繰り返すだけの中、経済界を中心に苛立ちの声が上がっていました。政府関係者はよく「単独介入しても効果は期待できない」と言います。しかし、世界各国が自国通貨安競争をしている中で協調介入は期待できません。はなから単独介入を否定しては「日本政府は円高に対して打つ手がない。事実上容認している。」という間違ったメッセージを送ることになってしまいます。
まずは「単独介入も辞さない。断固として超円高を阻止する。」という強い姿勢を示すことです。政府が徹底介入を本気で実行すると市場参加者が信じれば、実際に大量介入を行わなくても円高を止めることもできるかもしれない。
もう一つ、私は「為替介入の非不胎化」を主張したいと思います。「為替介入の非不胎化」とは、ドル買い介入によって増えた日銀当座預金を政府短期証券(FB)の売りオペなどによって日銀が吸収することなく、そのまま放置して、ベース・マネーを増加させる政策を言います。
1999年当時にイェール大学の浜田宏一教授が唱えた「非不胎化介入論」がエコノミストの間に大論争を巻き起こしたことがありました。これについては、やや専門的な話になるので個々での説明は省略します。
ただ、99年9月に当時の堺屋経企庁長官が「不胎化しない介入の選択肢の一つ」と述べただけで、円買いの勢いが一時弱まったということもありました。
また、2003年1月~2004年3月にかけて日本政府は合計35兆円の介入を実施しましたが、この時期に日銀が当座預金目標を15兆円引き上げたことが「部分的な介入資金の非不胎化」として、為替レートに円安効果を与えたという観測もあります。
99年以降介入資金の原資となる政府短期証券は、それまでの日銀引き受けではなく市場で引き受けられるようになったので、非不胎化には、単に介入資金を放置するだけでは不十分で、資金供給の拡大を伴う追加的金融緩和を行うことが必要です。
白川総裁は、これまで非不胎化介入について前向きな発言を行っており、同時に今後とも必要であれば追加緩和策を採用していく意向を示してきました。
そうした中、今日4日午前、政府・日銀は、約4ヶ月半ぶりとなる円売り・ドル買いの為替介入を実施しました。一方、日銀も一日前倒しで、金融政策決定会合を開き、追加の金融緩和策として、社債などの資産を買い取る基金の規模を10兆円増額して50兆円にすることを決めました。野田財務相は緊急会見し、「無秩序な動きには断固たる措置を取る」と述べ、日銀の白川総裁も「(介入が)為替相場の安定的な形成に寄与することを強く期待する」との談話を発表しました。
私は、今回の政府と日銀の連携した動きは、評価してよいと思います。今後とも政府と日銀がコミニケーションを密にして協調することが重要です。市場もこれに反応、為替介入が効を奏し、外国為替市場で、ドルが一時80円まで上昇し、3週間ぶりの高値を更新しました。為替介入の効果は一時的との見方もあるが、ワンショットで終わらせることなく、円高阻止の断固たる姿勢を貫くことと、それに呼応した追加的金融緩和を思いきって行うことを引き続き求めていきます。