今日は、本ブログのメイン・テーマの話題です。
奈良教育大の大先輩:中上武二さんが長年のフィールド調査で蒐集されたお話のうち
76話をまとめて、『大和の民話』を自費出版されました。

-------以下、朝日新聞(20115.10.12.)より---------------------------------
長年、県内各地に伝わる民話を収集してきた小学校の元校長が、「大和の民話」(奈良県篇、奈良市篇の2冊)を自費出版した。
子供たちに聞かせるように、優しくリズム感のある語り口で76話を紹介している。
著者は、水間、帯解、西大寺北の奈良市立の各小学校で校長を務めた中上武二(なかうえたけじ)さん(72)。
野迫川村弓手原(ゆみてはら)で生まれた。
「お大師さん(空海)が高野山にお寺を開く前、弓手原にやってきて候補地にしたこともあった」。
そんな言い伝えを囲炉裏端で祖母や曽祖母から聞いて育った。
奈良学芸大(現奈良教育大)に入り、民俗学者の林宏・助教授(当時)に師事。
下北山村や奈良市の山間部での聞き取り調査に付き従った。宮司や住職、お年寄りの語りに耳を傾けては、つぶさに書きとめた。
小学校教諭になってからも、十津川村や野迫川村での調査を続け、研究会で報告。
教室で子供たちに、季節や年中行事に合った話を語り聞かせた。
「校長先生は昔話をする時、目が大きくなります」と作文に書いた子も。
「うちのじいちゃんもその話、知ってるぞ」などと言われると、家を訪ねて話してもらうこともあった。
1998年、情報誌「月刊大和路ならら」で民話連載を開始。古事記や日本書紀に原典があるものも、そのまま引くのではなく、
必ず登場する舞台に足を運び、地元の人たちに言い伝えを確かめた。
原文の雰囲気を損ねず、わかりやすく伝える言葉選びに心を砕いた。
挿絵は現奈良市立春日中学校の杉本哲也教諭らが担当。中上さんは2010年にくも膜下出血で倒れるまで、136話をつづった。
今回、この中から奈良県篇に31話、奈良市篇に45話を収録。200部ずつを自費出版した。
大和名所記や今昔物語集が伝えるものや、奈良市の「牛に生まれ変わった話」「鳥見の蟹(かに)の恩返し」など
日本霊異記に書かれたもの……。奇想天外な展開の中に、今にも生きる教訓がちりばめられている。
「家族のかたちや娯楽が変わり、伝承は途絶えつつある。各地に伝わる民話を、地元に関心を持つ入り口にしてもらえたら」。
大和の民話は、奈良市の県立図書情報館で読むことができる。(栗田優美)
-------以上、朝日新聞より-------------------
この記事を読んで、一部分けてもらおうと、すぐ先生に連絡したが、残念ながら、在庫はないとのこと。
奈良市立中央図書館、県立図書情報館にあるので、閲覧くださいとのことでした。
このような郷土史家の地味な活動と翻字・再話テキストが、わたしたち、ナーミン(奈良の民話を語りつぐ会)では
大切な資料なのです。
是非、拝読して、私たちのレパートリーに入れたいと思います。
たとえば、次のような話は面白いですね。
-------以下産経新聞(2015.9.19.)記事より-------
奈良県編の箸墓(桜井市)にかかわる民話では、長者の男が貧乏な暮らしを願い、
「箸を捨てると天罰で貧乏になる」という言い伝えから毎日、箸や膳などを捨て、それが積もって箸墓になったという話や、
大峯山寺(天川村)では千手観音の功徳を説いた千手陀羅尼を唱えながら修行していた聖人の男が、
深い谷で大蛇の群れに襲われそうになったが、鬼に助けられる-という話などが紹介されている。
--------以上産経新聞記事より--------------------
では、みなさま、来週末、次のブログでお会いしましょう!
これから寒くなります。みなさま、お元気で!
奈良教育大の大先輩:中上武二さんが長年のフィールド調査で蒐集されたお話のうち
76話をまとめて、『大和の民話』を自費出版されました。

-------以下、朝日新聞(20115.10.12.)より---------------------------------
長年、県内各地に伝わる民話を収集してきた小学校の元校長が、「大和の民話」(奈良県篇、奈良市篇の2冊)を自費出版した。
子供たちに聞かせるように、優しくリズム感のある語り口で76話を紹介している。
著者は、水間、帯解、西大寺北の奈良市立の各小学校で校長を務めた中上武二(なかうえたけじ)さん(72)。
野迫川村弓手原(ゆみてはら)で生まれた。
「お大師さん(空海)が高野山にお寺を開く前、弓手原にやってきて候補地にしたこともあった」。
そんな言い伝えを囲炉裏端で祖母や曽祖母から聞いて育った。
奈良学芸大(現奈良教育大)に入り、民俗学者の林宏・助教授(当時)に師事。
下北山村や奈良市の山間部での聞き取り調査に付き従った。宮司や住職、お年寄りの語りに耳を傾けては、つぶさに書きとめた。
小学校教諭になってからも、十津川村や野迫川村での調査を続け、研究会で報告。
教室で子供たちに、季節や年中行事に合った話を語り聞かせた。
「校長先生は昔話をする時、目が大きくなります」と作文に書いた子も。
「うちのじいちゃんもその話、知ってるぞ」などと言われると、家を訪ねて話してもらうこともあった。
1998年、情報誌「月刊大和路ならら」で民話連載を開始。古事記や日本書紀に原典があるものも、そのまま引くのではなく、
必ず登場する舞台に足を運び、地元の人たちに言い伝えを確かめた。
原文の雰囲気を損ねず、わかりやすく伝える言葉選びに心を砕いた。
挿絵は現奈良市立春日中学校の杉本哲也教諭らが担当。中上さんは2010年にくも膜下出血で倒れるまで、136話をつづった。
今回、この中から奈良県篇に31話、奈良市篇に45話を収録。200部ずつを自費出版した。
大和名所記や今昔物語集が伝えるものや、奈良市の「牛に生まれ変わった話」「鳥見の蟹(かに)の恩返し」など
日本霊異記に書かれたもの……。奇想天外な展開の中に、今にも生きる教訓がちりばめられている。
「家族のかたちや娯楽が変わり、伝承は途絶えつつある。各地に伝わる民話を、地元に関心を持つ入り口にしてもらえたら」。
大和の民話は、奈良市の県立図書情報館で読むことができる。(栗田優美)
-------以上、朝日新聞より-------------------
この記事を読んで、一部分けてもらおうと、すぐ先生に連絡したが、残念ながら、在庫はないとのこと。
奈良市立中央図書館、県立図書情報館にあるので、閲覧くださいとのことでした。
このような郷土史家の地味な活動と翻字・再話テキストが、わたしたち、ナーミン(奈良の民話を語りつぐ会)では
大切な資料なのです。
是非、拝読して、私たちのレパートリーに入れたいと思います。
たとえば、次のような話は面白いですね。
-------以下産経新聞(2015.9.19.)記事より-------
奈良県編の箸墓(桜井市)にかかわる民話では、長者の男が貧乏な暮らしを願い、
「箸を捨てると天罰で貧乏になる」という言い伝えから毎日、箸や膳などを捨て、それが積もって箸墓になったという話や、
大峯山寺(天川村)では千手観音の功徳を説いた千手陀羅尼を唱えながら修行していた聖人の男が、
深い谷で大蛇の群れに襲われそうになったが、鬼に助けられる-という話などが紹介されている。
--------以上産経新聞記事より--------------------
では、みなさま、来週末、次のブログでお会いしましょう!
これから寒くなります。みなさま、お元気で!













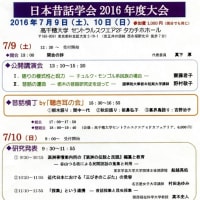






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます