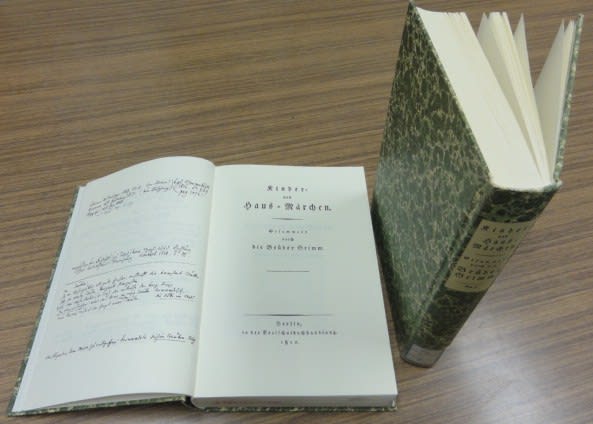最近はアイドルといえば、グループで登場しますよね。
それもなぜか48人なんですね。
AKB48、SKE48、NMB48、HKT48
こんなにもグループがあるのをご存知でしたか?
いずれも放送作家・作詞家である秋元康がプロデュースしたアイドルグループです。
活動拠点から命名されたそうです。
順に、秋葉原(東京)、栄(名古屋)、難波(大阪)、博多(福岡)のグループです。
AKihaBara、SaKaE、NaMBa、HaKaTa のグループです。
それから、秋葉原にはSDN48もあるそうです。
これはAKB48の別働隊で土曜日に出演するそうです。
SturDayNightに由来しているそうです。
さて、さて、奈良のNMN48とは?
ナーミンテラーズ(NaMiNtellers)48のことです。
このブログの定期読者はご存知ですよね。
ナーミン(奈良の民話)テラーズ(語り手たち)48人です。
今年で3年目になる
奈良教育大の「伝統と文化」教育プログラムの
「なら語りの入門講座」には20名の方が熱心に受講されました。

講師の村上さんの講義を聴く方々 104教室

図書館・絵本の広場でのお話会
この3期生の受講生からもナーミンテラーズが誕生しようとしています。
1期生、2期生から生まれたテラーズを合わせると、
なんと48名を越えるほどになるのです。
まさに、NMN48(エヌ・エム・エヌ・フォーティー・エイト)です。
今年夏も、奈良燈花会のころ「奈良民話祭り」にアイドルNMN48が出演します。
「歌って踊るアイドル」ではありませんよ。
「ナーミンのうた」は歌いますが、そのあとすてきな語りがあります。
応援のほどよろしくお願いします!!
それもなぜか48人なんですね。
AKB48、SKE48、NMB48、HKT48
こんなにもグループがあるのをご存知でしたか?
いずれも放送作家・作詞家である秋元康がプロデュースしたアイドルグループです。
活動拠点から命名されたそうです。
順に、秋葉原(東京)、栄(名古屋)、難波(大阪)、博多(福岡)のグループです。
AKihaBara、SaKaE、NaMBa、HaKaTa のグループです。
それから、秋葉原にはSDN48もあるそうです。
これはAKB48の別働隊で土曜日に出演するそうです。
SturDayNightに由来しているそうです。
さて、さて、奈良のNMN48とは?
ナーミンテラーズ(NaMiNtellers)48のことです。
このブログの定期読者はご存知ですよね。
ナーミン(奈良の民話)テラーズ(語り手たち)48人です。
今年で3年目になる
奈良教育大の「伝統と文化」教育プログラムの
「なら語りの入門講座」には20名の方が熱心に受講されました。

講師の村上さんの講義を聴く方々 104教室

図書館・絵本の広場でのお話会
この3期生の受講生からもナーミンテラーズが誕生しようとしています。
1期生、2期生から生まれたテラーズを合わせると、
なんと48名を越えるほどになるのです。
まさに、NMN48(エヌ・エム・エヌ・フォーティー・エイト)です。
今年夏も、奈良燈花会のころ「奈良民話祭り」にアイドルNMN48が出演します。
「歌って踊るアイドル」ではありませんよ。
「ナーミンのうた」は歌いますが、そのあとすてきな語りがあります。
応援のほどよろしくお願いします!!