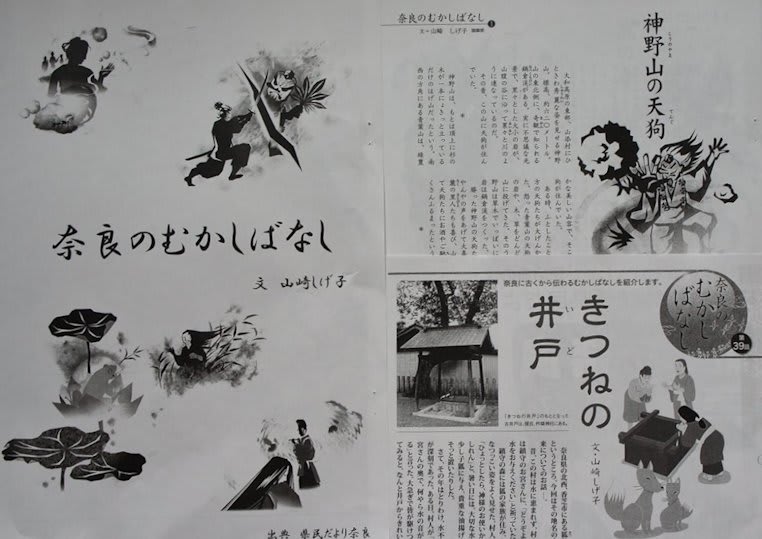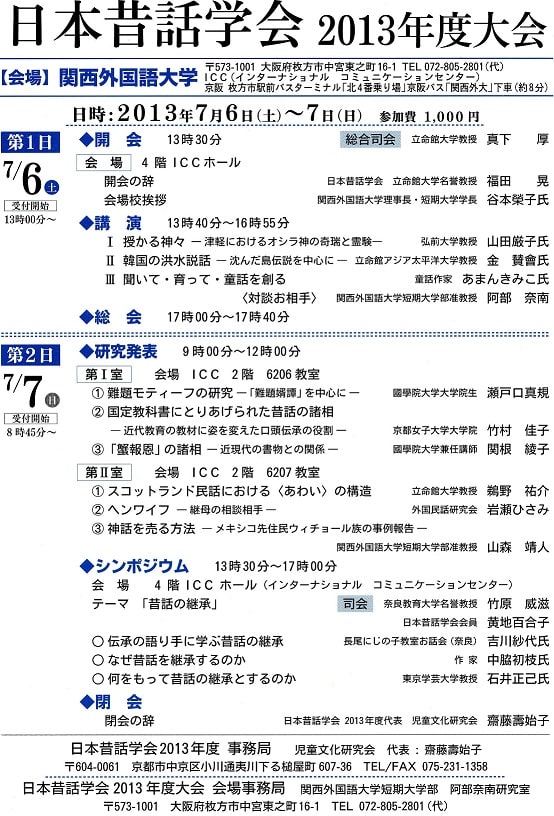奈良民話祭り2013は、盛会のうちに終了しました。
年々、少しずつ、参加者が増え、市民に定着しつつあります。
感謝をもって皆様に報告いたします。
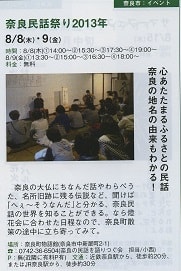
ぱーぷる8月号のEVENTに載せていただきました。

奈良新聞の8月8日の催しランンナップのイベントに載せていただきました。

語りに耳を傾ける人々

音声館のスタッフによるわらべ歌と手遊びに興じる人々

紙芝居に見入る子どもたち

夕方、燈花会のともしびに雰囲気満点の会場:奈良町物語館

8月8日にはNHK奈良放送局が「ならナビ」でニュースとして取り上げてくださいました。
奈良日々新聞にも記事が載るそうです。
ナーミンテラー(奈良の民話の語り手)のみなさま、お疲れでした。
そして、参加してくださった多くのみなさま、ありがとう、多謝、サンキュウ、ダンケ!
来年は5年目を迎えます。
奈良燈花会の風物詩として奈良県民に愛される「民話祭り」になりますよう
さらにナーミンテラーともども精進します!
---------------
さて、8月14日(水)には、
「第3回、エフエムハイホー ラジオ祭り」が
王寺駅前、リーベル王寺東館5Fりーべるホールで開催されます。
私が午後1時から30分間「奈良の民話を楽しむ」と題して講演します。
下記のサイトをご覧ください:
エフエムハイホー ラジオ祭り
ならまち、吉野、柳生のお話を語りつつ、
民話地図やこのほど出版された「子どもと家庭のための奈良の民話」も
話題にするつもりです。
よろしかったら、聴きに来てくださいね。
ところで、毎日暑いですね。
お元気でお過ごしください。
年々、少しずつ、参加者が増え、市民に定着しつつあります。
感謝をもって皆様に報告いたします。
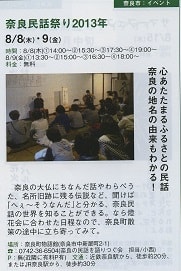
ぱーぷる8月号のEVENTに載せていただきました。

奈良新聞の8月8日の催しランンナップのイベントに載せていただきました。

語りに耳を傾ける人々

音声館のスタッフによるわらべ歌と手遊びに興じる人々

紙芝居に見入る子どもたち

夕方、燈花会のともしびに雰囲気満点の会場:奈良町物語館

8月8日にはNHK奈良放送局が「ならナビ」でニュースとして取り上げてくださいました。
奈良日々新聞にも記事が載るそうです。
ナーミンテラー(奈良の民話の語り手)のみなさま、お疲れでした。
そして、参加してくださった多くのみなさま、ありがとう、多謝、サンキュウ、ダンケ!
来年は5年目を迎えます。
奈良燈花会の風物詩として奈良県民に愛される「民話祭り」になりますよう
さらにナーミンテラーともども精進します!
---------------
さて、8月14日(水)には、
「第3回、エフエムハイホー ラジオ祭り」が
王寺駅前、リーベル王寺東館5Fりーべるホールで開催されます。
私が午後1時から30分間「奈良の民話を楽しむ」と題して講演します。
下記のサイトをご覧ください:
エフエムハイホー ラジオ祭り
ならまち、吉野、柳生のお話を語りつつ、
民話地図やこのほど出版された「子どもと家庭のための奈良の民話」も
話題にするつもりです。
よろしかったら、聴きに来てくださいね。
ところで、毎日暑いですね。
お元気でお過ごしください。