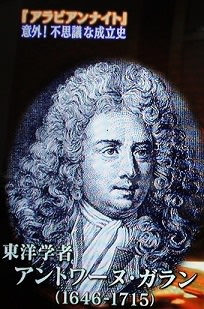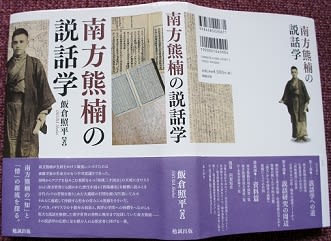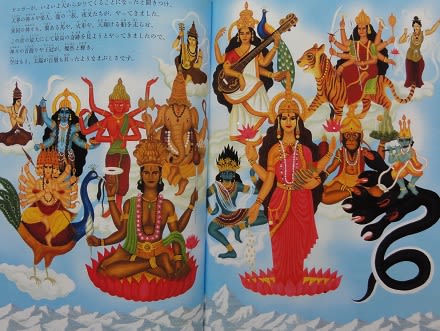すっかり秋らしくなってきましたね。
梅花女子大のキャンバスも見事な錦秋です。

地面には枯葉が敷き詰められています。
ところで、みなさま、イヴ・モンタンの歌う「枯葉」をご存知ですね。
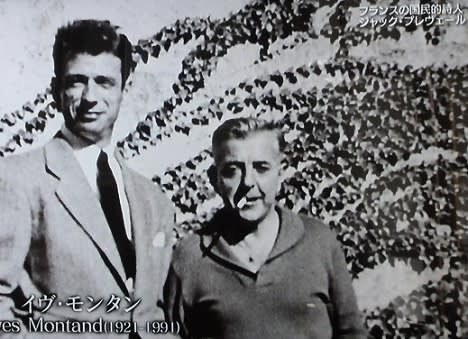
(NHK番組「SONGSズペシャル 松任谷由実」より)
左手はイヴ・モンタン、右手は、作詞者のジャック・プレヴェールです。
ジャック・プレヴェールは、フランスの国民的詩人で、
松任谷由実は、この詩人の詩に若き日から親しんでいたそうです。

(NHKの同上番組より)
松任谷由実(ユーミン)は、
高校一年の頃に小学校時代の同級生男子が筋ジストロフィーで亡くなった時
その死を悼(いた)み、「若くして死ぬって、どういうことかな」と思いめぐらし、
高校3年の時、「ひこうき雲」という歌を作ったそうです。
白い坂道が 空まで続いていた。
ゆらゆら かげろうがあの子を包む。
誰も気づかず ただひとり
あの子は昇っていく。
何もおそれない、そして舞い上がる。
空を憧れて 空をかけていく。
あの子の命はひこうき雲。
(作詞・作曲:荒井由美 1973年)
実にすばらしいレクイエム(鎮魂歌)です。
のちに、これは荒井由実のファースト・アルバム(2000年)のタイトル曲になっています。
作曲からちょうど40年目に、なんと宮崎駿がこの曲を映画「風立ぬ」の主題曲に採用したのです。

(NHKの同上番組より)
皆さん、是非、宮崎駿監督の最後の作品「風立ぬ」も見てくださいね。
ひたむきな愛!
自分の夢に忠実にまっすぐすすむ意志!
個人の人生に襲いかかる悲痛な運命!
秘密のない国民が主人公の政治の尊さ!!
みなさんは、何を読みとられるでしょうか?
今日は、「枯葉」 → 「ひこうき雲」 → 「風立ぬ」
の三題噺でした。
では、次回のブログでお会いしましょう!
梅花女子大のキャンバスも見事な錦秋です。

地面には枯葉が敷き詰められています。
ところで、みなさま、イヴ・モンタンの歌う「枯葉」をご存知ですね。
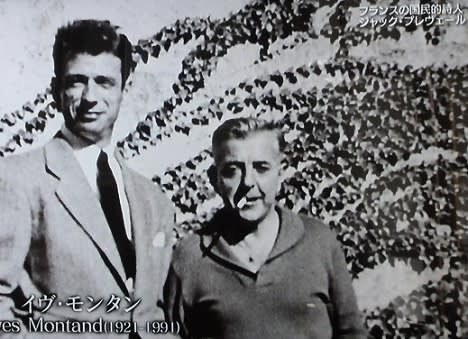
(NHK番組「SONGSズペシャル 松任谷由実」より)
左手はイヴ・モンタン、右手は、作詞者のジャック・プレヴェールです。
ジャック・プレヴェールは、フランスの国民的詩人で、
松任谷由実は、この詩人の詩に若き日から親しんでいたそうです。

(NHKの同上番組より)
松任谷由実(ユーミン)は、
高校一年の頃に小学校時代の同級生男子が筋ジストロフィーで亡くなった時
その死を悼(いた)み、「若くして死ぬって、どういうことかな」と思いめぐらし、
高校3年の時、「ひこうき雲」という歌を作ったそうです。
白い坂道が 空まで続いていた。
ゆらゆら かげろうがあの子を包む。
誰も気づかず ただひとり
あの子は昇っていく。
何もおそれない、そして舞い上がる。
空を憧れて 空をかけていく。
あの子の命はひこうき雲。
(作詞・作曲:荒井由美 1973年)
実にすばらしいレクイエム(鎮魂歌)です。
のちに、これは荒井由実のファースト・アルバム(2000年)のタイトル曲になっています。
作曲からちょうど40年目に、なんと宮崎駿がこの曲を映画「風立ぬ」の主題曲に採用したのです。

(NHKの同上番組より)
皆さん、是非、宮崎駿監督の最後の作品「風立ぬ」も見てくださいね。
ひたむきな愛!
自分の夢に忠実にまっすぐすすむ意志!
個人の人生に襲いかかる悲痛な運命!
秘密のない国民が主人公の政治の尊さ!!
みなさんは、何を読みとられるでしょうか?
今日は、「枯葉」 → 「ひこうき雲」 → 「風立ぬ」
の三題噺でした。
では、次回のブログでお会いしましょう!