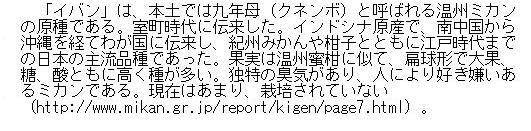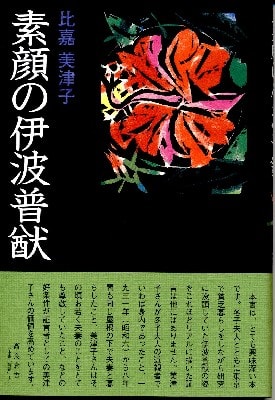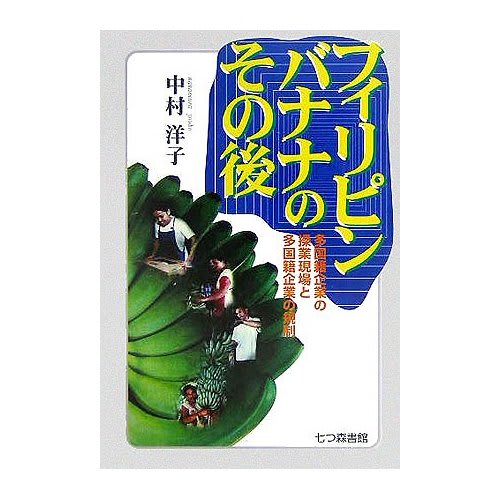9日間の、竹富島の種子取(タントゥイ)祭のクライマックスは、「庚寅」(かのえ・とら)に当たる7日目と、「辛卯」(かのと・う)に当たる8日目の奉納芸能である。
7日目、玻座間(はざま)村では、北東にある「世持御嶽」(ユームチ・ウタキ)の神司による祈願から行事は始まる。午前5時半頃である。同じ時刻、村の東にある弥勒奉安殿では、与那国家、大山家といったこの地の名家の「御主前」(ウ・シュ・マイ=当主のこと)や、地元名士たちが、「弥勒起こし」(ミルク・ウクシ)を行う。弥勒様に睡眠から起きていただくのである。
大山家は、琉球王朝時代には豪農であり、代々、「勢頭座敷」(セト・ザシキ)とか、「筑登之座敷」(チクドゥン・ザシキ)とかいった高い位階を琉球王から付与されていたとされる。
大山家の当主を褒め称える「世曳き」(ユー・ヒキ)という狂言が竹富島にはある。この狂言は、竹富弁で語られることが多いい、他の竹富島の狂言とは異なり、沖縄本島の首里言葉が使われている。それは、琉球王に経緯を評して、位階を与えられたことへの感謝の狂言である。位階を表す言葉は、「御座敷」(ウ・ザッシュ」である。この位階を与えられたことの感謝を本島からきた「与人」(ユン・チュ=役人)に表すのである。
狂言では、<「「うひな」(誉れの)「うざっしゅん」(御座敷の)「すでぃがふどぅ」(位階までいただき)「しゃびる」」(大変果報者である)>と謳われている。ただし、役人への感謝だけでなく、子供とともに豊作を祝う言葉も出されている。このような、豊作を祈願する祈りに、前もって豊作を祝う種類の芸能は、「予祝芸能」と呼ばれている。
狂言「世曳き」は、琉球王朝時代の支配の片鱗を伝えるものである。
おそらくは、首里における支配者の命を受けた劇作家が、竹富島向けにこの狂言を作ったのであろう。狂言が首里言葉で演じられることからそう推察される。首里の権力者が、税の徴収を大山家に命じ、その義務をはたしたご褒美として、大山家に位階を授ける。そのことを大山家の当主が感謝して歌い、踊るという場面、そして、豊作の報告を村の最高権力者の与人に行うという設定が、そうした事情を物語っている。税徴収の報酬としての位階、それを祝う狂言を、村の大事なお祭りで村人演じさせる。いつの時代も、勲章で人を釣り、それを祝う民衆を浮き彫りにするという劇を演じさせるということは、古今東西の権力者の共通の行動様式であった。
「世曳き」の「世」(ユー)は「豊作」、つまり、「富」を意味する。
「曳き」とは、文字通り、「引っ張ってくる」という意味であろう。海の彼方から「富を引っ張ってくる」のである。そして、その力が大山家と与那国家には備わっているとの信仰があったのである。つまり、神様のような両家の指示に民衆は従えというのである。
沖縄では、神様は海からくる。それが、「ニライカナイ」信仰である。それを体現したのが、弥勒(みろく)神である。つまり、八重山では、弥勒は、仏ではなく神である。
海の彼方から富をもたらす神様が弥勒様であった。
ここで、大事なことは、この弥勒様が、与那国家と大山家だけに宿るとされていたことである。芸能を通じて、権力の忠実な配下を神的な位置につけ、芸能を見る民衆に配下への尊敬の念を植えつける。これが、いわゆる民衆芸能なるものの、哀しい真実である。私には、村の芸能が、すべて自然発生したものであるとは思われない。葵祭然り、天神りしかり、いわんや神戸祭はまったく民衆の創設ではない。
民衆芸能のすごさを重々承知している積もりではあるが、伝統的民衆芸能の洗脳作用にいま少し、人々は注意を向けた方がいいと、私は感じる。
種子取祭の7日目の早朝、大山家の当主が弥勒様を起こすという儀式は、富を曳いて下さる弥勒様を眠りから呼び起こす行為に他ならい。
八重山の弥勒は、安南から伝わってきたと言われている。竹富島の弥勒伝説では、仲道家の先祖が、海岸で弥勒の仮面を拾い、それを家に祀って信仰していたが、後にその面を与那国家に譲ったとされている。これが何を意味しているのかは分からない。なんらかの権力関係の変化があったのだろう。いまでも、祭のときに弥勒の面を被ることができるのは、与那国家と大山家の当主だけである。
「みるくうくし」(弥勒起こし)は、「みるく節」(ミルクブシ)の歌で弥勒様の起床を促すことから始まる。弥勒は起きてきて、「シーザ」(二才=年長の青年のこと)、大勢の供、子供を連れて登場する。
ちなみに、我々がいう「青二才」は、先輩(二才)にもなれない未熟者という意味である。
弥勒への捧げ物をもった供、シーザが弥勒の周りを回り、さらに、シーザ4人による踊りが奉納され、「弥勒節、ヤーラヨ節」に送られて、弥勒は退場する。
「弥勒節」の作者は特定されている。1790年代の八重山士族の大浜用倫が作者である。弥勒節は、石垣島と竹富島では同じ節である(喜舎場永(きしゃば・えいじゅん)編『八重山民謡誌』東京堂書店 大正13年)。男性合唱のみからなり、三線は用いず、笛と太鼓による伴奏だけであり、厳粛な歌である。
さて、伝承によれば、島の6つ村長たちが、栽培作物の選択、したがって、いつ種子を蒔くかを争い、決着がついたことを祝う「種子取祭」が何故、「種子蒔き」の祭りになるのだろうか。「種子を取る」ことと、[種子を蒔く」こととは、まったく違う行為のはずである。しかし、ここに、離島の哀しさが表現されているのである。この離島では、「種子取り」とは、海の向こうから「種子を貰う」のである。このことを推測させるものとして、仲筋村に伝わる「天人」(アマンチ」という狂言がある。
ただし、この狂言も「ウチナーグチ」(沖縄言葉=首里言葉)が使われており、首里の支配者が、竹富島の人々を支配下に置いたことの宣言と受け取ることのできる構成になっている。
「天人」(アマンチ)とは、琉球王朝の神話に登場する「アマミキヨ」のことである。国造りの神、稲作を始めた神とされる。
村の長老が、栽培すべき穀物の種子を頂けるように祈るために、海岸にやってくる。そこに、「天人」が、作物の種子を村人に与えようと、海を渡って島にやってくる。両者は、海岸で出会い、長老は、種子を頂き、作物の作り方を天人から教わる。つまり、「種子取り」に成功したのである。
天人が去った後、農作業を始めるべく、「マミドゥ」という農作業を表現する舞踏が演じられる。その際、長老が、「マミドゥ」を踊る若者たちに向かって、「筑登之・親雲上」(チクドゥン・ベーチン」と声をかける。「筑登之」も「親雲上」も、琉球王朝時代に、国王から授かる高位の位階である。おそらくは、首里の国王から高位階を授けてもらえるように頑張れと呼びかけているのであろう。つねに、王朝に恩義を感じ、王朝の寵愛を求めるという設定は、けっして地元発のものではないだろう。首里権力が、芸能を通じて竹富島の民衆の忠誠心を煽ったのである。
ただし、ここまで書いてしまうと慌てて訂正しなければならない。これは、琉球王朝時代のことであり、現在ではまったく従属者のものではなく、村人が素直に古典芸能の幽玄さに酔っているのであり、こうした芸能を通じて、失われつつある人々の共感を呼び起こそうとしている事は疑いえない。
与那国家も大山家も、いまでは、断じて権力の走狗ではない。なんら権力をもたず、ひたすら、伝統文化を保持・発展させようと、両家を含めて、島人は粉骨砕身しているのである。与那国家の当主は、琉球大学で教鞭を執っていて、祖先伝来の屋敷を町に寄進し、旧家は一般に公開されている。
両家の当主は、祭の時はもとより、伝統文化の維持・発展にとてつもなく大きなエネルギーを無心で注いでおられる。低い次元で、そうした尊い努力を私は揶揄しているわけではない。誤解のないように。
今回の資料は、全国竹富島文化協会のウェブ・サイトからその多くを参照した。