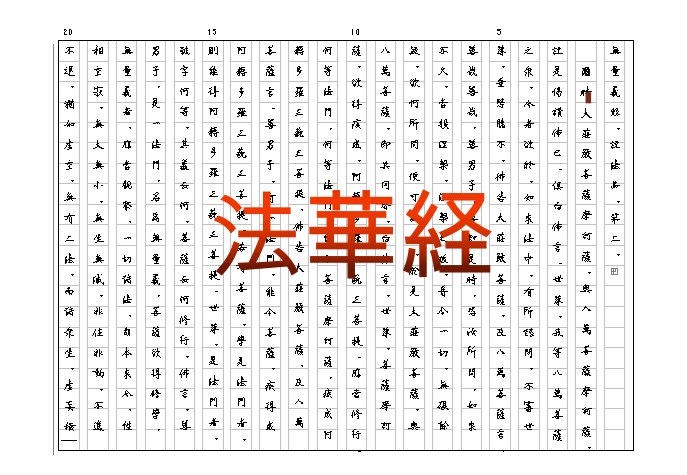小乗仏教の利己性に不満をもつ人たちの大乗仏教の運動がインドで紀元前後に起こり、これが中国、朝鮮に伝わったとされる。
この運動の中で、『法華経』、『華厳経』、『無量寿経』がまず形成されたと先述の末木氏は言う(『日本仏教史』新潮文庫)。
大乗仏教が本格的に中国に定着するのは4世紀の道安(どうあん、312~385年頃)の努力と、5世紀初め、西域から長安にきて教典の漢訳に画期的な業績を残した鳩摩羅什(くまらじゅう、350~409年頃)の業績によることが多いと同氏は説明している。時は中国の南北朝時代であった。
朝鮮半島では、北の高句麗に372年、南の百済には中国の南朝から384年に伝わった。新羅も早くから伝わっていたはずであるが、公的に認可されたのは527年である。百済でも仏教が盛んになったのは、6世紀初めの聖王のときであった。末木氏は、その意味で、日本に百済から仏教が伝来したのは、538年で、最新の文化であったと言う。
聖徳太子(574~622年)信仰の一つに、彼が南岳慧思(なんがくえし、515~577年)の生まれ変わりであったというものがある。
太子の生年と慧思の没年が異なり、太子が生まれた年にはまだ慧思は生きていたので、この説は明らかに間違いなのだが、この説は、慧思が当時、中国の仏教界ではいかに大きい存在であったかを示している。
慧思は、天台宗を開いた随の天台智(てんだいちぎ、538~597年)の師であり、法華経解説者、および、法華経に基づく禅定の実践者として著名な人であった。それほどの著名な慧思が日本で聖徳太子として生まれ変わり、日本に仏教を広めたのであるとの説が奈良時代には語られていた。
この説を広めたのは、日本に苦難の末に天平勝宝5年(753年)に到着した鑑真の弟子、思託(したく)であったと末木氏は断定している。
思託は、日本最古の僧伝、『延暦僧録』や、『大和上鑑真伝』の著者である。太子伝説は、平安時代の延喜17年(917年)に編纂された『聖徳太子伝暦』(藤原兼輔撰)に収録されている。
その太子が『三経義疏』(さんぎょうしょ)を著したことは前回で述べたが、この三経の中に『法華経』が入っていた。
そして、天台宗は、この『法華経』に基づいたものである。
中国の天台の著作を日本にもたらしたのは、5回の日本への渡航失敗と失明の末に、やっと、日本に上陸した鑑真がもたらしたものである。鑑真は大仏の前で聖武天皇に菩薩戒を授けた。この菩薩戒というのは、鳩摩羅什が訳した『梵網経」(ぼんもうきょう)という、慮舎那仏の蓮華台蔵世界(巻頭)、菩薩の修行(上巻)、菩薩の戒(下巻)を説いたもので、大仏建立はこの経典によると言われている。
この菩薩戒は、元来が、在家者向けのものであったのに、出家者向けに替えてしまったのが最澄である。戒律を重視したからであると、末木氏は解釈する。
初期大乗仏教の骨格をなすものが、『法華経』と『華厳経』であった。
紀元2世紀頃には作成されていたと考えられている。ただし、多くの仏教経典と同じく、『法華経』といっても単純なものではない。古層と新層があって複雑な構成をもっている。
総じて、小乗仏教や原始仏教に比べて大乗仏教の経典は分かりにくい。
これは、江戸時代の大坂の天才、富永仲基(とみながなかもと、1715~1746年)が喝破したように、大乗仏典は釈迦自身の言葉だけでなく、後代の人間が次々に書き加えてできあがったものだからである。複雑さの度合いは年代が経つにつれて増加する。
富永は、大乗は仏ではない。架空のものである(大乗非仏論、『出定後記』)とした。
明治になって、丹波出身の村上専精(むらかみせんしょう、1851~1929年)も大乗非仏論を唱えたが、その罪で真宗大谷派の僧籍を剥奪された。彼は東京帝大教授で、『日本仏教史綱要』、『仏教統一論』の著者である。
さらに、漢訳という変容を仏教経典は被る。当然、経典には矛盾が出てくる。実際には、経典の成立時代背景の差が、そうした違いを生むのに、中国の仏教学者たちは、年齢毎の釈迦の悟りの境地の深さの差として経典の違いを理解しようとした。経典のことごとくが、釈迦の真言だと理解しようとしたのである。
代表的な作業は、天台宗の始祖、天台智である。そして、『法華経』が釈迦の最晩年のものとされて、最高の悟りの経典とされた。
通常、『法華経』という時、鳩摩羅什が漢訳した『妙法蓮華経』(みょうほうれんげきょう)を指している。まさに、正しい教えとは「白い蓮華の花」(サッダルマ・プンダリーカ)、つまり「正しい教え」(サッダルマ)、「白い蓮華」(プンダリーカ)なのである。
比較的短い『法華経』は、「方便」という考え方を導入している。「方便」とは「巧みな手段」という意味である。
釈迦は、聴衆の理解力に応じて説法方法を変えた。これを方便という。
したがって、方便は究極の真理ではなく、そこに至る手段だというのである。大乗は小乗と違って広く衆生(しゅうじょう)の救済を目指す。それに対して、小乗は、自己の救済のみを願う。仏の弟子(声聞、しょうもん)なのに、縁覚(えんがく)といって自分一人で悟ったとか、自分の利益しか考えないものである。
このように小乗を貶め、大乗の優越さを誇りながらも、『法華経』の編纂者たちは、大乗と小乗との合一を目指していた。その重要な概念が「方便」であった。理解力で劣る小乗人に説明したのが小乗の教えであり、それはより正しい真理に導く「方便」なのである。まさに「嘘も方便なり」である。
あらゆる宗派は、最終的には一切衆生が同じように仏になる。それこそ、『法華経』が示す道筋であるとしたのである。
「方便」を、『法華経』は比喩を駆使して説明する。「火宅」の比喩がある。火宅とは火事になった家のことである。ある長者の家が火事になった。長者はいち早く地獄の火宅から外部の安全な地に逃れたが、愛する3人の子供たちはまだ火事に気付かず、家の中で遊んでいる。仕方なく、長者は、子供たちにそれぞれ別の呼びかけ方(方便)をした。それぞれに羊の車、鹿の車、牛の車をあげるから外に出てこいというのである。3人の子供たちは、羊、鹿、牛とそれぞれ好む車が異なっていたからである。3人が無事に外に出てくると、長者は、子供たち全員に大きな白い牛の車(大白牛車)を与えたというのである。
つまり、長者が仏陀、3人の子供たちが声聞、縁覚、菩薩である。声聞がもっとも修行が足らず、縁覚が少しまし、菩薩がもっとも修行が進んでいる。修行段階に応じて、羊、鹿、牛と乗る車が異なっている。羊よりも鹿、鹿よりも牛が高級である。しかし、いずれの車も乗り物としては小さい(小乗)。そして最後は、彼らは全員を収容できる、白い牛の大きな車(大乗)に乗って唯一の真理に向かって進むのである。つまり、大乗とは、際限なく分裂をして小さくなってしまった小乗たちを包み込む大きな車なのである。こうした比喩を扱ったのが『法華経鵜の第一部である。
第二部がまたすごい。インドで生まれ、菩提樹の下で悟りを開いた仏陀は、真実の仏陀ではない。永遠の仏陀の一つの現れでしかない、というのである。
真実の仏陀は久遠の昔から存在し、すでに成仏していた( 久遠実成仏、くおんじつじょう)。そして、絶えず、手を替え、品を替えて教えを説き続けていたのであると。
因みに、『法華経』では、話のまとまり、章別構成を、「品」(ぼん)という用語で行っている。第一部分は「方便品」(ほうべんぼん)、第二部分は、「法師品」(ほっしぼん)、「嘱累品」(ぞくるいぼん)、「如来寿量品」(むりょうじゅりょうぼん)、さらに第三部で6つの「品」が語られる。
第二部では、迫害に耐えて『法華経』を護持してきた法師、菩薩たちの実践が語られる。
有名な個所では、「常不軽菩薩品」(じょうふきょうぼさつぼん)がある。どれほど人々から軽蔑されても、そうした人々に対して「我、深く汝らを敬う」と語り続けた菩薩の話である。「堤婆達多品」(だいばだったぼん)も有名である。これは悪人の堤婆達多が回心して成仏した話である。
第三部には、「観世音菩薩普門品」(かんぜおんぼさつふもんぼん)がある。
この「品」は後に、『観音経』として独立する。「薬王菩薩本事品」(やくおうぼさつほんじぼん)は後に「捨身供養」(しゃしんくよう)の根拠になったものである。つまり、薬王菩薩が両腕を燃やして仏を供養したという説話である。
『法華経』を最終的な最高の経典として強く主張したのは先述の天台智である。彼は本来の永遠の仏陀の教えを「本門」といい、時々に姿を変えて本仏から派生した(垂迹、すいじゃく)仏の教えを「迹門」(しゃもん)と呼んだ。
さらに一切の存在を「空」(くう)、「仮」(け)、「中」(ちゅう)の三次元から説明した。一切存在は平等である。これを彼は、「空」と呼んだ。
一切存在は個別性をもっている。これを彼は「仮」と呼んだ。
これら2つは、しかし、それぞれが一面的なものでしかない。というよりも対立的な概念である。存在するもののすべては「平等である」。同時に存在するすべてのものは個別性という「差別性」をもつ。2つは相互に矛盾している。そうした相反するものを統一的に止揚する概念、それが「中」である。これを「三諦円融」(さんていえんゆう)と名付け、そうした思想が『法華経』では説かれているというのである。
弁証法は、ソクラテスによって許否された。彼よりも前のギリシャ哲学は、しかし、弁証法が基本であった。『法華経』もまた古代ギリシャの東方、つまり、中国から見た西方の古代思想を受け継いでいるのである。
この運動の中で、『法華経』、『華厳経』、『無量寿経』がまず形成されたと先述の末木氏は言う(『日本仏教史』新潮文庫)。
大乗仏教が本格的に中国に定着するのは4世紀の道安(どうあん、312~385年頃)の努力と、5世紀初め、西域から長安にきて教典の漢訳に画期的な業績を残した鳩摩羅什(くまらじゅう、350~409年頃)の業績によることが多いと同氏は説明している。時は中国の南北朝時代であった。
朝鮮半島では、北の高句麗に372年、南の百済には中国の南朝から384年に伝わった。新羅も早くから伝わっていたはずであるが、公的に認可されたのは527年である。百済でも仏教が盛んになったのは、6世紀初めの聖王のときであった。末木氏は、その意味で、日本に百済から仏教が伝来したのは、538年で、最新の文化であったと言う。
聖徳太子(574~622年)信仰の一つに、彼が南岳慧思(なんがくえし、515~577年)の生まれ変わりであったというものがある。
太子の生年と慧思の没年が異なり、太子が生まれた年にはまだ慧思は生きていたので、この説は明らかに間違いなのだが、この説は、慧思が当時、中国の仏教界ではいかに大きい存在であったかを示している。
慧思は、天台宗を開いた随の天台智(てんだいちぎ、538~597年)の師であり、法華経解説者、および、法華経に基づく禅定の実践者として著名な人であった。それほどの著名な慧思が日本で聖徳太子として生まれ変わり、日本に仏教を広めたのであるとの説が奈良時代には語られていた。
この説を広めたのは、日本に苦難の末に天平勝宝5年(753年)に到着した鑑真の弟子、思託(したく)であったと末木氏は断定している。
思託は、日本最古の僧伝、『延暦僧録』や、『大和上鑑真伝』の著者である。太子伝説は、平安時代の延喜17年(917年)に編纂された『聖徳太子伝暦』(藤原兼輔撰)に収録されている。
その太子が『三経義疏』(さんぎょうしょ)を著したことは前回で述べたが、この三経の中に『法華経』が入っていた。
そして、天台宗は、この『法華経』に基づいたものである。
中国の天台の著作を日本にもたらしたのは、5回の日本への渡航失敗と失明の末に、やっと、日本に上陸した鑑真がもたらしたものである。鑑真は大仏の前で聖武天皇に菩薩戒を授けた。この菩薩戒というのは、鳩摩羅什が訳した『梵網経」(ぼんもうきょう)という、慮舎那仏の蓮華台蔵世界(巻頭)、菩薩の修行(上巻)、菩薩の戒(下巻)を説いたもので、大仏建立はこの経典によると言われている。
この菩薩戒は、元来が、在家者向けのものであったのに、出家者向けに替えてしまったのが最澄である。戒律を重視したからであると、末木氏は解釈する。
初期大乗仏教の骨格をなすものが、『法華経』と『華厳経』であった。
紀元2世紀頃には作成されていたと考えられている。ただし、多くの仏教経典と同じく、『法華経』といっても単純なものではない。古層と新層があって複雑な構成をもっている。
総じて、小乗仏教や原始仏教に比べて大乗仏教の経典は分かりにくい。
これは、江戸時代の大坂の天才、富永仲基(とみながなかもと、1715~1746年)が喝破したように、大乗仏典は釈迦自身の言葉だけでなく、後代の人間が次々に書き加えてできあがったものだからである。複雑さの度合いは年代が経つにつれて増加する。
富永は、大乗は仏ではない。架空のものである(大乗非仏論、『出定後記』)とした。
明治になって、丹波出身の村上専精(むらかみせんしょう、1851~1929年)も大乗非仏論を唱えたが、その罪で真宗大谷派の僧籍を剥奪された。彼は東京帝大教授で、『日本仏教史綱要』、『仏教統一論』の著者である。
さらに、漢訳という変容を仏教経典は被る。当然、経典には矛盾が出てくる。実際には、経典の成立時代背景の差が、そうした違いを生むのに、中国の仏教学者たちは、年齢毎の釈迦の悟りの境地の深さの差として経典の違いを理解しようとした。経典のことごとくが、釈迦の真言だと理解しようとしたのである。
代表的な作業は、天台宗の始祖、天台智である。そして、『法華経』が釈迦の最晩年のものとされて、最高の悟りの経典とされた。
通常、『法華経』という時、鳩摩羅什が漢訳した『妙法蓮華経』(みょうほうれんげきょう)を指している。まさに、正しい教えとは「白い蓮華の花」(サッダルマ・プンダリーカ)、つまり「正しい教え」(サッダルマ)、「白い蓮華」(プンダリーカ)なのである。
比較的短い『法華経』は、「方便」という考え方を導入している。「方便」とは「巧みな手段」という意味である。
釈迦は、聴衆の理解力に応じて説法方法を変えた。これを方便という。
したがって、方便は究極の真理ではなく、そこに至る手段だというのである。大乗は小乗と違って広く衆生(しゅうじょう)の救済を目指す。それに対して、小乗は、自己の救済のみを願う。仏の弟子(声聞、しょうもん)なのに、縁覚(えんがく)といって自分一人で悟ったとか、自分の利益しか考えないものである。
このように小乗を貶め、大乗の優越さを誇りながらも、『法華経』の編纂者たちは、大乗と小乗との合一を目指していた。その重要な概念が「方便」であった。理解力で劣る小乗人に説明したのが小乗の教えであり、それはより正しい真理に導く「方便」なのである。まさに「嘘も方便なり」である。
あらゆる宗派は、最終的には一切衆生が同じように仏になる。それこそ、『法華経』が示す道筋であるとしたのである。
「方便」を、『法華経』は比喩を駆使して説明する。「火宅」の比喩がある。火宅とは火事になった家のことである。ある長者の家が火事になった。長者はいち早く地獄の火宅から外部の安全な地に逃れたが、愛する3人の子供たちはまだ火事に気付かず、家の中で遊んでいる。仕方なく、長者は、子供たちにそれぞれ別の呼びかけ方(方便)をした。それぞれに羊の車、鹿の車、牛の車をあげるから外に出てこいというのである。3人の子供たちは、羊、鹿、牛とそれぞれ好む車が異なっていたからである。3人が無事に外に出てくると、長者は、子供たち全員に大きな白い牛の車(大白牛車)を与えたというのである。
つまり、長者が仏陀、3人の子供たちが声聞、縁覚、菩薩である。声聞がもっとも修行が足らず、縁覚が少しまし、菩薩がもっとも修行が進んでいる。修行段階に応じて、羊、鹿、牛と乗る車が異なっている。羊よりも鹿、鹿よりも牛が高級である。しかし、いずれの車も乗り物としては小さい(小乗)。そして最後は、彼らは全員を収容できる、白い牛の大きな車(大乗)に乗って唯一の真理に向かって進むのである。つまり、大乗とは、際限なく分裂をして小さくなってしまった小乗たちを包み込む大きな車なのである。こうした比喩を扱ったのが『法華経鵜の第一部である。
第二部がまたすごい。インドで生まれ、菩提樹の下で悟りを開いた仏陀は、真実の仏陀ではない。永遠の仏陀の一つの現れでしかない、というのである。
真実の仏陀は久遠の昔から存在し、すでに成仏していた( 久遠実成仏、くおんじつじょう)。そして、絶えず、手を替え、品を替えて教えを説き続けていたのであると。
因みに、『法華経』では、話のまとまり、章別構成を、「品」(ぼん)という用語で行っている。第一部分は「方便品」(ほうべんぼん)、第二部分は、「法師品」(ほっしぼん)、「嘱累品」(ぞくるいぼん)、「如来寿量品」(むりょうじゅりょうぼん)、さらに第三部で6つの「品」が語られる。
第二部では、迫害に耐えて『法華経』を護持してきた法師、菩薩たちの実践が語られる。
有名な個所では、「常不軽菩薩品」(じょうふきょうぼさつぼん)がある。どれほど人々から軽蔑されても、そうした人々に対して「我、深く汝らを敬う」と語り続けた菩薩の話である。「堤婆達多品」(だいばだったぼん)も有名である。これは悪人の堤婆達多が回心して成仏した話である。
第三部には、「観世音菩薩普門品」(かんぜおんぼさつふもんぼん)がある。
この「品」は後に、『観音経』として独立する。「薬王菩薩本事品」(やくおうぼさつほんじぼん)は後に「捨身供養」(しゃしんくよう)の根拠になったものである。つまり、薬王菩薩が両腕を燃やして仏を供養したという説話である。
『法華経』を最終的な最高の経典として強く主張したのは先述の天台智である。彼は本来の永遠の仏陀の教えを「本門」といい、時々に姿を変えて本仏から派生した(垂迹、すいじゃく)仏の教えを「迹門」(しゃもん)と呼んだ。
さらに一切の存在を「空」(くう)、「仮」(け)、「中」(ちゅう)の三次元から説明した。一切存在は平等である。これを彼は、「空」と呼んだ。
一切存在は個別性をもっている。これを彼は「仮」と呼んだ。
これら2つは、しかし、それぞれが一面的なものでしかない。というよりも対立的な概念である。存在するもののすべては「平等である」。同時に存在するすべてのものは個別性という「差別性」をもつ。2つは相互に矛盾している。そうした相反するものを統一的に止揚する概念、それが「中」である。これを「三諦円融」(さんていえんゆう)と名付け、そうした思想が『法華経』では説かれているというのである。
弁証法は、ソクラテスによって許否された。彼よりも前のギリシャ哲学は、しかし、弁証法が基本であった。『法華経』もまた古代ギリシャの東方、つまり、中国から見た西方の古代思想を受け継いでいるのである。