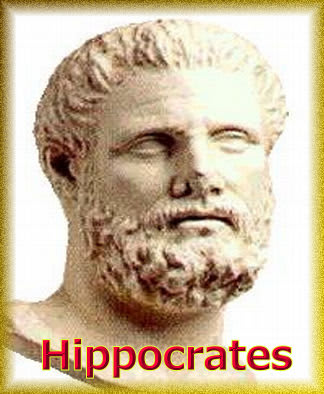
Hic Rhodos, hic salta! (ここがロードス島だ、ここで跳べ!)
マルクス『資本論』の貨幣論で出てくる言葉である。

元々は、イソップ寓話に収められた「ほら吹き男」の話に出てくる言葉である。

古代競技のある選手が、遠征先から帰ってきて自慢話をし、「おれはロドス島では、五輪選手も及ばないような大跳躍をした。皆がロドス島へ行くことがあれば、その大跳躍を見た観客が快く証言してくれるだろう」と言ったところ、それを聞いていたうちの一人が、「そんな証言は要らない。君が大跳躍をしたと言うなら、ここがロドスだ、ここで跳べ」
と言ったという話である。
ロードス島(Rhodes)はエーゲ海に実在するギリシャ領の島であるが、イソップの寓話を語る際には「ロドス」と記すことが多い(http://www6.plala.or.jp/symbell/book/story.htm ;http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q119440446より)。
堀江忠男は、Hic Rhodos, hic salta! を、「ここがロードス島だ、ここで跳べ!」ではなく、「ここがロードス島だ、ここで踊れ!」と訳している(『マルクス経済学と現実』学文社)。
堀江忠男は、その著、『弁証法経済学批判』のなかで、意図的に「跳べ」ではなく「踊れ」を選択したことの理由を述べている。
「余談だが、ここのHic Rhodos, hic salta! は、「ここがロードス島だ、ここで跳べ」と訳されている場合が多いのに、「ここで踊れ」と訳したのは次の理由からだ。ヘーゲルの『法の哲学』の序文に Hic Rhodos, hic saltus. という言葉がある。これが「ここがロードスだ、ここで跳べ」である。これは『イソップ物語』に出てくる寓話の一節で、あるほら吹きがロードス島でものすごい飛躍をしたと自慢したので、聞いた人が「ほんとだったら、ここがロードス島だと思って、跳んで見せろ」といったら、参ってしまったという話だ。
さて、ヘーゲルはついで「さきの慣用句はすこし変えればこう聞こえるだろう。Hier ist die Rose, hier tanze! これがローズ(ばら)だ、ここで踊れ!」(以上、両文とも Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, HW, 7, S. 26.にある。二章(8)の資料 『世界の名著――ヘーゲル』171~3ページ参照。)これをラテン語に書きなおせば Hic rodon, hic salta! である。マルクスはおそらくこの両方を知っていて、Hic Rhodos, hic salta! 「……踊れ」と書いたのであろう」。

『世界の名著35ヘーゲル』を見てみると、 Hic Rhodos, hic saltus.(ここがロドスだ、ここで跳べ)には、次のような注が付いている。
「『イソップ物語』にあるほら吹きが、ロドス島でものすごい跳躍をやらかしたこと、おまけにそれを見ていた証人がいたことを自慢したので、聞いていた人が「お前さん、もしそれがほんとうなら、証人なんかいらない、ここがロドスだ、ここで跳べばいい」といった話がある」。
また、「ここにローズ(薔薇)がある、ここで踊れ。」(Hier ist die Rose, hier tanze!) には、次のような注が付いている。
「ギリシア語のロドス(島の名)をロドン(ばらの花)、ラテン語の saltus(跳べ)をsalta(踊れ)に「すこし変え」たしゃれ。ヘーゲルはここにギリシア語もラテン語も記してはいないが」。
『資本論』では、Hic Rhodos, hic salta! となっているのに対して、ヘーゲルの『法の哲学』では、Hic Rhodos, hic saltus! となっている。
"saltus" と "salta" の違いについて、森田信也(東洋大教授)は次のような見解をもっている。
マルクスが資本論の中で使った salta は、salto「跳ねる、踊る」の命令形であるが、ヘーゲルが使った saltus は、「跳躍」という意味の名詞の対格(=直接目的格)で、おそらく ago「する」の命令形 age「~をしなさい」が省略されていると考えるのが、最も妥当かと思われる。
ただし、研究社の『羅和辞典』では、salto に「踊る」の訳だけ、saltus に跳躍の訳だけが載っている。Cassell's Latin Dictionary では、salto には、to dance, esp. with pantomimic geatures。 また、saltus には、a spring, leap, boundとある。salto 自体は、踊るの意味が優先するようである。
また、Hic Rhodos, hic salta! を「ここにロドス島あり、ここにて跳べ」、 Hic Rhodos, hic saltus! を、「ここにロドス島、ここに跳躍」と訳している辞典もある。『ギリシア・ラテン引用語辭典』岩波書店)。
アイソフォスの寓話のなかに、ロードス島で他人が真似のできないほどすばらしく踊ったという人にむかって「ここでロードス島だと思ってもう一度踊ってみよ」といった話もある。
フォイエルバッハには、Hic Athenae, hic cogita!(ここがアテナイだ、ここで考えろ!)という言葉がある(http://dia.blog.ocn.ne.jp/shima/2007/11/post_31d9.htmlより引用)。
ロードス島について、『ウィキペディア』の記述を転載させていただく。
ロードス島(ギリシア語:Ρόδος、アルファベット表記:Rodos。英語:Rhodes)はエーゲ海南部ドデカネス諸島に属するギリシャ領の島である。
アテネとキプロス島のほぼ中間、アナトリア半島から18km西方に存在する。2004年時点での人口は130,000人、内60,000人あまりがロードス市で生活している。ロードス市はドデカネーゼ地域の首府でもある。歴史的遺産が多く残る所であり、世界の七不思議の一つであるロードスの巨像が存在したことでも知られる。また、中世期の町並は世界遺産に登録されている。
紀元前16世紀にはミノア文明の人々が、そして紀元前15世紀にアカイア人が到来し、さらに紀元前11世紀にはドーリア人がこの島へとやってきた。ドーリア人たちはのちに本土のコス、クニドス、ハリカリナソスに加えてリンドス、イアリソス、カミロスという3つの重要な都市(いわゆるドーリア人の6ポリス)を建設した。
ペルシャ戦争後の紀元前478年にロードス島の諸都市はアテナイを中心とするデロス同盟に加わった。この後紀元前431年にはペロポネソス戦争が勃発するが、ロードス島はデロス同盟の一員ではあったものの中立的な立場をとりつづけた。紀元前357年にハリカルナソスのマウスロス王によってロードス島は征服され、紀元前340年にはアケメネス朝の支配下に入った。しかしその後紀元前332年に、東征中のアレクサンドロス3世がロードス島をアケメネス朝の支配から解放し、自己の勢力圏の一部とした。
アレクサンドロスの死後、後継者問題からその配下の将軍らによる戦乱が起こり、プトレマイオス1世、セレウコス、アンティゴノスらが帝国を分割した。 このいわゆるディアドコイ戦争の間ロードス島は主に交易関係を通じてエジプトに拠るプトレマイオスと密接な関係にあったが、ロードスの海運力がプトレマイオスに利用されることを嫌ったアンティゴノスは息子デメトリオスに軍を率いさせてロードスを攻撃させた。これに対してロードス側はよく守ってデメトリオスの攻撃を凌ぎきり、翌年攻囲戦の長期化を望まないアンティゴノスとプトレマイオス双方が妥協して和平協定が成立した。この時デメトリオスの軍が遺していった武器を売却して得た収益をもとに、今日アポロの巨像としてその名を残している太陽神ヘリオスの彫像が造られた。
ロードス島はエジプトのプトレマイオス朝との交易の重要な拠点となると同時に、紀元前3世紀のエーゲ海の通商を支配した。海における商業と文化の中心地として発展し、その貨幣は地中海全域で流通していた。哲学や文学、修辞学の有名な学府もあった。
紀元前190年、セレウコス朝の攻撃を受けるもこれを退けた。この時の勝利を記念して、エーゲ海北端のサモトラケ島に翼をもった勝利の女神ニケの像が建てられた。
紀元前164年にローマ共和国と平和条約を結び、以後ローマの貴族たちのための学校としての役割を担うことになる。両者の関係は、当初はローマの重要な同盟国として様々な特権が認められていたが、のちにローマ側によりそれらは剥奪されていき、ガイウス・ユリウス・カエサル死後の戦乱の最中にはカシウスによる侵略を受け都市は略奪された。
紀元前後、後にアウグストゥスの後を継ぎ皇帝となるティベリウスがこの地で隠遁生活を送ったほか、パウロが訪れキリスト教を伝えた。297年、それまでのローマの同盟国という地位からその直接統治下に移ったが、ローマ帝国分裂後は東ローマ(ビザンティン)帝国領となった。ビザンティン領であった一千年の間には、ロードス島はさまざまな軍隊によって繰り返し攻撃された。
ビザンティン帝国が衰亡しつつあった1309年、ロードス島は聖ヨハネ騎士団(別名・ホスピタル騎士団)に占領され、ロードス島騎士団と称されるこの騎士団のもと都市は中世ヨーロッパ風に作り変えられた。騎士団長の居城などのロードス島の有名な遺跡の多くはこの時期に造営されたものである。騎士団は島内に堅固な城塞を築き、1444年のエジプトのマムルーク朝の攻撃や1480年のオスマン帝国のメフメト2世の攻撃を防いだが、1522年にスレイマン1世の大軍に攻囲され遂に陥落した。騎士団の残った者たちはマルタ島へ移っていった。
1912年、トルコ領だったロードス島はイタリアによって占領され、1947年にはドデカネス諸島ともにギリシャに編入された。
マルクス『資本論』の貨幣論で出てくる言葉である。

元々は、イソップ寓話に収められた「ほら吹き男」の話に出てくる言葉である。

古代競技のある選手が、遠征先から帰ってきて自慢話をし、「おれはロドス島では、五輪選手も及ばないような大跳躍をした。皆がロドス島へ行くことがあれば、その大跳躍を見た観客が快く証言してくれるだろう」と言ったところ、それを聞いていたうちの一人が、「そんな証言は要らない。君が大跳躍をしたと言うなら、ここがロドスだ、ここで跳べ」
と言ったという話である。
ロードス島(Rhodes)はエーゲ海に実在するギリシャ領の島であるが、イソップの寓話を語る際には「ロドス」と記すことが多い(http://www6.plala.or.jp/symbell/book/story.htm ;http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q119440446より)。
堀江忠男は、Hic Rhodos, hic salta! を、「ここがロードス島だ、ここで跳べ!」ではなく、「ここがロードス島だ、ここで踊れ!」と訳している(『マルクス経済学と現実』学文社)。
堀江忠男は、その著、『弁証法経済学批判』のなかで、意図的に「跳べ」ではなく「踊れ」を選択したことの理由を述べている。
「余談だが、ここのHic Rhodos, hic salta! は、「ここがロードス島だ、ここで跳べ」と訳されている場合が多いのに、「ここで踊れ」と訳したのは次の理由からだ。ヘーゲルの『法の哲学』の序文に Hic Rhodos, hic saltus. という言葉がある。これが「ここがロードスだ、ここで跳べ」である。これは『イソップ物語』に出てくる寓話の一節で、あるほら吹きがロードス島でものすごい飛躍をしたと自慢したので、聞いた人が「ほんとだったら、ここがロードス島だと思って、跳んで見せろ」といったら、参ってしまったという話だ。
さて、ヘーゲルはついで「さきの慣用句はすこし変えればこう聞こえるだろう。Hier ist die Rose, hier tanze! これがローズ(ばら)だ、ここで踊れ!」(以上、両文とも Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, HW, 7, S. 26.にある。二章(8)の資料 『世界の名著――ヘーゲル』171~3ページ参照。)これをラテン語に書きなおせば Hic rodon, hic salta! である。マルクスはおそらくこの両方を知っていて、Hic Rhodos, hic salta! 「……踊れ」と書いたのであろう」。

『世界の名著35ヘーゲル』を見てみると、 Hic Rhodos, hic saltus.(ここがロドスだ、ここで跳べ)には、次のような注が付いている。
「『イソップ物語』にあるほら吹きが、ロドス島でものすごい跳躍をやらかしたこと、おまけにそれを見ていた証人がいたことを自慢したので、聞いていた人が「お前さん、もしそれがほんとうなら、証人なんかいらない、ここがロドスだ、ここで跳べばいい」といった話がある」。
また、「ここにローズ(薔薇)がある、ここで踊れ。」(Hier ist die Rose, hier tanze!) には、次のような注が付いている。
「ギリシア語のロドス(島の名)をロドン(ばらの花)、ラテン語の saltus(跳べ)をsalta(踊れ)に「すこし変え」たしゃれ。ヘーゲルはここにギリシア語もラテン語も記してはいないが」。
『資本論』では、Hic Rhodos, hic salta! となっているのに対して、ヘーゲルの『法の哲学』では、Hic Rhodos, hic saltus! となっている。
"saltus" と "salta" の違いについて、森田信也(東洋大教授)は次のような見解をもっている。
マルクスが資本論の中で使った salta は、salto「跳ねる、踊る」の命令形であるが、ヘーゲルが使った saltus は、「跳躍」という意味の名詞の対格(=直接目的格)で、おそらく ago「する」の命令形 age「~をしなさい」が省略されていると考えるのが、最も妥当かと思われる。
ただし、研究社の『羅和辞典』では、salto に「踊る」の訳だけ、saltus に跳躍の訳だけが載っている。Cassell's Latin Dictionary では、salto には、to dance, esp. with pantomimic geatures。 また、saltus には、a spring, leap, boundとある。salto 自体は、踊るの意味が優先するようである。
また、Hic Rhodos, hic salta! を「ここにロドス島あり、ここにて跳べ」、 Hic Rhodos, hic saltus! を、「ここにロドス島、ここに跳躍」と訳している辞典もある。『ギリシア・ラテン引用語辭典』岩波書店)。
アイソフォスの寓話のなかに、ロードス島で他人が真似のできないほどすばらしく踊ったという人にむかって「ここでロードス島だと思ってもう一度踊ってみよ」といった話もある。
フォイエルバッハには、Hic Athenae, hic cogita!(ここがアテナイだ、ここで考えろ!)という言葉がある(http://dia.blog.ocn.ne.jp/shima/2007/11/post_31d9.htmlより引用)。
ロードス島について、『ウィキペディア』の記述を転載させていただく。
ロードス島(ギリシア語:Ρόδος、アルファベット表記:Rodos。英語:Rhodes)はエーゲ海南部ドデカネス諸島に属するギリシャ領の島である。
アテネとキプロス島のほぼ中間、アナトリア半島から18km西方に存在する。2004年時点での人口は130,000人、内60,000人あまりがロードス市で生活している。ロードス市はドデカネーゼ地域の首府でもある。歴史的遺産が多く残る所であり、世界の七不思議の一つであるロードスの巨像が存在したことでも知られる。また、中世期の町並は世界遺産に登録されている。
紀元前16世紀にはミノア文明の人々が、そして紀元前15世紀にアカイア人が到来し、さらに紀元前11世紀にはドーリア人がこの島へとやってきた。ドーリア人たちはのちに本土のコス、クニドス、ハリカリナソスに加えてリンドス、イアリソス、カミロスという3つの重要な都市(いわゆるドーリア人の6ポリス)を建設した。
ペルシャ戦争後の紀元前478年にロードス島の諸都市はアテナイを中心とするデロス同盟に加わった。この後紀元前431年にはペロポネソス戦争が勃発するが、ロードス島はデロス同盟の一員ではあったものの中立的な立場をとりつづけた。紀元前357年にハリカルナソスのマウスロス王によってロードス島は征服され、紀元前340年にはアケメネス朝の支配下に入った。しかしその後紀元前332年に、東征中のアレクサンドロス3世がロードス島をアケメネス朝の支配から解放し、自己の勢力圏の一部とした。
アレクサンドロスの死後、後継者問題からその配下の将軍らによる戦乱が起こり、プトレマイオス1世、セレウコス、アンティゴノスらが帝国を分割した。 このいわゆるディアドコイ戦争の間ロードス島は主に交易関係を通じてエジプトに拠るプトレマイオスと密接な関係にあったが、ロードスの海運力がプトレマイオスに利用されることを嫌ったアンティゴノスは息子デメトリオスに軍を率いさせてロードスを攻撃させた。これに対してロードス側はよく守ってデメトリオスの攻撃を凌ぎきり、翌年攻囲戦の長期化を望まないアンティゴノスとプトレマイオス双方が妥協して和平協定が成立した。この時デメトリオスの軍が遺していった武器を売却して得た収益をもとに、今日アポロの巨像としてその名を残している太陽神ヘリオスの彫像が造られた。
ロードス島はエジプトのプトレマイオス朝との交易の重要な拠点となると同時に、紀元前3世紀のエーゲ海の通商を支配した。海における商業と文化の中心地として発展し、その貨幣は地中海全域で流通していた。哲学や文学、修辞学の有名な学府もあった。
紀元前190年、セレウコス朝の攻撃を受けるもこれを退けた。この時の勝利を記念して、エーゲ海北端のサモトラケ島に翼をもった勝利の女神ニケの像が建てられた。
紀元前164年にローマ共和国と平和条約を結び、以後ローマの貴族たちのための学校としての役割を担うことになる。両者の関係は、当初はローマの重要な同盟国として様々な特権が認められていたが、のちにローマ側によりそれらは剥奪されていき、ガイウス・ユリウス・カエサル死後の戦乱の最中にはカシウスによる侵略を受け都市は略奪された。
紀元前後、後にアウグストゥスの後を継ぎ皇帝となるティベリウスがこの地で隠遁生活を送ったほか、パウロが訪れキリスト教を伝えた。297年、それまでのローマの同盟国という地位からその直接統治下に移ったが、ローマ帝国分裂後は東ローマ(ビザンティン)帝国領となった。ビザンティン領であった一千年の間には、ロードス島はさまざまな軍隊によって繰り返し攻撃された。
ビザンティン帝国が衰亡しつつあった1309年、ロードス島は聖ヨハネ騎士団(別名・ホスピタル騎士団)に占領され、ロードス島騎士団と称されるこの騎士団のもと都市は中世ヨーロッパ風に作り変えられた。騎士団長の居城などのロードス島の有名な遺跡の多くはこの時期に造営されたものである。騎士団は島内に堅固な城塞を築き、1444年のエジプトのマムルーク朝の攻撃や1480年のオスマン帝国のメフメト2世の攻撃を防いだが、1522年にスレイマン1世の大軍に攻囲され遂に陥落した。騎士団の残った者たちはマルタ島へ移っていった。
1912年、トルコ領だったロードス島はイタリアによって占領され、1947年にはドデカネス諸島ともにギリシャに編入された。



















