
(一八)ボエティウス(Boethius、480-524)。ギリシャの物理学者。ローマ帝国貴族。ローマ帝国最後の哲学者・著作家であり最初のスコラ哲学者。数学を四つの部門、算術・音楽・幾何学・天文学に分類、これらの四部門を「四科・クアドリウム」と呼ぶ。反逆罪に問われ処刑された。『算術提要』『哲学の慰め』。

(一九)カリッポス(カッリップス)(Calippus of Cyzicus、?~330B.)。ギリシャの哲学者。一年が.365.25日と、365日より回帰年に対する正確な値の発見。カリポス周期:太陽年と太陰年の公倍数76年の周期を作った。同心球形宇宙体系の理論。

(二〇)カタリナ(カタリーナ)(St. Catherine of Alexandria、?~307)。ギリシャ神学・哲学者。シエナ市の中心にはカタリナ大聖堂。十字軍を組織することを願い出た。

(二一)ケフェウス(Cepheus)。ギリシャ神話。エチオピアの王、天文学者、アンドロメダの父。ケフェウス座。

(二二)クレオメデス(Cleomedes、?~50B)。ギリシャの天文学者。屈折現象の研究、ストア派の天文学をまとめた普及書『天体の円運動理論』を残す。地平線付近での大気による屈折。

(二三)クレオストラトス(クレオストラタス)(Cleostratus、?~500B)。ギリシャの天文・哲学者。8年間に3回閏月をおく「8年法」を導入、アテネ暦(太陰・太陽暦)改良。
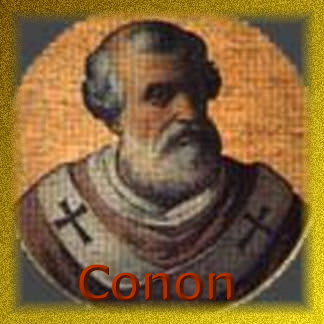
(二四) コノン(Conon、?~260B.)。ギリシャの天文学者。アルキメデスの友人、エジプトの日食記録を調べ暦を作成。プトレマイオス朝の宮廷に仕える。『かみのけ座』をつくる(ペレニケの髪:ペレニケはプトレマイオスⅢ世の妃)。

(二五)ダエダルス(ダイダルス/ダエダロス)(Daedalus)。ギリシャ神話のキャラクター。ギリシャの名工。日夜苦悶するパーシパエーの道ならぬ恋のために木製の牛を造った。パーシパエーは想いを遂げ、生まれたのが牛人ミーノータウロスでその牛人を閉じ込めるラビュリントス迷宮をも造る事に。

(二六)デモクリトス(Democritus、460-360B.)。ギリシャの天文・哲学・博物学者。原子論、実験・観察重視の姿勢、天の川は無数の星でつくられていることを提唱した初めての人。月の表面には高い山や深い谷がある。哲学的な不可分の究極粒子を「原子(アトム)」と呼び、このアトムは分割できず、いろいろな大きさ、形のもので発生することも消滅することもなく常に運動しており、それらの組み合わせや配列に従って、いろいろな物質を形成するものと考えた。運動を実現するものを「空虚(ケノン)」という。原子論は、古代ギリシャの初期唯物論の完成を示し、のちの物理学の礎を築いた(400BC頃)。

(二七)デモナックス(Demonax 、?~100B.)。人間的な善なるものすべてを蔑視し、あらゆる点において自由と自由な発言に身を委ねた。罪を犯すのが人間で、過ちを正すのが神や神々の如き人間であると考えた。

(二八)ディオニシウス(ディオニジウス/ディオニュシウス/ディオニシオス)(Dionysius 、A.D. 9-120)。ギリシャの天文・神学者。使徒パウロの最初のアテネの弟子。神の名前、神秘神学、天使の九階級および牧師の階層について。リッチョーリによると、彼はキリストが十字架に架けられたとき日食を観測。

(二九)ディオファントス(Diophantus、?~A.D.300)。ギリシャの数学者。代数の父。代数の方程式の解決策の、および整数論の研究。130の数学問題の収集研究。一次・二次方程式を解くための定理を確立。不定方程式、ディオファントス解析。

(三〇)エンデュミオン(エンディミオン)(Endymion)。ギリシャ神話の若い羊飼い、月の女神セレーネの冷たい心をひきつけた。女神がエンデュミオンにキスをすると永遠の眠りについた。

(三一) エピメニデス(パルメニデス)(Epimenides、?~596B.)。ギリシャの哲学・数学者。クレタ島の詩人、預言者。Epimenides Paradox。星々は火からできていると考えた。大地は球形で、宇宙をあらわす天球上のすべての点から等距離になるように釣り合っていると信じた。

(三二)エラトステネス(Eratosthenes、BC276-196頃)。ギリシャの天文・哲学・地理学者。アレキサンドリアの図書館長(BC240)。初めて地球の円周を46,250km程度(実際より15%過大)と測定した人。太陽までの距離と月までの距離を測定。「エラトステネスの球素数」を提案。 子午線の円弧。ナイル川の氾濫理由の解明。

(三三)ユークリッド(エウクレイデス/エウクリデス)(Euclides、?~300B.)。ギリシャの数学者。アレクサンドリアのアカデミーの創始者、ユークリッド幾何学の創始者。プラトンの弟子。ユークリッド幾何学『原論』(『幾何学原論』)と幾何光学の創始(光の直進、反射の法則:300BC頃)。「幾何学に王道なし」。『補助論』『図形分割論』『光学』。天文学では『諸現象』。

(三四)エウクテモン(エークテモン)(Euctemon、?~432B.)。ギリシャの天文学者。天気暦を編纂、星座は全て天気の変化との関連において示されており、みずがめ、わし、おおいぬ、かんむり、はくちょう、いるか、こと、オリオン、ペガスス、それとヒアデスとプレアデスの2星団が記されている。

(三五)エウドクソス(ユードクソス/エウドキアス)(Eudoxus、BC406(408)-355頃)。ギリシャの天文・数学者。プラトンの教えを受ける。天文学に数学的基礎を与えた最初の人。地球を中心とする同心天球説(後のアリストテレスの天動説)。惑星の運動を、中心を共有する球の集まりで説明しようとした。球面幾何学の創始。ユークリッドの比例論に基礎を与えた。『幾何学教科書5巻』。
(この項、続く)



















