
アテネは「市民社会」の永遠のロマンとして語り継がれてきた。しかし、私は、アテネを人類の幼年時代に咲いた最高の文明であったという通説を憎悪する。 私は、学生時代から「市民社会論」をとくとくと説く学者諸氏に対して、本能的な敵意を抱いてきた。それは、告白すれば、私の生い立ちが醸し出した感情である。私は、文字通りの貧民層出身である。ろくな教育を受けたこともない貧しい両親の下で育った。しかし、無学の両親は、私には最高級の人間であった。生意気な私を諫(いさ)める両親は、涙でかき口説くことしかできなかった。「それでは、世間に対して申し訳ない」。それで、十分であった。私は、ひたすら内職に励(はげ)む母を尊敬していた。尋常(じんじょう)小学校しか出ていない職人の父が作り出す生活のリズム感に心地よく浸って育った。晩酌を片手に父が描き出す油絵に偉そうに感想を述べ、父がうなずくと心の中で快哉(かいさい*)を叫んだ。私の名前の「美彦」は、「美術で生きていける男」という父(お父ちゃん)の願いが込められたものである。
*(「快なるかな」の意)痛快なこと。
私は、「世間様に対して恥ずかしくない生き方」を、両親から学ぼうとしていた。両親は、私が、「学問なるもの」に飛び込むことを「悪魔に子供が取られてしまう」という恐怖心に駆れていたらしい。屁理屈ばかりこねる嫌な人間にならないで欲しいというのが両親の口癖であった。「お父ちゃん、お母ちゃん、そうではないんだ」と心の中で叫んでも、貧しさの中で懸命に「世間」に認めてもらう生き方にすがる両親を、私は、批判できなかった。どこから聴いてきたのか、「美彦の大学は赤の巣窟(そうくつ)だということではないか」と私を難詰(なんきつ*)することもあった。「だからこの大学を選んだのに」と心の中でつぶやいたが、反論はしなかった。「これが庶民なのだな」と哀しく納得するしかなかった。しかし、私の生き方の原点は、この「教養」のない両親の、歯を食いしばって生き抜いた心にある。
*(そうくつ)悪者などのかくれが。
*(なんきつ)欠点を挙げ非難して問い詰めること。
私の博士論文は、『貿易論序説』である。博士号を得たとき、母は泣いた。貧乏な家庭の子供が博士号を貰ったことの感激から泣いたのではない。逆であった。「我が家の恥ずかしい貧乏ぶりを世間に公表し、世間様の同情を得ようとする我が子の浅ましさに、気も狂わんばかりに哀しい」と私にぶつかってきた母であった。父にいたっては、「大学に行かすのではなかった」と吐き捨てるようにいった。そうか、大事なことはこの感覚なのだと私は納得してしまった。私はいまさらのように、両親の子であることを神に感謝した。
つまらない独白をしてしまって、読者諸氏には申し訳ない。
一世を風靡した「市民社会論」者たちは、いまはどうしているのか。米国が口火を切った地球戦争を阻止する理論を彼らは作っているのか。フランス・ワインを飲み、フランス語で造語し、そのくせ、大衆の愚劣さをあげつらってきただけではないのか。無能で卑しい大衆、社会全体のことを考えず、ただ、雰囲気で群れる思想のない「タダモノ主義者」=貧民。そのような大衆に媚びるポピュリストに厳しい批判を畳みかけてきた。しかし、それ以上のことを「市民社会論」者たちはしてきたのか。私は、スノビズム*をもっとも嫌悪する。
*Snobbism- 俗物根性。社会的地位や財産などのステータスを崇拝し、教養があるように上品ぶって振る舞おうとする態度。学問や知識を鼻にかける気取る態度。また、流行を追いかけること。
彼らのいう「市民」とはなになのだろうか。会社の経営者であり、学者であり、自らの才覚で華麗に生きて行ける、要するに、社会の「エリート」たちではないのか。彼らのいう市民とは、「自覚した歴史の創出者」であって、「無能で」、「卑しい」大衆ではない。私が、ともに生きようとする層は、彼らの研究対象である「市民」では絶対にない。
アテネのポリスでは、わが両親は歴史に残らなかったであろう。せいぜい、奴隷にしては絵が上手いなという評価を得ただけであろう。ましてや、プラトン先生など歯牙にもかけてくださらなかったであろう。
アテネは「市民社会」の永遠のロマンとして語り継がれてきた。しかし、私は、アテネを人類の幼年時代に咲いた最高の文明であったという通説を憎悪する。このブログは、そうしたアカデミズムへの基本的拒否の表明である。このように、書いてしまえば、激してしまって、我を失うわが哀しい心情が「世間」様にばれることになるので、この程度で抑えておこう。この瞬間にわが母の涙が浮かんでしまった。ただ、これだけは断言する。「民主主義とは、馬鹿で、無能で、卑しい、下層民の誇りを保証するものだ」と。それ以外の民主主義など、私はいらない。衆愚に堕落しない社会を作る努力は払い続けよう。そうした努力の合い言葉が「共感」である。「共感」は、私の大学停年の最終講義のテーマであった。
エドアルト・マイヤー『古代史』第3巻、『ペルシャ帝国とギリシャ人たち』(1901年)の言葉は重い。
ペルシャ人がギリシャに対して勝利していたら、彼らは土着宗教の権威を借りていたであろう。土着の祭司層を支配的地位に引き上げ、単一の教会(デルフォイ神殿)と首尾一貫した神学大系が編纂されていたであろう。
「外国人支配、教会、神学の同盟は、ここギリシャでも、国家とともに、人間生活と人間的活動」を永久に妨げたであろう」(マイヤー)。
多くの地域にとって、支配は外部からくる。そして、必ず、地域内の抗争に苛立ち、外部の力を導入することによって、内部の抗争に勝利しようとする層が出てくる。新たな支配者は、地域の旧支配者を守旧派、ドアを開けて自分をこっそりと導き入れてくれた層を改革者と呼んで持ち上げるであろう。外部の支配者は、自分を引き入れた層に権威をもたすべく、体系的な学問を授ける。それが、市民なるものを選別する機構となる。守旧派イコール馬鹿というイメージが作り出され、市民はかぎりなく権威にすり寄り、改革者を装う。改革派の権威が弱くなる恐れが出てきたとき、権威は宗教を巻き込む。宗教も学問もひたすら体系化・儀式化が進行し、市民にすらなれなかった大衆が窒息する。いま明確にしなければならないことは、米国に媚びる日本の政治状況の構造である。また、ひたすら他国民を殺戮し、自らも殺されながら、良心に基づく反乱を起こさない最下層の兵隊たちの心理である。
「市民的勢力と宗教的勢力との間の一般的な親和性は、両者の一定の発展段階において典型的に見られる現象あるが、・・・これら両勢力は、封建的権力に対する正式の同盟にまで強化されることもある」(マックス・ウェーバー『支配の社会学』(創文社、1962年)第2巻第7節「政治的支配と教権制的支配」)。
封建的勢力を反体制組織と言い換え、市民的勢力を米国を導入する層と言い換え、宗教的勢力をキリスト教右派と言い換えて見れば、現在こそ、「マイヤー的世界」であることがわかるであろう。その意味において、権力機構の分析のない「市民社会論」ほど虚しいものはない。

*(「快なるかな」の意)痛快なこと。
私は、「世間様に対して恥ずかしくない生き方」を、両親から学ぼうとしていた。両親は、私が、「学問なるもの」に飛び込むことを「悪魔に子供が取られてしまう」という恐怖心に駆れていたらしい。屁理屈ばかりこねる嫌な人間にならないで欲しいというのが両親の口癖であった。「お父ちゃん、お母ちゃん、そうではないんだ」と心の中で叫んでも、貧しさの中で懸命に「世間」に認めてもらう生き方にすがる両親を、私は、批判できなかった。どこから聴いてきたのか、「美彦の大学は赤の巣窟(そうくつ)だということではないか」と私を難詰(なんきつ*)することもあった。「だからこの大学を選んだのに」と心の中でつぶやいたが、反論はしなかった。「これが庶民なのだな」と哀しく納得するしかなかった。しかし、私の生き方の原点は、この「教養」のない両親の、歯を食いしばって生き抜いた心にある。
*(そうくつ)悪者などのかくれが。
*(なんきつ)欠点を挙げ非難して問い詰めること。
私の博士論文は、『貿易論序説』である。博士号を得たとき、母は泣いた。貧乏な家庭の子供が博士号を貰ったことの感激から泣いたのではない。逆であった。「我が家の恥ずかしい貧乏ぶりを世間に公表し、世間様の同情を得ようとする我が子の浅ましさに、気も狂わんばかりに哀しい」と私にぶつかってきた母であった。父にいたっては、「大学に行かすのではなかった」と吐き捨てるようにいった。そうか、大事なことはこの感覚なのだと私は納得してしまった。私はいまさらのように、両親の子であることを神に感謝した。
つまらない独白をしてしまって、読者諸氏には申し訳ない。
一世を風靡した「市民社会論」者たちは、いまはどうしているのか。米国が口火を切った地球戦争を阻止する理論を彼らは作っているのか。フランス・ワインを飲み、フランス語で造語し、そのくせ、大衆の愚劣さをあげつらってきただけではないのか。無能で卑しい大衆、社会全体のことを考えず、ただ、雰囲気で群れる思想のない「タダモノ主義者」=貧民。そのような大衆に媚びるポピュリストに厳しい批判を畳みかけてきた。しかし、それ以上のことを「市民社会論」者たちはしてきたのか。私は、スノビズム*をもっとも嫌悪する。
*Snobbism- 俗物根性。社会的地位や財産などのステータスを崇拝し、教養があるように上品ぶって振る舞おうとする態度。学問や知識を鼻にかける気取る態度。また、流行を追いかけること。
彼らのいう「市民」とはなになのだろうか。会社の経営者であり、学者であり、自らの才覚で華麗に生きて行ける、要するに、社会の「エリート」たちではないのか。彼らのいう市民とは、「自覚した歴史の創出者」であって、「無能で」、「卑しい」大衆ではない。私が、ともに生きようとする層は、彼らの研究対象である「市民」では絶対にない。
アテネのポリスでは、わが両親は歴史に残らなかったであろう。せいぜい、奴隷にしては絵が上手いなという評価を得ただけであろう。ましてや、プラトン先生など歯牙にもかけてくださらなかったであろう。
アテネは「市民社会」の永遠のロマンとして語り継がれてきた。しかし、私は、アテネを人類の幼年時代に咲いた最高の文明であったという通説を憎悪する。このブログは、そうしたアカデミズムへの基本的拒否の表明である。このように、書いてしまえば、激してしまって、我を失うわが哀しい心情が「世間」様にばれることになるので、この程度で抑えておこう。この瞬間にわが母の涙が浮かんでしまった。ただ、これだけは断言する。「民主主義とは、馬鹿で、無能で、卑しい、下層民の誇りを保証するものだ」と。それ以外の民主主義など、私はいらない。衆愚に堕落しない社会を作る努力は払い続けよう。そうした努力の合い言葉が「共感」である。「共感」は、私の大学停年の最終講義のテーマであった。
エドアルト・マイヤー『古代史』第3巻、『ペルシャ帝国とギリシャ人たち』(1901年)の言葉は重い。
ペルシャ人がギリシャに対して勝利していたら、彼らは土着宗教の権威を借りていたであろう。土着の祭司層を支配的地位に引き上げ、単一の教会(デルフォイ神殿)と首尾一貫した神学大系が編纂されていたであろう。
「外国人支配、教会、神学の同盟は、ここギリシャでも、国家とともに、人間生活と人間的活動」を永久に妨げたであろう」(マイヤー)。
多くの地域にとって、支配は外部からくる。そして、必ず、地域内の抗争に苛立ち、外部の力を導入することによって、内部の抗争に勝利しようとする層が出てくる。新たな支配者は、地域の旧支配者を守旧派、ドアを開けて自分をこっそりと導き入れてくれた層を改革者と呼んで持ち上げるであろう。外部の支配者は、自分を引き入れた層に権威をもたすべく、体系的な学問を授ける。それが、市民なるものを選別する機構となる。守旧派イコール馬鹿というイメージが作り出され、市民はかぎりなく権威にすり寄り、改革者を装う。改革派の権威が弱くなる恐れが出てきたとき、権威は宗教を巻き込む。宗教も学問もひたすら体系化・儀式化が進行し、市民にすらなれなかった大衆が窒息する。いま明確にしなければならないことは、米国に媚びる日本の政治状況の構造である。また、ひたすら他国民を殺戮し、自らも殺されながら、良心に基づく反乱を起こさない最下層の兵隊たちの心理である。
「市民的勢力と宗教的勢力との間の一般的な親和性は、両者の一定の発展段階において典型的に見られる現象あるが、・・・これら両勢力は、封建的権力に対する正式の同盟にまで強化されることもある」(マックス・ウェーバー『支配の社会学』(創文社、1962年)第2巻第7節「政治的支配と教権制的支配」)。
封建的勢力を反体制組織と言い換え、市民的勢力を米国を導入する層と言い換え、宗教的勢力をキリスト教右派と言い換えて見れば、現在こそ、「マイヤー的世界」であることがわかるであろう。その意味において、権力機構の分析のない「市民社会論」ほど虚しいものはない。











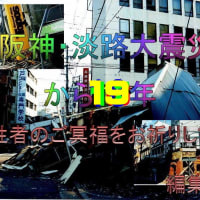





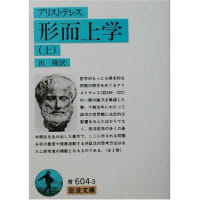

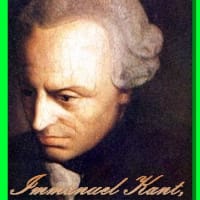

前まで法務教官として、ある医療少年院で働いてましたが、合わなくてすぐ辞めちゃいました(^_^;)こんな自分ですが、よかったら友達になってほしいです。よろしくね(^-^)
http://blog.livedoor.jp/keijikun/
でも、「市民社会」という言葉は使い続けます。
なぜって?
それはきれいごと言ってるやつらに対して、「そんな甘いもんじゃない。」と真逆の意味をこの言葉に載せて、「送りかえりて差し上げたいから」です。
絶対に妥協しません。
しょうもない御託ばっかり並べてるやつらは、ほっときます。僕は先生に常に「共感」してこの10年間研究し続けてきました。その怒りを生のエネルギーに変え、文章の所々にその思いを迸らせていくやり口にいつも脱帽してます。
これからもずっと同じです。
以上!