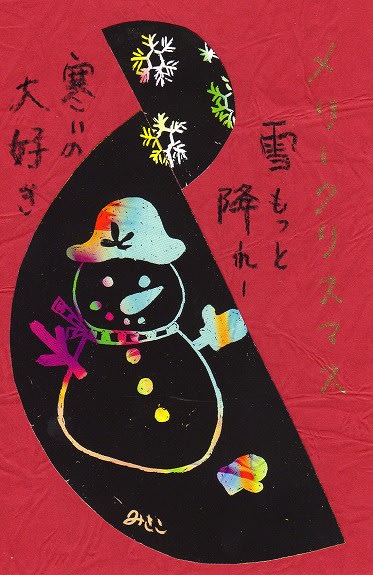絵手紙教室でご一緒のMさんから「花だより」をいただいたのは5月のこと・・・
5月14日
いつも楽しくブログ拝見してます。
綺麗な写真と楽しいお話であけるのが楽しみです。
桜は早かったり遅かったり、タイミングが難しいですね。
今年は、
和歌山県⇒根来寺、
京都府⇒花の寺、山科の毘沙門天(動く襖絵、形の変わる龍の天井絵等、住職さんの説明を受けました)
奈良県⇒瀧蔵神社の権現桜(桜井市)、奈良県立図書館前辺りの桜並木もとても綺麗でした
吉野(西行庵までかなりのアップダウンで少し疲れました)
岐阜県⇒根尾谷の淡墨桜、
10日に以前から行きたかった花桃の里に行ってきました。
園原インターを降りてすぐの月川温泉郷辺りに5千本の花桃が植えてあり、祭りの最終日で花はやや散りかけでしたが、とても綺麗でした。


添付写真は携帯電話によるものなのであまり綺麗ではありませんが・・・。
花桃の里全景とアップです。
水芭蕉も見られるようです。日帰りで片道3時間半~4時間かかるのであまりゆっくりできませんでしたがそれなりに得たものもあったかな?。
7日には曼殊院(京都市)
11日には蹴上(京都市)の浄水場へツツジを見に行きました。浄水場はこの日が一般公開最終日で駆け込み見学でした。ツツジのトンネル等趣向をこらし楽しめるようにしてありましたよ。
携帯でちょっと・・・

蹴上から南禅寺山門を撮りました。
Re:わんちゃん
いつもblogを見ていただいてアリガトウです。
コレって結構励みになってるんですよ、ウレシイです。
今年は桜の見ごろ時期が迷走してしまって、アッというまに桜前線は通り過ぎて、行ってしまいましたね。
ちょっと残念でした、ま、来年に期待しましょうってとこでしょうか。
たくさんの花だよりアリガトウ
桜、何か所も行かれたんですね。
携帯で撮ってらっしゃるとは思えないほど立派です。
Mさんのウデマエも携帯の性能もスッゴイんですね。
西行さんですけど、本名は佐藤義清(のりきよ )だったんですね、
西行さんは亡くなる十数年前に、遺言のような次の歌を詠んでたんですね。
『願はくは花のもとにて春死なむ その如月(きさらぎ)の望月の頃』
※如月の望月=2月15日。釈迦の命日。
(願わくば2月15日ごろ、満開の桜の下で春逝きたい)
西行さんが来世へ旅立ったのは2月16日。釈迦の後ろを一日遅れてついて行った・・・
大河ドラマで藤木直人くんが演じてはりましたね、西行さんはイケメンだったそうですよ。
桜の名所のあっちこっちに西行庵があって、訪ねてみたいなって思いつつ月日は過ぎて行き・・・です。
>園原インターを降りてすぐの月川温泉郷辺りに5千本の花桃
ここはどこ?でしょうか?
曼殊院は思い出のお寺です。
蹴上の浄水場へは舅が元気なころ主人と3人で行ったことがあり懐かしく思いだしてました。
これから、あじさい、花菖蒲と、まだまだ花行脚は続きますよね
キレイなお花が咲きますように丹精込めて育ててはる方たちの思いを大切に・・・といつも思います。
いつもアリガトウ
また、花だより楽しみにしてます
Re:Mさん
5月18日
花桃の里は長野県下伊那郡阿智村で、中央自動車道の園原インターで降りてすぐの所です。
昼神温泉、月川温泉等もありますが、なかなかひなびた所ですよ。
春には桜、水芭蕉等も見られる様です。時間があればゆっくり散策したかったのですが、なにぶん日帰りで時間が無かったので・・・来年に期待です。
私は行けなかったのですが、主人が16日に大田神社を訪れたらしく、杜若が満開だったと言ってましたヨ。

大田神社は上賀茂神社の隣です。
Re:わんちゃん
>花桃の里は長野県下伊那郡阿智村で、中央自動車道の園原インターで降りてすぐの所です。
遠いところを日帰りされたんですね、
信州の春はお花がいっせいに咲くのでしょうね、若い頃何度か信州方面には訪れてるんですけど、
全く、お花に興味が無かったんでどんな花が咲いていたのか全然記憶にないのです
今から思えばもったいないことです。
チャンスがあれば信州の方へも花を訪ねて行きたいモンです
「花桃の里」いっぺん行ってみたいですねぇ
温泉もアリとか?
16日はちょうど、
葵祭り を撮りに上賀茂神社の境内に居ました
(ひょっとしてご主人さんとニアミス?)
よっぽど太田神社の方へも行こうかと思ったんですが
午前中はグラウンドゴルフ・・・で上賀茂神社に(葵祭)到着のシーンのみを撮るようになってしまって。
今から思えばグラウンドゴルフはいつでもできる、そしてその日はスコアがあンまりよくなかったんですよ、太田神社(カキツバタ)へ行っとけばよかったぁ・・・
4年前に
太田神社(カキツバタ)
そのずっと前に主人とも行ってるんですよ、
太田神社のすぐそばに
「愛染倉(あぜくら)」 というお店があって食事をしたこともありました。
お庭も凄くステキで、オススメですよ。
是非ご主人さんとご一緒に・・・
Re:Mさん
大田神社、行ってらしたんですね。今三番咲きとか・・・。
16日、主人も葵祭りを見に行っていて、神馬舎辺りにいたそうです。
その後、杜若を見に行ったらしいです。
18日に「山陰一の藤公園」と言われる兵庫県和田山の大町公園へ行ってきました。

ピンクは終わり、紫も枯れかけていましたが、白色が満開でした。

村起しの一貫なのか、ずいぶん綺麗に整地されていました。
藤うどん?紫うどん?(ブルーベリーを麺に混ぜ込んである)なるもので腹ごしらえをし、散策。
噴水を囲むように藤棚の下を歩けるようにしてあったり、90段の階段を上がると小さなダムをせきとめた溜池の端から端へ、鯉のぼりが渡してありました。
風がつよかったので、鯉のぼりの鯉さんたちもヒッシ・・・
階段の両側には、水仙がいっぱい植えられていましたよ。
駐車場も広くツツジが植えてありました。
Re:わんちゃん
>「山陰一の藤公園」と言われる兵庫県和田山の大町公園へ行ってきました。
兵庫県和田山は両親の田舎がそちらの方です、
けど、知りません、そんな藤の名所があるなんて・・・
Mさんから教えていただくお花の名所のなんて多い事。
機会を作って行ってみたいです
いろんな情報アリガトウです
Mさんから
5月25日
24日、伊丹市にある荒牧バラ公園に行って来ました。
JRの新聞折込みを見て急に出かけたシダイです。
住宅地の中にある公園で、近所の方が、散歩の途中で気軽に立ち寄れるような所です。
が、昼過ぎともなると駐車場も満車状態になり、保育園児、介護施設からと・・・大勢の人達で賑わっていましたよ。
1.7haの敷地に250種1万本のバラが植えられています。
原種、ベルギーや日本で品種改良されたもの等が所狭しと植えられていました。
写真は、「上から見下ろした所」と、

「プリンセスアイコ、その後ろに少し見えている赤いのがプリンセスミチコ」です。
駐車場から公園へと歩く道に「百合の木」がありました。

写真では全体はわかりませんが、高さ15メートルにもなるようで、咲いていても上を見上げないと気が付かない
みたいです。花の中はどんなふうになってるのか見てみたいです。
わんちゃんは見はったことありますか?。私は初めてでした。
植物園にあるのかな?なんて思ったり・・・。
Re:わんちゃん
あぁ~~そういえばバラの時季ですねぇ
伊丹市のバラ公園は行ったことないですね、
シーズンを見逃さないMさんスゴイなぁ・・・
バラは京都府立植物園もステキだし神戸の須磨離宮公園も良かったなぁ
ダイアナ妃のバラがありましたよ
須磨離宮公園は5~6年前に行ったきりなんでまた行きたいなと思ってます。
バラと言えば大和郡山の松尾寺へも・・・
何年か前、厄年の年、友達と厄払いにちょうどバラの頃に行きました
ところがご祈祷料がもったいなくて、その分「弁慶」で食事しました(笑)
ユリノキですが
ウチの近所の浄化センター(むくのきセンター)の並木に植栽されてて、いつもそばを通るのですが、ソレがユリノキで花が咲くとつい最近知りました
それで、今日のお昼に見てきました
大きめの花ですね
写真は先週の金曜日に河内長野市の公園で撮ってます
フツー街路樹や公園の木に多いのですが高く伸びるので下の方は剪定されてて花はなかなか見ることができないって教えていただきました。
ここの公園ではまだ若い木で下の方でも咲いていました、と言うても背伸びして傘の柄で引っ張ってもらってね撮ったんですけど・・・

コレはキーウイの花です、キーウィの花は初めて見ました
出かけた時住宅街を通ってて「えっ?アレは?」
車にカメラを載せていたので撮ることができました
キーウイは雌花と雄花があるんですねぇ・・・
雌花

雄花

また花だよりくださいね
いつもアリガトウ
Re:Mさん
ユリの木、バッチリですね。中も良くわかります。
キーウイの花可愛いですね。この頃家の庭にぶらさがってるのをみかけますが、花は見たことは無かったです。
須磨離宮公園、今日行ってきました。満開で散ってる花も多かったです。
今の天皇陛下のご成婚記念事業として整備が始まったとか・・・。
噴水広場から水路を流れて最後は大噴水に。とても壮観でした。その左右にバラが植えられていて、とても綺麗でした。
プリンセス・ミチコ、ロイヤル・プリンセス(愛子さま誕生記念に名ずけられた)、マサコ、ダイアナ・プリンセス・オブ・ウェールズ・・・。
180種4000株だとか。
バラの他には梅、桜(小さなサクランボがいっぱいついてました)、花菖蒲、等300種以上の植物が植えられているようです。
子供達がかなり危険?そうな滑り台でたのしんでました。
さすが離宮だけあって、松並木や立派な正門、石積等は豪華でした。

写真はダイアナさんです。
Mさんから
6月5日
ユリの木、よく見ればいろんな所に植えてあるんですね。知らないだけで。
実は、灯台下暗しというか、家のすぐ近くの神功幼稚園の門を入ったすぐのところに
一本ですが植えてあったんです。二階建ての園舎の屋根を、かる~く越えてます。
先生も「最近知ったんです。二階の遊戯室から良く見えますよ。見に来て下さい。」
と言われたようですが・・・。
娘二人卒園したのに知りませんでした。その頃は興味も無かったんでしょうね。
ブログ見せてもらって、近くでも色々楽しめることを再発見してます。
4日ツツジが満開で、特別拝観が出来るということで京都鹿ケ谷の安楽寺へ行ってきました、が・・・
由来はおいといて、7月25日に中風まじない鹿ケ谷カボチャ供養があり
参拝者に振舞いがあるみたいです。中風にならないように願う行事だそう。
いっとかないと・・・。
銀閣寺へのみちの途中にある法然院に寄ったんですが、本殿は拝観出来ませんでした。
でも静かで落ち着いた良い所です。
お昼ご飯はご存知でしょうか「おめん」でリッチにおうどん。
修学旅行の中学生のグループが何組も入ってました、いまどきは下調べしてタクシーで回るんですね。
運転手さん同士「どこどこ回って来た」「次はここ」とか、会話したはりました。
また楽しいお話(ブログ)を!!。
Re:わんちゃん
いつもアリガトウです
ホンマにそうですね
ユリノキ、いつも通る道路の傍に100本も植栽されてるんですよ、今の今まで気が付かなかったぁ
ちょっと注意すると意外とあるんですよね、ユリノキ以外にもそんなんがあるかも知れないですね。
法然院について
「境内は森閑とし、多くの大木の中にヤブツバキの老木が目立つ、3月上旬から境内のあちこちに赤や白の椿が咲き、下旬ともなるとそれらの落花が風情を誘う。山門までの参道は特に落花が多く、石畳を彩る花が仲春の訪れをささやく」こんなキャッチコピーとその写真が添えられてる花の本を見て行ってきました、
「3月20日遅すぎた・・・」とメモが挟んであります、15年も前のこと・・・
その日でしたね銀閣寺の傍の「おめん」に主人と立ち寄って美味しいおうどんいただいたのは・・・
懐かしい思い出です。
Mさんから
6月6日
これからいよいよ紫陽花のシーズンですね。
去年京都洛西の善峰寺(遊龍の松で有名、西国?番の札所)に行った時、綺麗に整地され、紫陽花がいっぱい植えられていてびっくりしました。シーズンじゃなかったので今年行ってみてもいいかな?なんて思ってます。
高校の3年から結婚するまですぐ近くの「右京の里」にいたので懐かしいところです。
また花情報お願いしまーす。
Re:わんちゃん
善峰寺(西国三十三箇所第二十番札所)へは紅葉の頃お参りした記憶があります、紫陽花ですか?いいかも・・・
宇治の三室戸寺(西国三十三箇所第十番札所)へもちょうど紫陽花の頃お参りしたことがあります。幻のアジサイと言われていたシチダンカに初めて出合ったのがこのお寺でした
今じゃわんちゃんちの庭ででも咲いてますけど・・・

シチダンカ(七段花)ユキノシタ科
琵琶湖畔の長命寺(西国三十三箇所第三十一番札所)が札所めぐりで一番最初に訪れたお寺でしたちょうど紫陽花の頃でした。
こんなこと目にしました
長命寺あじさいコンサート
それから神戸市の市花がアジサイで須磨離宮公園にある20品種8000株のアジサイが・・・と。
神戸市立森林植物園もさすがです。
お近くで済まされるのなら大和郡山の矢田寺辺りはいかがでしょうか?
じゃぁ又ね、花だより楽しみにしてまぁす