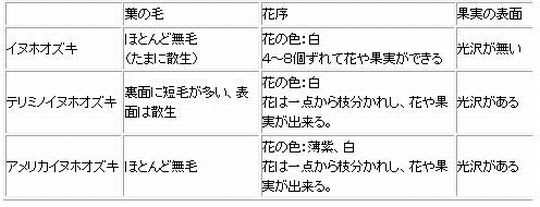この夏、偶然にも同じ場所を植物観察で三度訪れました
7月7日(やましろ里山の会・植物部)
7月22日(木津川市植物同好会)
7月28日(個人的に)
暑い暑い真夏の木津川河川敷です。
京田辺市玉水橋から木津川左岸を少し下流に歩きサイクリングロードを河川敷に下りて行ったところです。
河川敷の中のお花畑のように思いました ⇒こちら
ちょっと日にちがずれますと、出合うお花たちの顔ぶれも、ちょっと変わってきますね。
オオフタバムグラの可愛いお花、ちっちゃいお花なんで撮るには難しかったです
オオフタバムグラ(大双葉葎)アカネ科

オオフタバムグラは北アメリカ原産の帰化植物です。
生育場所は海岸や河川敷などの砂地を好むようです⇒ナルホドです。
『木津川市植物同好会』での観察会の時アカメガシワの花外蜜腺というのを教えていただきました
「ここに虫がきてますね、花にきてるのなら解りますが・・・なぜでしょうか?」
「エッ!はぁ?」
「ココに蜜腺があるんですよ、花の外の蜜腺で花外蜜腺といいます、アリがよくきてますね、アリが寄って来ることで毛虫が付かない、ということでアカメガシワは工夫してるんですねぇ」

2009.6.4 山城森林公園
この日はたまたまヒメジュウジナガカメムシが訪れていました。
ヒメジュウジナガカメムシ

ホラちゃんとね・・・

カメムシ目 ナガカメムシ科
大きさ 8mm前後
鮮やかな朱色と黒色に塗り分けられた印象的なデザインのカメムシ。
(いっぺん見たら忘れませんね)
オニグルミ(鬼胡桃)クルミ科

「何でこんなところにオニグルミがあるんでしょうか?」
「どっかから流れてきたんかしら?」
「コレは谷筋に居る木なんです、上流の谷筋から流されてここ(河川敷)まで来たのでしょう」
「あらぁ!実が生ってるぅ」「この実は食べれる?」
「食べられますよ、もっと熟してきたら、周りの果皮を腐らします、中の実を干して炒ったりして食べるんですよ」
オニグルミは4月の終わりから5月にかけて花を咲かせます⇒こちら
オニグルミの実を撮っていたら小さな虫を発見(上の写真の矢印)

ベッコウハゴロモ大きさ (翅端まで)9-11mm
このように、お花を撮っていると虫たちにも目が行きます。
どの虫たちも木津川河川敷で出合った虫たちです。
ヒラヤマアミメケブカミバエ ミバエ科

体長3.5~4mm。
ミバエの仲間は、実(み)に限らず、植物組織内に卵を産み、幼虫は周囲の組織を食べて育ちます。
ヒラヤマアミメケブカミバエはヨモギの茎の先端に虫えい(虫こぶ)を作って育ちます。
ラミーカミキリ(Ramie髪切)コウチュウ目(鞘翅目)カミキリムシ科

体長:10~20mm
(今年の夏はこのカミキリムシによく出合ってますねぇ)
大阪市立大学付属植物園⇒こちら
南山城村童仙房⇒こちら
ツメクサガ チョウ目(鞘翅目)ヤガ科

大きさ (開張)32-35mm
「幼虫の食草のムラサキツメクサにツメクサガ、いい写真ですね。」
「アリガトウございます」
ナカグロツトガ チョウ目 ツトガ科

翅をたたんで棒状になってとまっているところです。
マメコガネ(豆黄金)コウチュウモ目 コガネムシ科

大きさ 9-13mm
キレイな色のカワイイ虫!と思いましたが、結構農作物を食い荒らすらしい、日本在来種だが、移入した北アメリカで繁殖して大害虫となり、"Japanese beetle"(ジャパニーズ・ビートル)と呼ばれて嫌われている。
と言うてもアメリカに移入したのは1910年代の頃のこと・・・
キマダラコヤガ ヤガ科

大きさ (開張)21-24mm
前翅は黄色に黒い線と点の斑紋があり、明瞭な色彩が引き立って綺麗。
キマダラコヤガに初めて出合った時⇒こちら
ホソハリカメムシ カメムシ目 ヘリカメムシ科

大きさ 9-11mm
淡褐色で、やや細長いカメムシ。胸部の両端が鋭く尖っている。
メヒシバ、エノコログサ(↑ナルホドです)など、イネ科の植物でよく見られる。水田のイネも食害する。
虫たちの写真が溜まってるんで、あともう少し紹介します。続く・・・
7月7日(やましろ里山の会・植物部)
7月22日(木津川市植物同好会)
7月28日(個人的に)
暑い暑い真夏の木津川河川敷です。
京田辺市玉水橋から木津川左岸を少し下流に歩きサイクリングロードを河川敷に下りて行ったところです。
河川敷の中のお花畑のように思いました ⇒こちら
ちょっと日にちがずれますと、出合うお花たちの顔ぶれも、ちょっと変わってきますね。
オオフタバムグラの可愛いお花、ちっちゃいお花なんで撮るには難しかったです
オオフタバムグラ(大双葉葎)アカネ科

オオフタバムグラは北アメリカ原産の帰化植物です。
生育場所は海岸や河川敷などの砂地を好むようです⇒ナルホドです。
『木津川市植物同好会』での観察会の時アカメガシワの花外蜜腺というのを教えていただきました
「ここに虫がきてますね、花にきてるのなら解りますが・・・なぜでしょうか?」
「エッ!はぁ?」
「ココに蜜腺があるんですよ、花の外の蜜腺で花外蜜腺といいます、アリがよくきてますね、アリが寄って来ることで毛虫が付かない、ということでアカメガシワは工夫してるんですねぇ」

2009.6.4 山城森林公園
この日はたまたまヒメジュウジナガカメムシが訪れていました。
ヒメジュウジナガカメムシ

ホラちゃんとね・・・

カメムシ目 ナガカメムシ科
大きさ 8mm前後
鮮やかな朱色と黒色に塗り分けられた印象的なデザインのカメムシ。
(いっぺん見たら忘れませんね)
オニグルミ(鬼胡桃)クルミ科

「何でこんなところにオニグルミがあるんでしょうか?」
「どっかから流れてきたんかしら?」
「コレは谷筋に居る木なんです、上流の谷筋から流されてここ(河川敷)まで来たのでしょう」
「あらぁ!実が生ってるぅ」「この実は食べれる?」
「食べられますよ、もっと熟してきたら、周りの果皮を腐らします、中の実を干して炒ったりして食べるんですよ」
オニグルミは4月の終わりから5月にかけて花を咲かせます⇒こちら
オニグルミの実を撮っていたら小さな虫を発見(上の写真の矢印)

ベッコウハゴロモ大きさ (翅端まで)9-11mm
このように、お花を撮っていると虫たちにも目が行きます。
どの虫たちも木津川河川敷で出合った虫たちです。
ヒラヤマアミメケブカミバエ ミバエ科

体長3.5~4mm。
ミバエの仲間は、実(み)に限らず、植物組織内に卵を産み、幼虫は周囲の組織を食べて育ちます。
ヒラヤマアミメケブカミバエはヨモギの茎の先端に虫えい(虫こぶ)を作って育ちます。
ラミーカミキリ(Ramie髪切)コウチュウ目(鞘翅目)カミキリムシ科

体長:10~20mm
(今年の夏はこのカミキリムシによく出合ってますねぇ)
大阪市立大学付属植物園⇒こちら
南山城村童仙房⇒こちら
ツメクサガ チョウ目(鞘翅目)ヤガ科


大きさ (開張)32-35mm
「幼虫の食草のムラサキツメクサにツメクサガ、いい写真ですね。」
「アリガトウございます」
ナカグロツトガ チョウ目 ツトガ科

翅をたたんで棒状になってとまっているところです。
マメコガネ(豆黄金)コウチュウモ目 コガネムシ科

大きさ 9-13mm
キレイな色のカワイイ虫!と思いましたが、結構農作物を食い荒らすらしい、日本在来種だが、移入した北アメリカで繁殖して大害虫となり、"Japanese beetle"(ジャパニーズ・ビートル)と呼ばれて嫌われている。
と言うてもアメリカに移入したのは1910年代の頃のこと・・・
キマダラコヤガ ヤガ科

大きさ (開張)21-24mm
前翅は黄色に黒い線と点の斑紋があり、明瞭な色彩が引き立って綺麗。
キマダラコヤガに初めて出合った時⇒こちら
ホソハリカメムシ カメムシ目 ヘリカメムシ科

大きさ 9-11mm
淡褐色で、やや細長いカメムシ。胸部の両端が鋭く尖っている。
メヒシバ、エノコログサ(↑ナルホドです)など、イネ科の植物でよく見られる。水田のイネも食害する。
虫たちの写真が溜まってるんで、あともう少し紹介します。続く・・・