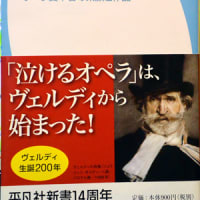北沢方邦の伊豆高原日記⑭
南に傾いた陽射しが室内にも当るこの季節、いつものように、夏のあいだ外に出していた観葉植物をとりこんだ。そのひとつにカネタタキが付いていたらしく、夜の灯のもとで鳴きはじめた。近くで聴くと、コオロギより小さな体から出るとも思えないほどよくひびく、その透明な鉦の音に、奥深い寺院の内陣にいるような瞑想的な気分になる。
北朝鮮の核実験騒動
安倍首相の初仕事が訪中・訪韓の首脳会談であり、中・韓両国との外交関係の修復であった。歴史認識の問題があいまいなままに決着したが、少なくともその脱小泉の姿勢と修復の結果は評価すべきであろう。そこにさらに彼にとっての追い風が吹いた。いうまでもなく北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国)による核実験である。
ことわるまでもなく私は一切の核開発(平和利用も含め)に反対だし、北朝鮮を擁護する気は毛頭ない。アリゾナ州のウラン鉱山で低レベル放射線長期被曝したナバホ族の鉱夫たちの苦痛と死、チェルノブイリの恐るべき被害、ほとんど報道されないウラン精錬工場や濃縮施設あるいは再処理施設での被曝者たちの苦しみなど、核開発はそれにともなう犠牲があまりにも大きい。無人の空間(防護服着用しないものの入室禁止の立て札)のドラム缶に音もなく降り注ぐ黄色い粉末(6弗化ウラン)を、黒く分厚い防護カーテンの隙間からかいまみたニューメキシコ州のウラン精錬工場での経験以来、私はことあるごとに核開発反対を主張してきた。
だがいまだに核軍縮の協議さえはじめない(冷戦時代、米・ソ間ではしばしば協定が締結されてきたにもかかわらず)5核兵器大国(米・ロ・英・仏・中)のエゴイズム、所有を黙認されているイスラエル、核兵器クラブに入会を許されたわけでもないが、ほとんど形式的な制裁しか受けなかったインドとパキスタン。こうした二重・三重の国際基準のなかで、北朝鮮だけがきびしい制裁を受けるのは決してフェアではない。
安倍政権が、国連安全保障理事会の憲章第七章にもとづく制裁決議に従い、制裁を行うことは当然だが、その枠を超えた日本独自の過剰な制裁は、北朝鮮の敵対心を掻きたてるだけだろう。さらに問題は、これに乗じて国民のナショナリズムを煽りたて、北朝鮮への憎悪に油を注ぐメディアや論調である。 いわゆる瀬戸際政策をとりながらも、いまなお「われわれの目的は朝鮮半島の非核化にある」と明言している北朝鮮は、結局は外交交渉を視野に入れているのだ。国民を飢えさせてなにが核開発だ、と非難するのはたやすいが、この細めに開けられた扉を大きく開かせる努力が必要だ。
ドイツ国民を破滅に導いたヒトラーの狂気を、金正日氏はそれこそ歴史認識として知っているであろうし、また逆に、核開発放棄によって多大の経済援助や投資を獲得したリビアのカダフィ大佐の例をもよく知っているはずだ。彼が決定した核実験も、今後の「核兵器開発放棄」をより高く売るための戦略かも知れない。
左翼やリベラルズはなぜ国民を味方にできなかったか
ニューヨーク・タイムズの書評紙(Oct.1,2006)に、マイラ・マクファースンの『“すべての政府は嘘をつく”;反逆のジャーナリストI.F.ストーンの生涯と時代』および『I.F.ストーンのベスト集』の書評が掲載された。
1971年の5月、首都ワシントンで私は、坂本義和氏の事前の紹介で彼に会うこととなった。ワシントンでもっとも美味だというコールド・ビーフの店に招待され、昼食の2時間を懇談した。当時ニクソン政権のヴェトナム政策をきびしく批判し、反戦学生たちの英雄でもあった彼は、すでに60歳代の半ばであり、眼鏡越しの眼光は鋭いが、親切な白髪の好好爺という感じであった。ただ帰りに当時流行の最先端であった緑色塗装のフォード・ムスタングを運転し、ホテルまで送ってくれたが、その取り合わせの妙に感じいったものである。
それはともかく、左翼リベラルズを代表する政治ジャーナリストとして一時代を画したストーンは、終始毀誉褒貶のさなかにあり、ときにはヴェトナム戦争の敗北を予言した予言者として称えられ、あるときはソヴェトのスパイとまで疑われ、いまイラク戦争批判の渦巻く時代にふたたび脚光を浴びる、といった次第であった。
彼の著作を熟読したわけではないのでその業績を評価することはできないが、この書評記事を読みながら私は、日米を問わず、「左翼やリベラルズはなぜ国民を味方にできなかったか」という疑問に囚われつづけた。いまもその疑問は完全に解けたわけではないが、主としてわが国について考えた一端を書き記してみよう。
あえて「国民」といったが、近代の国民国家(ネーション・ステート)の構成員を指すわけではなく、特定の国土に住むひとびと、といった程度の意味だと考えてほしい。とにかくわが国の左翼やリベラルズ、とりわけ戦後民主主義者とよばれる知識人たちが、その意味での国民を味方にすることができなかったことは、いまやその主張を代表する政治勢力が、共産党という特異な政党を除けば、社民党という弱小政党でしかないという事実が示している。残念なな事実だが、それはなぜだろう。
おそらくそれは、彼ら知識人たちが、その思考体系から感性や文化を脱落させ、観念やイデオロギーでのみ考え、主張していたことに主因がある。
国民の生活は、固有の自然環境に根ざし、それとの関連のなかで形成された歴史、そして文化、さらにはそのなかではぐくまれた感性に深くかかわっている。ラフカディオ・ハーンをはじめ、明治の初期にやってきた外国の知識人たちに感銘をあたえたのは、ゆたかな自然と共生し、繊細で詩的な感受性をもち、人情細やかな日本人の姿であった。
ハーンが予感していたように、この古き良き日本は、その後の富国強兵の帝国主義への道とその破滅によって多くが失われたが、まったく消滅したわけではない。欧米的近代化が徹底したいまでも、それはわれわれの心の奥底に眠っているといってよい。だが皇国史観に代表される軍国主義を嫌悪する左翼や戦後民主主義者たちは、それらすべてをひっくるめて封建的遺物として弾劾し、葬り去ろうとしたのだ。
だが感性や身体性に根ざした文化は、髪の毛を金髪に染めるようには変えることはできない。むしろわれわれの固有の文化を深く理解し、みずからのうちにその感性や身体性を回復し、ひとびとの魂に眠る「古き良き日本」に共感するところから、変革の思想や方策を構築しなくてはならない。
私が師でもある丸山真男を批判するようになったのは、彼が『古事記』を近代主義的な立場から切り捨て、明治天皇制のイデオロギー的先駆でもあるかのように扱ったことに、きわめて否定的な衝撃を受けたからである。『古事記』は古代人の壮大な宇宙論であり、われわれの祖先の残したすばらしい遺産なのだ。
しかし、そうかといって私は風土論や文明の生態史観を評価するわけではない。それらは結局、気候風土決定論であって、気候風土にかかわる人間社会のダイナミックで弁証法的な働きをほとんど無視しているからだ。たとえばアメリカ・インディアンを見ればわかるように、同じ気候風土にあっても、異なった多様な文化が生まれ、共生する。
『古事記』や『万葉集』、あるいは現代のひとびとの魂の奥深くに眠っている「感性としての思想」に共感し、愛することができれば、変革の思想や勢力は、はじめて国民を味方にすることができるだろう。
(注)拙著『感性としての日本思想──ひとつの丸山真男批判』(2002年、藤原書店)、および『古事記の宇宙論』(2004年、平凡社新書)をお読みいただければ幸いである。