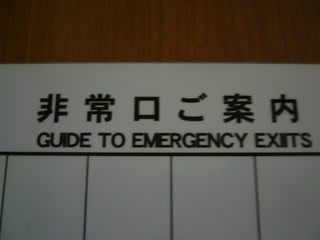5月23日(月)、北九州市立大学で日本ジョン・スタインベック学会が開催されました。
まずは、琉球大学名誉教授の仲地弘善会長から開会の辞があり、その後、開催校北九州市立大学の木原謙一副学長よりご挨拶をいただきました。
続けて、日本ジョン・スタインベック協会の元会長で関西大学名誉教授でもある中山喜代市先生の「スタインベック研究の過去、未来」と題する特別講演がありました。

中山先生は、国際的にも著名なスタインベック研究者であり、お名前を「きよし」とお読みするので、僕と同じであり、したがって僕が国際学会に出席しても、中山先生のおかげで、「若い方のきよし」(younger Kiyoshi)として名前をよく覚えていただけています。また、中山先生が率いるスタインベック・カントリーツアーに1994年に参加した際は、道中のホテルでは同部屋滞在をさせていただき、それ以来、色々とお世話になっています。
その後、熊本大学の馬渡美幸先生による、研究発表が行われ、午前中は終了し、昼食となりました。
僕の担当するシンポジウムは、午後最初の演目でした。
シンポジウムのタイトルは「スタインベックと『二十日鼠と人間』と演劇と」でした。
今回は、私が司会兼講師を担当し、他の講師2名は協会外から求める形を取りました。
僕が2008年に観た劇団Link Projectの『二十日鼠と人間』を演出されたLink Project主宰の為国孝和さんと、同じく『二十日鼠と人間』に出演された俳優の塚原英志さんにご登壇いただきました。

まずは僕が、「スタインベック作品の演劇化」と題して、今回のシンポジウムの内容が決まっていった経緯と、スタインベック作品が演劇化されることについて概略を話しました。

その後は、為国さんが「『二十日鼠と人間』を演出して」と題し、ご自身が演出された演劇の主要シーンを見せていただきながら、演出の狙い等を解説されました。

そして、塚原さんが「『二十日鼠と人間』でレニー役を演じて」と題して、知的障害を持ち非常に難しい役であるレニーを見事に演じていた時の体験をお話してくれました。

途中、機材の不調があり少し時間をロスしてしまいましたが、無事与えられた時間を使って有意義なシンポジウムができたのではないかと自負しています。
私たち研究者は、スタインベックの作品がどのように演劇化されるかについては非常に興味をもっているのですが、実際にそれを演出する演出家や役を演じる役者の方々からお話を聞けることがあまりないので、非常に貴重な機会になりました。
また、今回のシンポジウムへの参加が、演出の為国さんや俳優の塚原さんのお二人にとっても何らかの意味で今後の役に立ってくれれば幸いです。
その後は、総会があり、僕は学会誌
Steinbeck Studiesの新編集長に就任したことが紹介されました。
最後に、「第30回スタインベック・フェスティバル(於・サリーナス)報告」があり、僕もこのフェスティバルに参加した一員としてビデオ映像をもとに報告をさせていただきました。

学会後は片付けをし、その後恒例の慰労会に新幹線

の時間まで参加、帰路に着きました。
今回は、シンポジウムの進行役、スタインベック・フェスティバルの映像準備、学会誌
Steinbeck Studiesの編集作業と準備が大変な学会でしたが、無事終えることができ、ホッとしています。
























 の時間まで参加、帰路に着きました。
の時間まで参加、帰路に着きました。
 のすぐそばでした。
のすぐそばでした。

 。
。