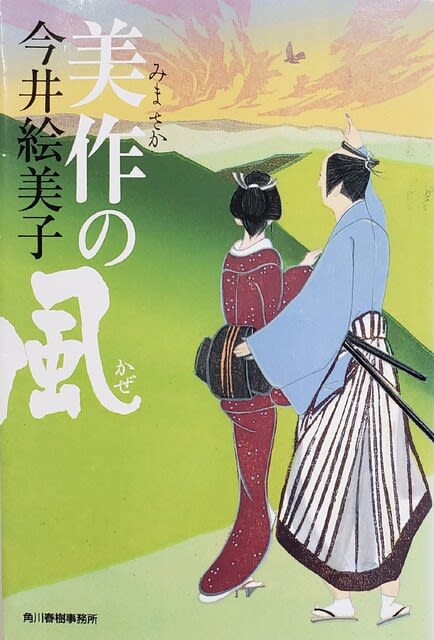2015年2月23日に実施した、第15回オーストラリア研修第2回説明会で説明した内容(一部非公開のため削除しています。また文字列が一部崩れています)です。
2014(平成26)年度第15回オーストラリア研修旅行第2回説明会 2015.2.23 研修室1・2
◎オーストラリア滞在中の約1週間は、皆さんの人生の中でも記憶に残る素晴らしい1週間になるはずです。
(でも、何か悪いことに巻き込まれたりすると、それが台無しになってしまいます…)
◎皆さんの人生を変えるくらいの出来事になる可能性もあります(学生時代に海外研修に参加した人たちの約5%がその後、「海外進出」(留学、ワーキングホリデー、海外活動、別の海外研修等に参加など)をしています。)
はじめに
説明の聞き方
説明者・英会話レッスンの先生の言葉がわからないときに隣の友達同士で確認しない(日本人学生によく見られる悪い点)
確認している間に大切な情報・解決のヒントを聞き漏らす(自分自身だけでなく友達も)
わからないときには説明者や先生と一対一で向き合い、言葉を交わす中で解決する
安全で快適な海外旅行のために
お金について
クレジットカード
できれば一枚あると便利(オーストラリアは日本よりクレジットカード社会化が進んでいる、万一の場合手持ちの現金がなくても助かる)
未成年の場合は保護者に相談
学生の身分でカードを作ることができる会社とそうでない会社がある
保護者の家族カードを発行してもらえる場合もある
オーストラリアではJCBよりもVISAかMasterのほうが使える店がはるかに多い。市内中心部ではJCBが使用できる店も増えている
トラベラーズチェック(TC)*あまり勧めません
お得だが、やや不便(パスポートなどの提示を求められるので)
大きい額面のTCで安いお菓子などを買い現金化するとよい
現金(日本円、現地通貨)
空港から自宅まで帰るための日本円は残しておく
お札は100ドル、50ドル、20ドル、10ドル、5ドル
コインは2ドル、1ドル、50セント、10セント、5セント(1セントコインがないので端数は切り上げまたは切り捨て)
100セントで1ドル
販売税(Sales Tax)がかかるが内税
帰国後お札は両替可、コインは不可(コインはお土産にもなる)
現地通貨を日本で準備しておくほうがよいがオーストラリアの銀行や両替所でも両替可
言葉について
基本英会話集などで勉強しておくとよい
携帯用の英和・和英辞典(合冊になったものが便利)か電子辞書があるとコミュニケーションに役立つ
わからなければ紙に書いてもらう(ペンと手帳を常に持参するとよい)
せっかくの機会なので積極的に参加すること
多少の間違いを気にしないで発言する、他人の間違いを笑わない
英語での自己紹介をする機会が何度かあるはずです。自己紹介ができるようにしておこう(自分のこと、家族のこと、出身地のこと、学校のことなど)(*家族や学校や出身地などの写真があると自己紹介が楽になります)
とにかくできるだけ多くの英語を聞き、英語に耳を慣らしておこう(できればオーストラリア英語を聞くのが理想的、オーストラリア英語やYouTubeなどのオーストラリアの映像など)
いろいろな場面を想定し、英語で何と言ったらよいか考えてみよう(イメージトレーニング)
電話について
引率教員としては、緊急連絡用に携帯電話の持参を強く勧めます。そのまま使える機種と、ICチップを別の電話機に入れて使う場合などがあるようです(最近のスマホはほとんどそのまま使えると思います)。詳しくは各携帯電話ショップ等で確認してください。
日本の保護者との連絡用としても携帯電話をそのまま使えるようにしていったほうが保護者も安
心
ホストファミリーとの連絡も便利です(連絡用の電話がない学生は受け入れないというホストファミリーもいます)
Skype, Lineなども利用可のはず(連絡用にこの研修旅行Lineグループを作ろうと思います)
国際電話はプリペイドカード、コレクトコール、クレジットカード通話(KDDI やIDC など)も利用できます
ホームステイ先での国際電話使用は緊急時以外極力控えること
Free Wi-fiが使えるところは増えています(メルボルン・ランゲージ・センターも利用可)。ホームステイ先で使えるかどうかは家庭によります。確実なのは、ポケットWi-fiをレンタルすることです。
服装・洗濯について
ホームステイ中は、基本的にその家庭の洗濯機を使わせてもらいます
洗濯ネットは便利
施設訪問の場合は質素な服装で、ただしチャイルドケアセンター訪問の場合は動きやすい服装で
朝晩は涼しいかもしれません。重ね着できる服装の組み合わせを考えましょう
日本の初春はオーストラリアの初秋です。
飛行機内は結構冷えることもあるので上着は機内に持ち込むほうがよい
危機管理について
交通事故に注意(車は左側通行で日本と同じですが、トラム乗り場が道路の中央分離帯部分にあることもあるので細心の注意を払う)
バッグ類の紐に引っかかりやすい部分を作らない(トラムなどの引っかかり事故や強奪防止)
犯罪の被害者にならないために(いい人を装ったり、日本語で近づいてくる人には注意)
現地の男性(女性)の誘いには慎重に(素性の明らかでない人にはついていかない)
山内は緊急連絡用に携帯電話を常時携帯している(引率教員の番号は登録しておいてください)
予期できないことが起こった場合もパニックにならず落ち着いて行動しよう
時間について
集合時間を守る
慣れない場所での移動では時間に余裕をもつのがポイント
メルボルンは日本より夏時間で2時間早い(日本が午後6時の時、メルボルンは午後8時)
団体行動上の注意
通路や道をふさがない
レストランや機内で騒がない
記念写真はできるだけ一つのカメラで撮影し帰国後データのやり取りをする(帰国後皆さんの(差し支えない)写真データを一つにまとめたいと思います(あるいは、Lineグループで共有)。
人数が多いので移動の際はできるだけ固まって移動する
単独行動はできるだけ避ける
体調管理
普段飲みなれた薬(風邪薬、頭痛薬、鎮痛剤など)を準備
薬についてはある程度英語で説明できるようにしておく(入国での税関チェックで)
体調が悪くなったら早めに引率教員や現地日本人スタッフに相談する
施設訪問
山内が通訳を行う
施設訪問は基本的に全員で同じ所に行く(医療・福祉・保育施設)
施設の方が英語で説明をしてくださるときにも熱心に聞く(後で通訳の日本語を聞けばいいと思って日本語で話したりしないように!)
質疑応答の時間には積極的に質問をする(質問がないのは説明をしてくれた人に対して失礼なので、前もって質問したいことを考えておくとよい)
チャイルドケアセンター訪問では一緒に遊ぶ時間を取ってもらえたら、折り紙などをさせてもらいたいと思います。折り紙を持参してください。また日本の歌や手遊びなどをぜひ披露しましょう。(幼児教育学科の人を中心に内容を検討しましょう)
高齢者施設では、利用者さんとの交流時間を取っていただけるようなら、折り紙や書道などの交流ができればと思います。(高齢者施設訪問が、小児科病院に変更になる可能性あり)
研修には含まれていませんが、山内の友人夫妻が開業している東洋医療クリニックを平日の夕方(日にち未定)見学訪問させてもらう予定です。その際、何か簡単な手土産をお願いします。
ホームステイ
ホームステイ先は、有償ですが、見ず知らずの皆さんに家庭の一部を提供してくださっています
感謝の気持ちを忘れずに。
むやみに他人のホストファミリーと比較をしない(皆さんのそれぞれのご家庭が違うのと同様、そ
れぞれのホストファミリーで条件は違う)。
ホストファミリーにいわゆる「当たりはずれ」がないとは言いませんが、ホストファミリー側か
ら見たら、学生の「当たりはずれ」も同様に存在します。そのようなことを気にするより、何
かの縁で滞在させてもらうことになったそのご家庭での有意義な過ごし方を考える(子どもが
いる家庭の希望が時々あるが、子育て中の家庭はそれだけで忙しいことが多く、ホームステイ
を引き受ける余裕がないことが多い。むしろ子どもが独立した退職者の家庭が、空き部屋とな
っている元子ども部屋を使ってホストファミリーになることもある。子どもがいれば子どもと
の交流も楽しめばいいし、大人しかいなければ大人とじっくり交流を楽しめばよい。いろいろ
とどこかに連れていってくれる家庭がいいと思うかもしれないが、自分で行きたいところに行
けないかもしれない。放任主義のほうが自分の好きなように動けるかもしれない。要はあなた
の心持ち次第)
帰国後もホストファミリー(や知り合った人たち)と交流を続けよう。海外の知り合いは一生の財
産です。これまでに多くの留学生を滞在させた経験のある家庭もありますが、滞在中だけで
はなく、滞在後も連絡を取り続けることによって印象に残る学生になることができます。(僕自
身は、自分が大学生の時(27年前)のホストファミリーと今でも交流、最初のオーストラリア訪
問時のホストファミリーとも交流(今回訪問予定の東洋医療クリニックを夫婦で開業している)
学生時代のアメリカのホストファミリーについてはこちら↓をご覧ください。
学生時代のホストファミリーとの再会
最初にメルボルンを訪問した時のホストファミリーについては、こちらをどうぞ↓。
オーストラリア研修旅行(2014年3月26日)
土産
ホームステイでお世話になるファミリーにはあまり高価でないものでよいが何か一つおみやげを用意するとよい
英会話レッスンの先生にもちょっとしたものがあれば話しかけるきっかけにもなる
自分の手作り、ふるさとの特産品などだとなおよい
いろいろな人に出会うのでちょっとしたものを多数用意しておくとよい(自分のメールアドレス入りの英語表記の名刺、プリクラ、写真なども役に立つ。文通のきっかけづくり)
個人の写真の他に大学案内パンフレット(自分が写っている人は特に)、ふるさとの町や新見市のパンフレット(英語表記もあるものが好ましい)を持っていくとよい。
本学のホームページ、新見市ホームページを参照
100円ショップも意外な掘り出し物があります。でも日本製ではないものもあります。
その他、いろいろな場面で知り合う方々に配るちょっとしたお土産もあったほうがいいでしょう。しおり、絵葉書、5円玉、折り鶴などそれぞれ考えて用意してみましょう。
自分、家族、友達、ペット、家の周り、学校の写真などがあると会話が広がります。ぜひ簡易アルバム、デジカメ、スマホなどに入れて持参しましょう。
食品は持っていかないほうが無難
企画
週末のオプショナルツアーでペンギンパレード見学以外の観光は皆さんの希望があれば、メルボルン市内の動物園、水族館、ユーリカ展望台、ヴィクトリアマーケット、サンデーマーケット、観覧車などを回る予定)
オーストラリア独特の食べ物(カンガルー、エミュー、クロコダイルなど)の料理を食べる会も実施可(皆さんの希望があれば)
その他
山内の新見から関西空港までの経路及び時間は決まり次第お知らせします。関西空港までの行き方が不安な人など、必要な場合は途中で合流してください
オーストラリアやメルボルンについての下調べ
オーストラリア、メルボルンについてはガイドブック類がたくさん出版されている。下調べをして何をしたいか、どこに行きたいかを考えておくと限られた時間を有効に過ごすことができる。インターネットを利用するのもよい。
オーストラリアについての本を読んだり、オーストラリアの映画を見たりすると、話題づくりになってよい
オーストラリアの各施設のどんな面を見たい・知りたいか考えておくとよい
可能なら自分の卒業研究テーマに関連させて調べてみるのもよい
逆に日本について、新見公立大学・短期大学について、新見・岡山について、それぞれのふるさとについてなど聞かれることも多い。基本的なこと(人口、特産物、国際姉妹都市など)は(英語で)答えられるようにしておく
インターネット利用
メルボルン市内にはインターネットカフェも多い
ホームステイ先でインターネットを利用させてもらえるかもしれない(May I use the Internet?などと確認して使用)
メルボルン・ランゲージ・センターのコンピュータールームも使用可能(予定)
携帯メールの送受信についても各携帯電話ショップで確認してください
エアメール
葉書は日本まで1枚1ドル50セント(料金は変更しているかも)。エアメール郵便は1週間弱で届
く
切手は郵便局以外あまり売っていない
郵便局は、研修する学校(メルボルン・ランゲージ・センター)と同じ通り(Lygon Street)にある(徒
歩3~4分)
荷造り
行きはスーツケースを満杯にしない(帰りのほうが荷物が増えるはず)
スーツケース(預け荷物)にはパスポート、現金、カメラを入れない(手荷物にする)
手荷物にははさみ、爪切り、ピンセット、カミソリなどを入れない(預け荷物に入れる)
花火は持っていかない(*以前空港で没収された人がいる)
語学学校またはホストファミリー宅に着くまでスーツケースは開けないつもりで荷造りをする
スーツケースの鍵、暗証番号を忘れないように。
筆記用具(ペン)は道中持参しておく
支払い
旅行代金支払いについては旅行会社さんの指示に従ってください。
現地で皆で食事した時などは、山内が立替で一括払いをすることが多くなりそうです(一人ずつの支払いは店がいやがる)。その場合は、後ほど(帰国後日本円でもよい)、支払ってください。
パスポートコピー
未提出者は旅行会社さんの指示に従ってください。
旅行保険
万一に備えて必ず保険には加入しよう。クレジットカードに旅行保険がついている場合もある
皆さんの空港までの行き方については日程が近付いてきたら山内が確認します(移動は余裕を持っておく)
万一遅れそうなときは山内携帯に連絡
質問など
質問があれば旅行会社の担当者さんか山内まで
皆さんへの個々の連絡がある場合は基本的にメールか電話を利用します。上記の電話番号から電話がかかって来たら出てください。学校からの一斉送信メールも使います(が、Lineグループができたら全体の連絡はそちらでします。)
その他
ホームステイ先周辺及び学校周辺の地図について
出発時に空港で配布予定(機内でご覧ください)
迷子カードについて
メルボルン・ランゲージ・センターで配布(学校住所とホームステイ先の連絡先を記入し、迷子時に親切そうな方に見せて助けてもらうためのカード)
後援会からの補助金を本日支給します。後援会からのこの補助金の支給は在学中1回のみです。看護学部の学生で「国際交流活動」の履修をする者は、報告書とレポートを提出すること。
小田奨学金について申し込む場合は、学務課に申し込むこと
学務課に海外渡航届を提出のこと(全員で1枚で構わない)
Facebook利用者は、「新見メルボルンの会」のグループを作って、これまでのオーストラリア研修参加者、メルボルンでお世話になっている方々などで情報交換、情報提供を行っています。入会希望者は、山内に友達リクエストをしてください。
現在、ワーキングホリデーでメルボルン滞在中の幼児教育学科卒業生の先輩にも会えると思います